- 「お彼岸って何をする日なの?」
- 「2025年のお彼岸はいつ?」
と疑問に思っていませんか?
お彼岸の時期になると、お墓参りやお供え物をする風習がありますが、意外とその意味や作法を知らない人も多いかもしれません。
- 「お彼岸はお盆と何が違うの?」
- 「お供え物は何がいい?」
- 「お彼岸に何を食べるの?」
- 「全国の風習にはどんな違いがある?」
と悩んでいる人もいるでしょう。
この記事では、お彼岸の由来や意味、2025年の日程、お彼岸にやるべきことをわかりやすく解説します。
この記事を読めば、お彼岸の過ごし方やお供え物のマナーがバッチリわかるようになります!
正しい知識を身につけて、ご先祖様に感謝の気持ちを伝えましょう。
お彼岸とは?意味と由来を解説
お彼岸の意味と由来そして歴史、期間と日程などを以下で解説します。
お彼岸とは?意味と由来を解説
お彼岸の意味とは?
- お彼岸(ひがん) とは、日本の仏教行事の一つで、春分の日と秋分の日を中心にした7日間のことを指す。
- この期間に 先祖供養を行う 習慣があり、多くの人が お墓参り や 仏壇の掃除 をする。
- 「彼岸」とは、仏教の概念で 「悟りの境地」 や 「極楽浄土」 を意味する言葉。
- 反対に、私たちが生きる現世は 「此岸(しがん)」 と呼ばれる。
お彼岸の由来と歴史
- インドや中国にはなく、日本独自の仏教行事 とされる。
- もともとは仏教用語の 「波羅蜜多(パーラミター)」(到彼岸)が語源で、「向こう岸へ渡る」つまり 「悟りを開く」 ことを意味する。
- 日本では 平安時代(806年) に初めて「彼岸会(ひがんえ)」が行われた記録がある。
- 当時は政争や天災が多く、人々の不安が大きかったため、極楽浄土を願う祈りと先祖供養が結びつき、お彼岸の行事が定着していったとされる。
- 春分の日・秋分の日は、太陽が真東から昇り、真西に沈む日。極楽浄土は 西の方角 にあるとされているため、この日に 西を拝む 習慣が生まれた。
お彼岸の期間と日程(2025年)
- お彼岸は、 春分・秋分の日を中日 に、前後3日を加えた 7日間。
- 2025年の春彼岸
- 彼岸入り:3月17日(月)
- 中日(春分の日):3月20日(木・祝)
- 彼岸明け:3月23日(日)
- 2025年の秋彼岸
- 彼岸入り:9月20日(土)
- 中日(秋分の日):9月23日(火・祝)
- 彼岸明け:9月26日(金)
お彼岸にやることなど
お彼岸に行うこと
- 仏壇・仏具の掃除
- ご先祖様のいる仏壇を綺麗にし、お供え物を用意する。
- 掃除前には 「今日はお掃除をさせていただきます」と合掌 するとよい。
- お墓参り
- 雑草を取り除き、墓石を水拭きする。
- 供花や線香、お供え物を用意 して供養する。
- お墓の手順
- 墓石の掃除(柔らかい布で拭く)
- 供花をお供え
- お線香を焚く
- 合掌し、故人に感謝の気持ちを伝える
- 注意点
- 他人のお墓には手を合わせない。
- お供え物は 必ず持ち帰る(カラスや動物の被害を防ぐため)。
- お供え物とお彼岸の食べ物
- ぼたもち(春)・おはぎ(秋)
- どちらも もち米とあんこ で作られるが、季節によって名前が変わる。
- 春は「ぼたもち」(牡丹に由来)→ こしあん
- 秋は「おはぎ」(萩に由来)→ つぶあん
- 精進料理
- 仏教的な観点から 肉や魚を避けた料理 を食べる。
- 彼岸そば、うどん、小豆飯 などが代表的。
- ぼたもち(春)・おはぎ(秋)
お彼岸とお盆の違い
| お彼岸 | お盆 |
|---|---|
| 年に2回(春分・秋分) | 年に1回(7月または8月) |
| 「現世(此岸)」から「極楽浄土(彼岸)」に近づく期間 | 「ご先祖様の霊を迎えて供養する期間」 |
| 仏壇の掃除、お墓参りが中心 | 迎え火・送り火、精霊流しなど特別な儀式 |
| 極楽浄土の思想が由来 | 盂蘭盆会(うらぼんえ)や祖霊信仰が由来 |
地域によるお彼岸の違い
- 福島県:「会津彼岸獅子」と呼ばれる獅子舞の奉納が行われる。
- 秋田県:「地蔵焼き」といって、地蔵の霊を供養する行事がある。
- 沖縄県:「お墓参り」よりも 仏壇で供養 するのが主流で、ウチカビ(あの世のお金)を燃やす風習がある。
まとめ
- お彼岸は ご先祖様に感謝を伝え、供養する期間 である。
- 「極楽浄土に近づくために善行を積む」という意味がある。
- ぼたもち・おはぎ、精進料理を食べる習慣がある。
- お墓参りや仏壇の掃除を行い、ご先祖様と向き合う機会にする。
- お盆とは違い 「私たちが極楽浄土へ近づく期間」 という仏教的な考えが背景にある。
春と秋の節目に、ご先祖様への感謝の気持ちを新たにしよう。
2025年のお彼岸の日程
2025年のお彼岸の日程は以下の通りです。
2025年の春のお彼岸
- 彼岸入り:3月17日(月)
- 中日(春分の日):3月20日(木・祝)
- 彼岸明け:3月23日(日)
2025年の秋のお彼岸
- 彼岸入り:9月20日(土)
- 中日(秋分の日):9月23日(火・祝)
- 彼岸明け:9月26日(金)
お彼岸は 春分の日と秋分の日を中日(ちゅうにち) とし、その前後3日間を合わせた 7日間 のことを指します。
この期間に お墓参りや仏壇の掃除 を行い、ご先祖様を供養するのが一般的です。
お彼岸にやるべきこととは?
お彼岸は ご先祖様への感謝を伝え、供養する期間 です。この期間に行うべきことを紹介します。
仏壇や仏具の掃除
- 仏壇はご先祖様がいる大切な場所 なので、きれいにして迎える。
- まず、ご先祖様に 「今日はお掃除をさせていただきます」と合掌 する。
- 仏具を外に出し、毛ばたきや柔らかい布で拭く。
- 写真を撮っておくと、掃除後に元の配置に戻しやすい。
- 花や水、お供え物を用意し、感謝の気持ちを込める。
- 仏壇がない家庭は、ご先祖様の写真を拭いたり、新しい花を飾るだけでもよい。
お墓参り
お墓参りはお彼岸の大切な習慣。以下の手順で行う。
お墓参りの手順
- 手桶に水を汲み、墓前で合掌礼拝。
- お墓周辺の雑草や枯葉を取り除く。
- 墓石に水をかけ、柔らかい布やスポンジで汚れを落とす。
- 硬いブラシやたわしはNG(墓石が傷むため)。
- 花立てに水を入れ、供花を飾る。
- ハサミを持参すると便利。
- お供え物(ぼたもち・おはぎなど)を半紙の上に供える。
- お線香を焚き、火は手で仰ぐようにして消す。(口で吹き消すのはNG)
- 数珠をかけ、30秒ほど黙祷して手を合わせる。
- 供物は必ず持ち帰る。(カラスや動物の被害を防ぐため)
お墓参りの注意点
- 他人のお墓に手を合わせない。
- お墓では派手な服装や強い香水は避ける。
- 夕方以降は避け、できるだけ午前中に行く。
お彼岸に食べるものを準備する
お彼岸は 精進料理 を食べるのが習わし。肉や魚を避けた料理が基本。
代表的なお彼岸の食べ物
- ぼたもち(春)・おはぎ(秋)
- 春は「ぼたもち」(牡丹の花に由来)→ こしあん
- 秋は「おはぎ」(萩の花に由来)→ つぶあん
- 小豆には邪気を払う力がある とされ、ご先祖様の供養として供えられる。
- 彼岸そば・うどん
- 消化に良い食べ物で、体調を整えるために食される。
- そばは五臓六腑の汚れを清めるといわれる。
- 小豆飯(あずきめし)
- 小豆を炊き込んだご飯で、「萩ごはん」とも呼ばれる。
- 赤飯とは違い、うるち米を使うのが特徴。
- 明け団子
- お彼岸の最後の日(彼岸明け)に供える団子。
- 「物事を貫き通す」意味があり、ご先祖様へのお土産とも。
- いなり寿司・五目寿司
- ご先祖様へのおもてなしの意味で供えられる。
- 現世の人々も一緒に食べることで、ご先祖様とつながる。
彼岸会(ひがんえ)への参加
- お寺では「彼岸会(ひがんえ)」と呼ばれる法要 が行われる。
- 可能であれば、お寺の法要に参加し、ご先祖様の供養をする。
- 法要に行けない場合は、自宅でお経を唱えたり、仏壇の前で静かに祈るだけでもよい。
六波羅蜜(ろくはらみつ)の実践
お彼岸は 「悟りの境地(彼岸)に近づくための修行の期間」 でもある。 以下の6つの行いを実践するとよい。
- 布施(ふせ):人に親切にし、施しを行う。
- 持戒(じかい):ルールを守り、反省する。
- 忍辱(にんにく):不平不満を言わず、耐え忍ぶ。
- 精進(しょうじん):努力し、誠実に生きる。
- 禅定(ぜんじょう):心を落ち着かせ、冷静に考える。
- 智慧(ちえ):物事の本質を理解し、正しく判断する。
家族と過ごす時間を大切にする
- お彼岸は、家族が集まりやすい時期。
- ご先祖様を偲びながら、家族との時間を大切にするのも供養の一つ。
- 亡くなった方の思い出話をすることも、供養の一環となる。
まとめ
お彼岸には、ご先祖様への感謝を込めて以下のことを行うとよい。
✅ 仏壇・仏具の掃除
✅ お墓参り
✅ ぼたもち・おはぎなどのお供え
✅ 彼岸会(法要)への参加
✅ 六波羅蜜の実践(善行を積む)
✅ 家族と過ごし、故人を偲ぶ
お彼岸は、単なるお墓参りだけでなく 「日頃の行いを振り返り、心を整える期間」 でもある。
今年のお彼岸は、改めて 「ご先祖様に感謝し、自分自身を見つめ直す時間」 にしてみてはいかがだろうか。
お彼岸に食べるもの
お彼岸には、ご先祖様への供え物や精進料理を食べる習慣があります。
ここでは代表的な食べ物とその意味を紹介します。
ぼたもち(春)・おはぎ(秋)
お彼岸の定番の供え物で、 もち米を炊いてつぶし、あんこで包んだ和菓子 です。
✅ 春は「ぼたもち」(牡丹の花に由来)
✅ 秋は「おはぎ」(萩の花に由来)
- 春は「こしあん」(小豆の皮を取り除いた滑らかなあんこ)
- 秋は「つぶあん」(収穫したばかりの小豆をそのまま使う)
なぜ小豆を使うのか?
- 小豆の赤い色には 邪気を払う力がある とされ、魔除けの意味を持つ。
- ご先祖様への供養として、昔から食べられてきた。
小豆飯(あずきめし)
もち米やうるち米に小豆を混ぜて炊いたご飯で、「萩ごはん」とも呼ばれる。
- 赤飯とは違い、蒸さずに炊くのが特徴。
- 小豆の赤色が邪気を払うとされ、お彼岸の時期に食べられる。
彼岸そば・うどん
お彼岸の時期は季節の変わり目で体調を崩しやすいため、 消化の良い食べ物を食べる習慣 がある。
- そば には 「五臓六腑を清める」 効果があるとされ、ご先祖様を迎える前に体を清める意味がある。
- うどんは、 地域によっては「彼岸うどん」 として食べることも。
明け団子
お彼岸の最終日に供える団子で、串に刺したものが多い。
- 意味:「物事を貫き通す」(団子が串に通っていることに由来)。
- あの世へ帰るご先祖様へのお土産 とも言われている。
いなり寿司・五目寿司
- 「ご先祖様へのおもてなし」として供えられる。
- いなり寿司は 「五穀豊穣を願う」 意味がある。
- 家族で食べることで、ご先祖様とのつながりを感じる とされる。
精進料理(肉や魚を使わない料理)
お彼岸は 仏教行事 なので、 動物の殺生を避けた「精進料理」 がふさわしい。
✅ 精進揚げ(野菜の天ぷら)
✅ 煮しめ(根菜の煮物)
✅ 豆腐料理(湯豆腐や白和え)
✅ 味噌汁(昆布や椎茸の出汁を使用)
- お彼岸は 「六波羅蜜(ろくはらみつ)」 の教えを実践する期間でもあるため、質素で身体に優しい食事を心がける。
ぼたもち・おはぎの別名
地域や季節によって、ぼたもち・おはぎには別の呼び名がある。
| 季節 | 呼び名 | 由来 |
|---|---|---|
| 春 | ぼたもち(牡丹餅) | 春の花「牡丹」に由来 |
| 夏 | 夜舟(よふね) | 船は着いたことが分かりにくい(搗かない餅=つき知らず) |
| 秋 | おはぎ(御萩) | 秋の花「萩」に由来 |
| 冬 | 北窓(きたまど) | 北の窓からは月が見えない(つき知らず) |
- 「つき知らず」 という言葉が、餅をつかずに作るぼたもち・おはぎと結びついている。
まとめ
お彼岸には、ご先祖様への供養として以下のものを食べる。
✅ ぼたもち(春)・おはぎ(秋)(邪気払いの小豆を使用)
✅ 小豆飯(萩ごはんとも)
✅ 彼岸そば・うどん(消化を助け、体調を整える)
✅ 明け団子(ご先祖様へのお土産)
✅ いなり寿司・五目寿司(ご先祖様へのおもてなし)
✅ 精進料理(動物性食品を避ける)
お彼岸の食べ物には 「感謝・供養・健康」 という意味が込められている。
今年のお彼岸は、これらの食べ物を用意して、ご先祖様を偲びながら家族でいただいてみてはどうだろうか。
お彼岸とお盆の違い
お彼岸とお盆は、どちらも ご先祖様を供養する行事 ですが、目的や時期、行うこと に違いがあります。
お彼岸とお盆の基本的な違い
| お彼岸 | お盆 | |
|---|---|---|
| 目的 | 「現世から極楽浄土へ近づくための期間」 | 「ご先祖様の霊を迎えて供養する期間」 |
| 時期 | 春と秋の年2回(春分・秋分を中心に7日間) | 夏の年1回(7月または8月) |
| 意味・由来 | 「極楽浄土は西にある」という考えに基づき、ご先祖様への感謝と自身の修行のための期間 | ご先祖様の霊が帰ってくるとされ、迎え火や送り火で供養する |
| 行うこと | 仏壇やお墓の掃除・お墓参り・供物を供える・六波羅蜜の実践 | 迎え火・送り火・お墓参り・精霊流し・お供え・盆踊り |
| 供養の方法 | 「こちら側(現世)から極楽浄土へ近づく」 → お墓参りをして供養 | 「ご先祖様が帰ってくる」 → 霊を迎え、おもてなしをして送り出す |
| 食べ物 | ぼたもち・おはぎ・小豆飯・精進料理 | 精進料理・お供え(そうめん・なす・きゅうり・落雁など) |
| 飾りや儀式 | 特に決まりはない | 迎え火・送り火・盆提灯・精霊馬(なす・きゅうり) |
お彼岸とは?
お彼岸の目的
- 極楽浄土へ近づくための修行をし、ご先祖様へ感謝を伝える。
- 先祖供養だけでなく、自分自身を見つめ直し、善行を積む ことが目的。
お彼岸の時期
- 春分の日と秋分の日を中心にした7日間。
- 春分の日(3月20日前後)、秋分の日(9月23日前後)を中日 とし、その前後3日間を合わせた 7日間。
お彼岸に行うこと
✅ 仏壇・仏具の掃除
✅ お墓参り(ご先祖様への感謝)
✅ ぼたもち・おはぎなどのお供え
✅ 精進料理を食べる
✅ 六波羅蜜(善行)を実践
お彼岸の食べ物
✅ ぼたもち(春)・おはぎ(秋)(小豆が邪気を払う)
✅ 彼岸そば・うどん(体調を整える)
✅ 小豆飯(萩ごはん)(ご先祖様への供養)
お盆とは?
お盆の目的
- ご先祖様の霊がこの世に戻ってくるとされ、その霊を迎えて供養し、再び見送る行事。
お盆の時期
- 一般的には 8月13日~16日(地方によっては7月)。
- 新盆(初盆):故人が亡くなって 初めて迎えるお盆。
お盆に行うこと
✅ 迎え火(13日):ご先祖様が迷わないように、玄関やお墓で火を焚く。
✅ お墓参り:供花・線香を供える。
✅ 盆棚・精霊棚の設置:仏壇の前に供物を置く棚を作る。
✅ 盆踊り:先祖供養のために踊る。
✅ 送り火(16日):お盆の終わりに、ご先祖様をあの世へ送り出す(京都の五山送り火など)。
お盆の食べ物
✅ 精進料理(煮物・そうめん・落雁など)
✅ 精霊馬(しょうりょううま)(なすやきゅうりで作る乗り物)
✅ 団子・果物・野菜のお供え
お彼岸とお盆の大きな違い
目的の違い
- お彼岸 → 「ご先祖様へ感謝し、極楽浄土へ近づくための期間」
- お盆 → 「ご先祖様の霊を迎え、もてなし、送り出す行事」
供養の仕方の違い
- お彼岸 → こちら(現世)から供養をする
- お盆 → ご先祖様の霊を迎え、見送る
時期の違い
- お彼岸 → 春と秋の年2回
- お盆 → 夏の年1回(7月または8月)
まとめ
| 違い | お彼岸 | お盆 |
|---|---|---|
| 目的 | 極楽浄土へ近づく修行の期間 | ご先祖様を迎えて供養し、送り出す |
| 時期 | 春分・秋分の前後7日間(3月・9月) | 8月13日~16日(地域によって7月) |
| 行うこと | お墓参り・仏壇の掃除・精進料理 | 迎え火・お墓参り・精霊馬・送り火 |
| 食べ物 | ぼたもち・おはぎ・小豆飯・そば | 精進料理・そうめん・なす・きゅうり |
| 供養の方法 | こちら(現世)から供養する | ご先祖様の霊を迎え、見送る |
お彼岸は 「修行と感謝」、お盆は 「迎えて送る」 という違いがある。
どちらも ご先祖様を大切にする大事な行事 なので、しっかりと供養を行いたい。
お彼岸の過ごし方と地域の風習
お彼岸は 春分・秋分の日を中心に7日間 あり、ご先祖様への感謝と供養を行う大切な期間です。
地域によっては独自の風習があり、さまざまな形で受け継がれています。
一般的なお彼岸の過ごし方
お彼岸の期間中、以下のようなことを行います。
① お墓参り
✅ 家族でお墓を訪れ、ご先祖様に手を合わせる
✅ 墓石や周囲の掃除をし、花や線香を供える
✅ 供物(ぼたもち・おはぎなど)を供え、感謝の気持ちを伝える
② 仏壇や仏具の掃除
✅ 仏壇のほこりを払い、仏具をきれいにする
✅ 花やお供え物(果物・ぼたもちなど)を飾る
✅ 線香を焚き、手を合わせてご先祖様に感謝を伝える
③ 彼岸会(ひがんえ)に参加
✅ お寺で法要が行われる「彼岸会」に参列し、お経を聞く
✅ 僧侶にお布施を渡し、ご先祖様の供養をする
✅ 個人で読経したり、写経をする家庭もある
④ 精進料理を食べる
✅ お彼岸は仏教の行事なので、肉や魚を避けた「精進料理」を食べる
✅ 代表的な食べ物
- ぼたもち(春)・おはぎ(秋)
- 彼岸そば、うどん、小豆飯
- 精進揚げ(野菜の天ぷら)、煮しめ、湯豆腐
⑤ 六波羅蜜(ろくはらみつ)の実践
お彼岸は「六波羅蜜(悟りに至るための6つの行い)」を意識する期間ともされています。
✅ 布施(ふせ):人に親切にする
✅ 持戒(じかい):道徳的に正しい行動をとる
✅ 忍辱(にんにく):我慢し、耐え忍ぶ
✅ 精進(しょうじん):努力を怠らない
✅ 禅定(ぜんじょう):心を落ち着け、冷静に考える
✅ 智慧(ちえ):物事の本質を正しく理解する
地域ごとのお彼岸の風習
お彼岸は全国で行われますが、地域によって独特な風習があります。
① 福島県(会津若松市)|「会津彼岸獅子」
✅ 春のお彼岸に 「会津彼岸獅子」 という獅子舞が行われる。
✅ 獅子舞は、疫病退散と五穀豊穣を願う意味を持つ。
✅ 昔、疫病が流行した際に獅子舞を奉納したところ収まったことが起源。
② 秋田県(能代市・大館市)|「地蔵焼き」「木の造花供え」
✅ 能代市の鶴形地域では「地蔵焼き」 という行事が行われる。
✅ 送り彼岸の日(お彼岸の最終日)に、河川敷で地蔵を焼いて供養する。
✅ 大館市では、冬の間に生花が手に入りにくいため、「木の造花」を供える 文化がある。
✅ 柳の木を削って花びらを作り、赤やピンクに染める。
③ 熊本県(阿蘇地方)|「彼岸籠り」
✅ 「彼岸籠り(ひがんごもり)」 という風習がある。
✅ お彼岸の期間に、阿蘇山に登って夕日を拝む。
✅ 昔は 「お彼岸の中日に夕日を拝むと極楽浄土へ行ける」 と信じられていた。
④ 佐賀県|「お彼岸を神社で行う」
✅ 一般的にはお寺で行う彼岸の法要を、神社で行う地域がある。
✅ お彼岸の日に、神社で ぼたもちや料理を持ち寄り、お神酒を酌み交わす風習 がある。
✅ 仏教だけでなく、神道の影響も強い地域ならではの文化。
⑤ 沖縄県|「ウチカビを燃やす」
✅ 沖縄では 「お彼岸だからお墓参りをする」という習慣は少ない。
✅ お墓よりも 仏壇にお参りする家庭が多い。
✅ ウチカビ(あの世のお金)を燃やし、ご先祖様に届ける 風習がある。
✅ お供え物(ウサギムン)を仏壇に供え、家族でウサンデー(供物を食べる)。
✅ また、春には 「清明祭(シーミー)」 という行事があり、お墓の前で食事をする習慣も。
まとめ
お彼岸は 日本全国で行われるご先祖供養の行事 ですが、地域によって風習が異なります。
✅ 一般的なお彼岸の過ごし方
- 仏壇やお墓の掃除をする
- お墓参りをする
- 彼岸会に参加する
- 精進料理を食べる
- 六波羅蜜を意識して過ごす
✅ 地域の特徴的な風習
- 福島県:「会津彼岸獅子」獅子舞で疫病退散
- 秋田県:「地蔵焼き」や木の造花を供える
- 熊本県:「彼岸籠り」で阿蘇山から夕日を拝む
- 佐賀県:「お彼岸を神社で行い、料理を持ち寄る」
- 沖縄県:「仏壇にお供えし、ウチカビ(あの世のお金)を燃やす」
どの地域も 「ご先祖様への感謝」 を大切にし、時代とともに独自の文化が育まれている。
今年のお彼岸は、地域の風習も意識しながら、より深い意味を持って過ごしてみてはいかがだろうか?
まとめ
お彼岸は、ご先祖様に感謝し、供養する大切な期間です。
2025年のお彼岸の日程を確認し、正しい作法でお墓参りや仏壇の供養を行いましょう。
また、お彼岸に食べるぼたもちや精進料理には、それぞれ意味が込められています。
地域ごとの風習を知ることで、新たな発見があるかもしれません。
お彼岸を通じて、家族やご先祖様とのつながりを感じる機会にしてみてください。
あなたの地域のお彼岸の過ごし方も、ぜひコメントで教えてください!






















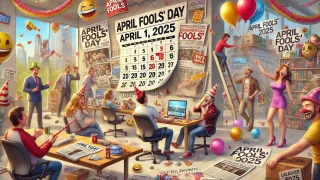



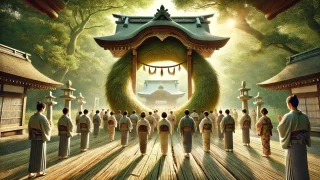



コメント