「防災の日っていつだっけ?」
「どうして9月1日なの?」
「何をしたらいいの?」
と、毎年なんとなく聞くけれど詳しく知らないまま過ごしていませんか?
近年は地震や台風などの大きな災害が増えています。
「うちは大丈夫」と思っていても、もしもの時は突然やってきますよね。
私も以前は、「防災の日って何か特別なことする日?」くらいにしか思っていませんでした。
でも、大切な人を守るためには備えが必要なんだと、実際の被災経験から強く感じています。
この記事では「防災の日」の由来や意味、そして今日からすぐできる備えまで、わかりやすくお話ししていきます。
読んでいただければ、「防災の日」がもっと身近に感じられて、家族や自分の安全を守る大事なきっかけになるはずです。
知ることで守れる命があります。ぜひ最後まで読んで、一緒に「もしも」に備えましょう!
防災の日とは?いつ・どんな日?
9月1日が「防災の日」に決まった理由
防災の日は 毎年9月1日 に決められています。
これは、1923年9月1日に起きた関東大震災 がきっかけです。
とても大きな地震で、たくさんの人が被害を受けました。
この出来事から、「災害はいつ起こるかわからない。
だからこそ、備えが大事だ」と多くの人が考えるようになったんです。
さらに、この時期は昔から台風がよく来る「二百十日(にひゃくとおか)」と呼ばれる季節でもあります。
そんな理由から、国が 1960年に9月1日を「防災の日」として決めた のです。
今では、この日に合わせて全国で防災訓練が行われたり、学校や職場でも避難訓練が行われるようになりました。
どんな意味があるの?災害への備えの日
防災の日は、「災害が起きたとき、自分や大切な人を守るために備える日」です。
地震や台風、大雨など、自然災害はいつどこで起きるかわかりません。
だからこそ、防災の日には
- 「もしもの時のために何を準備したらいいのか」
- 「家族や大切な人とどう連絡を取るか」
を考える大切なきっかけになるんです。
たとえば、防災グッズのチェックをしたり、避難場所を家族で話し合ったりするだけでも、もしもの時に落ち着いて行動できるようになります。
防災の日は、「備えることの大切さを思い出し、行動に移す日」なのです。
この日をきっかけに、家族みんなで防災について話してみましょう。
防災の日の由来と歴史を知ろう
関東大震災から生まれた「防災の日」
防災の日は 1923年9月1日に起きた関東大震災 が大きなきっかけで生まれました。
この地震は、東京や神奈川を中心にとても大きな被害をもたらしました。
たくさんの家が壊れ、火事も起きて、多くの人の命が奪われた悲しい災害でした。
その後、「こんな悲しいことを二度と繰り返してはいけない」「災害への備えが必要だ」という思いから、防災の日が作られたのです。
1960年に国が正式に防災の日を決めて、全国で防災の意識を高めるきっかけになりました。
たとえば、今では学校や会社、地域で防災訓練が行われています。
これは、昔の教訓を生かしているからこそ続いている大切な取り組みです。
つまり、防災の日は「過去の災害から学び、未来の命を守るための日」なんです。
二百十日ってなに?台風シーズンとの関係
防災の日が9月1日に決められたのは、もうひとつ理由があります。
それは、「二百十日(にひゃくとおか)」という言葉にも関係しているんです。
二百十日とは、昔の暦(こよみ)で立春から数えて210日目のこと。
だいたい 8月末から9月初め にあたります。
この頃は、ちょうど台風が多くなる季節と言われていて、農作物にも大きな被害が出やすい時期なんです。
だからこそ、「この時期に改めて災害への備えをしよう」という意味も込めて、9月1日が防災の日に選ばれました。
こうしてみると、防災の日は 地震だけでなく、台風や大雨などの自然災害に備える大切な日 だとわかりますね。
防災週間とは?2025年の日程と取り組み
2025年は8月30日〜9月5日
防災週間とは、毎年8月30日から9月5日まで 行われる、防災について考える特別な1週間です。
2025年も同じく、8月30日から9月5日 に実施されます。
この期間は、防災の日(9月1日)に合わせて、国や自治体が中心となり、全国でさまざまな取り組みが行われます。
なぜ防災週間があるのかというと、「災害への備えは一日では足りないから」です。
防災の日だけでなく、この一週間を使って、じっくり防災について考えたり、必要な準備を見直したりするために設けられているんですね。
たとえば、家族や地域の人たちと一緒に防災グッズのチェックをしたり、避難場所の確認をするだけでも大きな意味があります。
この防災週間は、「もしもの時に、命を守る行動ができるように備える時間」なんです。
防災訓練やイベントは全国で開催
防災週間中は、全国の学校や職場、地域で 防災訓練やイベント がたくさん開かれます。
地震や火災、台風などを想定した避難訓練や、消火訓練、防災グッズの展示会など、内容はさまざまです。
こうした取り組みは、「知っているつもり」になりがちな防災について、実際に体験しながら学べるとてもいい機会になります。
たとえば、地域の防災訓練に参加するだけでも、どこに避難するのか、どんな手順で動くのかがよくわかるようになりますよ。
このように、防災週間は「自分や家族の命を守るために、行動できる力をつける期間」なんです。
ぜひ、今年は防災週間のイベントや訓練に参加してみましょう。
ほかにもある!「津波防災の日」や「地域防災の日」
11月5日は「津波防災の日」
防災の日だけでなく、日本には 「津波防災の日」 という特別な日もあります。
毎年 11月5日 に決められていて、「津波の怖さを忘れずに、しっかり備えよう」という意味が込められているんです。
この日は、1854年の大きな「安政南海地震」 がきっかけになっています。
この地震では、大きな津波が押し寄せ、多くの人が被害にあいました。
でも、その中で「稲むらの火」というお話が残っています。
ある村人が、収穫したお米の稲に火をつけて、みんなを安全な高台に避難させたという話です。
この出来事から、「津波の怖さを忘れないこと」「命を守る行動を考えること」の大切さを伝えるために、津波防災の日が生まれました。
たとえば、海の近くに住んでいる人は、この日に改めて避難経路を確認したり、ハザードマップを見直したりすると安心ですね。
各地で設けられている「地域防災の日」
実は、日本各地には 「地域防災の日」 という日もあります。
それぞれの地域で過去に起きた災害を教訓に、「自分たちのまちは自分たちで守ろう」という思いを込めて作られているんです。
たとえば、静岡県では1月17日が「県民防災の日」 に決められています。
これは、阪神・淡路大震災の経験をもとにしているんですよ。
そのほかにも、地元ならではの防災イベントや訓練が行われる地域も多く、地域ごとに防災意識を高める取り組みが広がっています。
こうした「地域防災の日」は、普段なかなか考える機会の少ない災害について、身近な場所で学べる大切な日なんです。
このように、「防災の日」だけでなく、「津波防災の日」や「地域防災の日」もあることで、
さまざまな災害に目を向けて、より広く・深く備える意識が高まりますね。
防災の日にやるべきこと【家庭・企業・地域別】
防災の日は、家族や職場、地域で「もしもの時にどう動くか」を考える絶好のチャンスです。
具体的にどんな準備や見直しをすればいいのか、順番に見ていきましょう。
家庭での備え|防災グッズ・備蓄の確認
防災の日には、まず 家庭での備え を見直すことが大切です。
災害はいつ起きるかわからないので、備えがあれば安心ですよね。
その理由は、災害が起きると電気や水道、ガスが止まってしまうことが多いからです。
必要なものが手元にないと、とても困ってしまいます。
たとえば、防災リュックの中身をチェックしてみましょう。
懐中電灯、乾電池、非常食、水、ラジオ、簡易トイレなど、家族に必要なものがそろっているか確認します。
赤ちゃんや高齢者がいる家庭は、その人たちに必要なものも忘れずに準備しましょう。
こうして備えることで、いざという時に「やっておいて良かった」と思えるはずです。
企業や職場の備え|BCP(事業継続計画)を見直そう
会社やお店、職場でも 防災対策 はとても大事です。
災害が起きても、すぐに仕事を止めないための準備が必要になります。
そのために大切なのが BCP(事業継続計画) です。
これは、災害が起きた時に「どうやって事業を続けるか」を考えて決めておく計画のこと。
たとえば、建物の安全確認や、従業員の安否確認の方法、連絡手段をしっかり決めておくと安心です。働く人の命を守ることが、会社の大切な役目にもなります。
防災の日には、この計画がきちんと機能するかどうかを見直してみましょう。
地域での防災|避難場所やハザードマップの確認
地域での防災も、とても大切です。
大きな災害が起きた時には、ご近所さん同士で助け合う場面がたくさん出てきます。
そのためには、まず 避難場所 や ハザードマップ を確認しておきましょう。
ハザードマップを見ると、自分の住んでいる場所がどんな危険がある地域なのかがわかります。
地震、津波、川の氾濫など、想定される被害を知っておくことが命を守る力になります。
地域の防災訓練に参加するのも、とても良い機会になりますよ。
ペットの防災も忘れずに!
そして忘れてはいけないのが、ペットの防災 です。
ペットも家族の一員だからこそ、災害時にどうするか考えておく必要があります。
理由は、避難所によってはペットが一緒に入れない場所もあるからです。
そのため、ペット用の防災グッズ(ごはん・水・トイレ用品・キャリーバッグなど)も準備しておくと安心です。
たとえば、ペットと一緒に避難できる場所を事前に調べたり、慣れさせておくと、いざという時にも落ち着いて行動できます。
家族みんなが安心できるように、ペットの備えも忘れずに考えておきましょう。
このように、防災の日は 家庭・企業・地域・ペット それぞれの視点で「もしもの備え」を見直す、とても大事な日なんです。
小さなことからでも、できることを始めてみましょう。
最新トピック|2025年以降の防災と課題
近年増える地震・台風への備え
今、日本では地震や台風などの自然災害が増えています。
だからこそ、これまで以上に「防災への備え」が必要になっています。
理由は、気候変動や地殻変動の影響で、大きな災害が起こるリスクが高まっているからです。
突然の大雨や、今まで安全だと思っていた地域でも地震が起こる時代になりました。
たとえば、毎年のように発生する大型台風や豪雨災害は記憶に新しいですよね。
家や道路が壊れたり、川があふれたりする被害が全国で起きています。
だからこそ、「自分の地域でどんな災害が起こりやすいのか」を知り、具体的な備えをしておくことがますます大切になってきています。
南海トラフ地震などの巨大災害への警戒
特に心配されているのが、「南海トラフ地震」などの巨大地震です。
これは、日本の南側の海の下で起きると予測されている大地震で、もし発生すれば とても大きな被害が出る と言われています。
南海トラフ地震は、過去に何度も日本を襲ったことがあり、次にいつ起きてもおかしくない状況です。地震だけでなく、大きな津波も発生すると予測されています。
たとえば、政府や自治体も「最大クラスの被害」を想定して、避難計画や対策を進めています。
でも、それだけでは足りません。
私たち一人ひとりが、自分の命や家族を守るために、今から備えておくことが必要です。
能登半島地震など最近の災害から学ぶべきこと
最近では、能登半島地震(2024年) が記憶に新しいですね。
この地震では、家が壊れたり道路が寸断されたりして、多くの人が避難生活を強いられました。
能登半島地震から学べることは、「地震はどこでも起こりうる」ということ。
そして、起きてからでは遅いという現実です。避難所生活の大変さや、支援が届くまでの時間の長さなども改めて考えさせられました。
だからこそ、2025年以降の防災では「被害を少なくする備え」と「避難生活まで考えた準備」が必要だと強く感じます。
これからの時代は、災害に「備えること」が当たり前の時代になります。
どんなに大きな災害が来ても、大切な人や自分の命を守れるように、今から一緒に備えていきましょう。
「防災の日」は家族と備えを見直すチャンス
「防災の日」は、家族や大切な人と 備えを見直す大切なチャンス です。
この日をきっかけに、もしもの時のための準備を始めましょう。
なぜなら、どんなに災害が大きくても「自分の命は自分で守る」気持ちがなければ助かるチャンスを逃してしまうからです。
そして、そのためには 「自助・共助・公助」 の考え方がとても大切になります。
たとえば、「自助」は自分や家族で防災グッズをそろえたり、避難場所を確認したりすること。
「共助」はご近所さんや地域の人たちと協力し合うこと。
「公助」は国や自治体が行う支援や救助のことです。
どれか一つだけではなく、この3つの力を合わせることで、命を守る可能性が高まります。
未来のために、今日から小さな一歩を踏み出しましょう。
たとえば、防災リュックの中身を確認する、家族で避難場所を話し合う、それだけでも大きな前進です。
防災の日は、「まだ大丈夫」ではなく「今できることから始めよう」と思えるきっかけの日。
大切な人と一緒に、備えについて考える時間を作ってくださいね。
まとめ
防災の日は、昔の大きな地震や台風の教訓から生まれた大切な日です。
でも、普段の生活の中ではつい意識しづらいですよね。
もしもの時に後悔しないためにも、こうした「防災の日」をきっかけに、家族で話し合ったり防災グッズを見直す時間を作ってみてください。
私も、防災の日に家族と一緒に避難場所を確認したり、防災リュックの中身を見直すようになりました。
実際にやってみると、意外と忘れていた物があったり、足りない物が見つかるものです。
大きな災害が起きる前に「備えること」が、家族や大切な人を守るためにはとても大事なことだと思います。
災害はいつ起きるかわかりません。
でも、備えることで「いざ」という時に落ち着いて行動できますよ。
防災の日を、そんなきっかけの日にしてみませんか?





























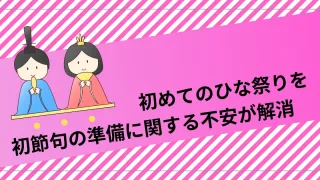


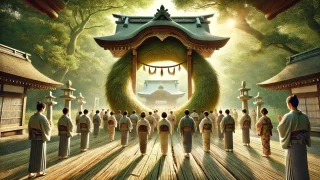




コメント