「ひな祭りや端午の節句の飾りは誰が買うの?」
この疑問を持つご家庭は多いのではないでしょうか?
- 「雛人形や兜は母方の実家が買うって聞いたけど、本当?」
- 「地域によって誰が買うか違うって聞くけど、実際はどうなの?」
- 「最近の家庭ではどうやって決めているの?」
このような悩みを抱える方は多いものです。
特に、初節句を迎える赤ちゃんがいる家庭では、「誰が買うべき?」という話題で親族間の意見が分かれ、悩まれることも少なくありません。
実は、ひな祭りの雛人形や端午の節句の五月人形・兜を誰が買うかには、地域による違いや昔からの風習が影響しています。
しかし、現代ではそのルールも変化しつつあり、家庭ごとに異なる決め方が増えてきました。
この記事では、「雛人形や兜は誰が買うのが正解?」という疑問について、地域ごとの違いや最新の傾向を分かりやすく解説していきます。
この記事を読むことで、家族間のトラブルを避けつつ、ベストな決め方ができるようになりますよ!
ひな祭り・兜は誰が買うのか問題とは?
ひな祭りの雛人形や端午の節句の兜・五月人形を「誰が買うのか」という問題については、地域や家庭の考え方によって異なります。伝統的な考え方から現代の傾向まで、詳しく解説します。
ひな人形は誰が買う?
- 伝統的には 母方の実家 が購入することが多い
- 理由は、昔は嫁いだ娘が実家に戻りにくかったため、孫と娘に会う口実として贈られた
- 地域によって異なるが、関西や九州では特にこの習慣が根強い
現代の傾向
- 核家族化により 両家で折半するケース が増えている
- 両親(パパ・ママ)が自分たちで購入することも多い
- 実家が費用を負担し、選ぶのは両親というケースも
兜・五月人形は誰が買う?
- 伝統的には 母方の実家 が購入するケースが多かった
- これは、ひな人形と同じく「孫と娘に会うため」という理由
- しかし、関東や東日本では 父方の実家 が用意する地域もある
- 地域によって異なり、関東では父方、西日本では母方が買うことが多い
現代の傾向
- 「どちらの実家が買うか」を 家庭ごとに相談して決める ことが一般的
- 両家で費用を折半する
- 夫婦が自分たちで購入するケースも増えている
- 祖父母が費用を負担し、両親が選ぶパターンもあり
地域差
- 関東・東日本 → 父方の実家が買うケースが多い
- 関西・西日本 → 母方の実家が買うケースが多い
購入時に起こりやすいトラブル
- 両家がそれぞれ購入し、兜が2つ届いてしまう
- どちらの実家が買うか決めず、節句までに用意できなかった
- 片方の実家だけに相談し、もう一方が不満を持つ
- 祖父母がサプライズで購入し、両親の好みと合わなかった
- 大きすぎて飾る場所がない
解決策
- 事前に 両家で相談して役割を決める
- 「誰が買うか」だけでなく 「誰が選ぶか」も決める
- お祝いのバランスを考え、片方の実家は五月人形、もう片方は鯉のぼりを購入するなど調整
兄弟がいる場合はどうする?
- 五月人形は本来「その子のためのお守り」なので、子ども1人に1つが理想
- ただし、住宅事情などを考慮し 1つを兄弟で共有する家庭もある
- 次男以降は「小さめの兜飾り」を購入するケースも
- 1人目の兜を母方が購入し、2人目の兜を父方が購入するなどの分担も可能
結局、誰が買うのがベストなのか?
- 昔ながらの習慣を尊重するなら母方の実家
- 地域の風習に従うなら、関東は父方、関西・九州は母方
- 公平さを重視するなら、両家で折半
- 親が主体的に選びたいなら、両親が購入
- 祖父母が費用を負担し、両親が選ぶ方法もアリ
まとめ
- 伝統的には 雛人形・五月人形ともに母方の実家が用意
- 関東では五月人形を父方の実家が買うこともある
- 現代では両家で折半や、親が自分たちで購入するケースが増加
- トラブルを避けるため、事前に両家で相談が重要
- 誰が買うかよりも、子どもの健やかな成長を願う気持ちが大切
どの方法を選ぶにせよ、大事なのは 子どもの成長を祝うこと です。
両家の意向を尊重しつつ、家族みんなで納得のいく形を選びましょう。
ひな祭りの雛人形は誰が買う?
雛人形を「誰が買うのか?」については、地域の風習や家庭の事情によって異なります。
昔ながらの習慣と現代の傾向を踏まえて詳しく解説します。
伝統的には母方の実家が購入
- 昔の風習では、母方の実家が用意するのが一般的
- 理由は、昔は結婚すると女性が夫の家に入り、実家に戻る機会が少なかったため
- 母方の両親が孫や娘に会う口実として雛人形を贈る風習が生まれた
- 特に関西・九州地方では、この習慣が今でも根強く残っている
現代の傾向
- 母方の実家が購入することが多いが、絶対ではない
- 両家の祖父母で折半するケースも増加
- 親(パパ・ママ)が自分たちで買う家庭もある
- 祖父母が費用を負担し、両親が選ぶことも
- お祝い金をもらい、そのお金で両親が購入する場合もある
最近では、家族で話し合って決めることが一般的になってきている
地域ごとの風習の違い
| 地域 | 誰が買うことが多いか |
|---|---|
| 関東 | 両家で話し合って決める or 両家折半 |
| 関西・九州 | 母方の実家が購入することが多い |
| 東北・北海道 | 父方の実家が購入するケースもあり |
- 関東では、両家で折半する家庭が増えている
- 関西や九州では「母方の実家が贈る」という伝統が残っている
- 東北や北海道では、父方の実家が贈るケースも見られる
雛人形購入時に起こりやすいトラブル
- どちらの実家が買うのか決めずにいたため、初節句までに用意できなかった
- 両家が別々に購入し、雛人形が2セット届いた
- 片方の実家が負担したのに、もう一方の実家が不満を持つ
- 祖父母がサプライズで購入し、両親の好みと合わなかった
- 大きすぎて飾る場所がない
→ 事前にしっかりと相談し、誰が購入するか、誰が選ぶかを明確にすることが大切
兄弟姉妹がいる場合はどうする?
- 雛人形は基本的に 「一人ひとつが望ましい」
- 理由:雛人形は「その子の身代わり」として厄を受けるもの
- 姉妹で共有する家庭もあるが、できれば一人ずつ用意するのが理想
- 住宅事情を考慮し、「小さめの雛人形」を妹用に用意するケースも
誰が買うのがベスト?
| 購入者 | メリット |
|---|---|
| 母方の実家(伝統的な方法) | 昔からの風習を守れる、母方の両親が満足する |
| 両家の祖父母で折半 | どちらの実家も関われる、公平感がある |
| 両親(パパ・ママ) | 自分たちの好みで選べる、家に合ったサイズが選べる |
| 祖父母が費用負担し、両親が選ぶ | 負担を減らしつつ、好きなデザインを選べる |
- 伝統を重視するなら 母方の実家
- 公平性を重視するなら両家折半
- 好みを重視するなら親が購入
- 出資は祖父母、選ぶのは親という方法もあり
大切なのは「誰が買うか」より「どう祝うか」
- ひな祭りの目的は 子どもの健やかな成長を願うこと
- 「誰が買うか」ではなく「家族全員で祝うこと」を大切に
- 事前に両家で相談し、お互いに納得できる形で準備することが重要
- 両家の関係を円満に保つためにも、購入方法や費用分担についてしっかり話し合うのがベスト
結論
「母方の実家が買う」という伝統はあるが、必ずしもそうしなければならないわけではない。
現代では、両家で話し合い、家庭に合った方法を選ぶのが主流になっている。
誰が買うかよりも、家族みんなでお祝いできることが大切!
五月人形・兜は誰が買う?
五月人形や兜を「誰が買うのか?」については、地域や家庭の考え方によって異なります。
伝統的な習慣と現代の傾向を踏まえながら、詳しく解説します。
伝統的な考え方
- 昔の風習では「母方の実家」が購入するのが一般的
- 理由:昔は結婚すると女性が夫の家に入り、実家に帰る機会が少なかったため
- 母方の実家が孫や娘に会うための口実として贈った
- 特に 関西・九州 ではこの風習が根強く残っている
- 関東・東日本では「父方の実家」が購入することも多い
- 理由:武家文化の影響が強く、跡取りの誕生を祝う意味があった
- 男児の誕生を重視する風習があったため、父方の家が用意するケースが多かった
現代の傾向
- 「母方の実家が買う」という伝統はあるが、必ずしもそうではない
- 両家の祖父母で折半するケースが増えている
- 親(パパ・ママ)が自分たちで購入する家庭も多い
- 祖父母が費用を負担し、両親が選ぶというスタイルも一般的
- お祝い金をもらい、そのお金で両親が購入するケースもある
最近では、「誰が買うか」よりも「どう祝うか」に重点を置く家庭が増えている
地域ごとの違い
| 地域 | 誰が買うことが多いか |
|---|---|
| 関東・東日本 | 父方の実家が購入することが多い |
| 関西・西日本 | 母方の実家が購入することが多い |
| 九州 | 母方の実家が購入することが一般的 |
- 関東では、武家文化の影響で父方が用意することが多い
- 関西・九州では、ひな人形と同様に母方の実家が贈るのが主流
- 現代では、両家で折半するケースや、両親が自分たちで購入するケースも増えている
購入時に起こりやすいトラブル
- どちらの実家が買うのか決めておらず、初節句に間に合わなかった
- 両家が別々に購入し、兜や五月人形が2セット届いた
- 片方の実家だけが負担し、もう一方の実家が不満を持つ
- 祖父母がサプライズで購入し、両親の好みと合わなかった
- 大きすぎて飾るスペースがない
→ 事前にしっかりと相談し、「誰が買うか」「誰が選ぶか」を決めることが大切
兄弟がいる場合はどうする?
- 五月人形や兜は本来「その子のためのお守り」としての意味がある
- 子ども一人に1つが理想的
- ただし、住宅事情を考慮し 1つを兄弟で共有する家庭も
- 次男・三男用に「小さめの兜飾り」を購入するケースも
- 長男の五月人形を母方、次男のものを父方が購入するなどの分担も可能
誰が買うのがベスト?
| 購入者 | メリット |
|---|---|
| 母方の実家(伝統的な方法) | 昔からの風習を守れる、母方の両親が満足する |
| 父方の実家(関東の風習) | 武家文化の影響を継承できる |
| 両家の祖父母で折半 | どちらの実家も関われる、公平感がある |
| 両親(パパ・ママ) | 自分たちの好みで選べる、家に合ったサイズが選べる |
| 祖父母が費用負担し、両親が選ぶ | 負担を減らしつつ、好きなデザインを選べる |
- 伝統を重視するなら「母方の実家」
- 地域の風習を重視するなら「関東は父方、関西・九州は母方」
- 公平性を重視するなら「両家で折半」
- 好みを重視するなら「親が購入」
- 出資は祖父母、選ぶのは親という方法もあり
大切なのは「誰が買うか」より「どう祝うか」
- 五月人形・兜の目的は 子どもの健やかな成長を願うこと
- 「誰が買うか」ではなく「家族全員で祝うこと」が大切
- 事前に両家で相談し、お互いに納得できる形で準備することが重要
- 両家の関係を円満に保つため、購入方法や費用分担についてしっかり話し合うのがベスト
結論
「母方の実家が買う」という伝統はあるが、地域差や家族の事情によって柔軟に決められる。
現代では、両家で話し合い、家庭に合った方法を選ぶのが主流。
誰が買うかよりも、子どもの成長を祝う気持ちが大切!
購入時のトラブルと対策
ひな祭りの雛人形や端午の節句の五月人形(兜・鎧飾り)は、初めての購入時に「誰が買うのか」「どんなものを選ぶのか」などでトラブルになることが多いです。
ここでは、初節句の人形購入時に起こりやすいトラブルと、その対策について詳しく解説します。
購入時に起こりやすいトラブルと対策
① どちらの実家が購入するか決めておらず、準備が間に合わない
【トラブル】
- 祖父母同士がお互いに「向こうが用意するだろう」と思い込む。
- 初節句直前になって「誰が買うの?」と慌てる。
- 人気の雛人形・五月人形が売り切れてしまう。
【対策】
✅ 両家で早めに相談する(最低でも2ヶ月前)
✅ 「誰が買うか」だけでなく「誰が選ぶか」も決める
✅ お祝い金をもらい、両親(パパ・ママ)が購入する方法も考える
✅ 購入時期は、雛人形は12月〜1月、五月人形は3月〜4月がベスト
② 両家がそれぞれ購入し、雛人形や兜が2セット届いてしまった
【トラブル】
- 祖父母が孫のためにと別々に購入し、2セット届く。
- 収納スペースがなく、両方を飾るのが難しい。
【対策】
✅ 事前に両家で話し合い、誰が用意するか決める
✅ 「雛人形は母方、五月人形は父方」など役割を分担する
✅ 片方の実家は「お祝い金」や「名前旗」など別のアイテムを担当
✅ どうしても両家が贈りたい場合は、小さいサイズのものを選ぶ
③ 片方の実家が負担し、もう一方が不満を持つ
【トラブル】
- 「母方の実家が雛人形・五月人形を購入したのに、父方の実家が何もしなかった」
- 逆に「父方が兜を買ったのに、母方の実家がもっと立派なものを買ってしまった」
- 両家の関係がギクシャクしてしまう。
【対策】
✅ 「雛人形は母方、五月人形は父方」など、負担を公平に分ける
✅ お祝い金をいただき、両親が購入する方法を提案
✅ 「人形は母方、飾りやお祝いの食事は父方」など役割分担
✅ 両家の気持ちを尊重しながら、お互いの意見を聞くことが大切
④ 祖父母がサプライズで購入し、両親の好みと合わなかった
【トラブル】
- 祖父母が選んだ雛人形や兜が、両親の好みと合わない。
- サイズが大きすぎる、部屋の雰囲気に合わない。
- 「せっかく買ってもらったから…」と我慢して飾ることに。
【対策】
✅ 事前に「どんなデザインが良いか」を夫婦で決めて伝える
✅ 購入前にカタログやオンラインショップで希望のデザインを共有
✅ 祖父母が購入する場合は、両親が一緒に選べるようにする
✅ サイズ感を重視し、飾るスペースを考慮したものを選ぶ
⑤ サイズが大きすぎて飾る場所がない
【トラブル】
- 立派なものを購入したものの、飾るスペースがない。
- 収納場所に困る(特に雛人形の7段飾り、鎧飾りのセットなど)。
【対策】
✅ 「どこに飾るか」を事前に確認し、サイズを決める
✅ コンパクトタイプや収納型の人形を選ぶ
✅ 「ケース飾り」「収納飾り」など、省スペース型の選択肢を検討
✅ 「祖父母に購入前に飾る場所の制約を伝えておく」ことが大切
⑥ 兄弟がいる場合の対応に困る
【トラブル】
- 「長男には兜を買ったけど、次男はどうする?」と迷う。
- 「兄弟で共有していいのか?」「次男・三男にも用意すべきか?」と悩む。
【対策】
✅ 「1人に1つが理想」だが、家庭の事情に合わせる
✅ 次男・三男には「小さめの兜飾り」や「名前旗」を追加する
✅ 長男の五月人形は母方、次男は父方と分担する方法も
✅ 兄弟で共有する場合、兄の人形に次男の名前を追加できるものを選ぶ
初節句の人形購入をスムーズに進める方法
✅ 1. 購入者を明確にする
- 母方の実家が買うのか、父方が買うのか、両家折半するのかを決める
- 事前に役割分担を決め、トラブルを回避。
✅ 2. デザインの希望を共有
- 「どんな雛人形・五月人形が良いか?」を夫婦で話し合い、カタログや店舗で具体的なイメージを固める。
- 祖父母が購入する場合も、事前に選ぶ機会を持つ。
✅ 3. 負担を分散する
- 「雛人形は母方、五月人形は父方」などの分担が定番。
- 「五月人形は母方、鯉のぼりは父方」など、アイテムごとに分けるのも◎
✅ 4. 早めに準備する
- 雛人形:12月〜1月がベスト
- 五月人形:3月〜4月がベスト
- 遅くなると人気のデザインが売り切れる可能性あり。
✅ 5. 両家の気持ちを尊重する
- 祖父母の「孫のために何かしたい」という気持ちを大切に。
- できるだけ両家が納得できる形で進める。
まとめ
| トラブル | 対策 |
|---|---|
| どちらが買うか決めず、準備が間に合わない | 早めに両家で相談し、役割を決める |
| 両家がそれぞれ購入し、2セット届く | 事前に購入者を決め、別のアイテムで調整 |
| 一方の実家だけ負担し、不満が出る | 費用を折半する、または別のアイテムを担当 |
| 祖父母がサプライズ購入し、好みと合わない | 事前にデザインの希望を共有し、両親が選ぶ |
| サイズが大きすぎて飾れない | 事前に飾る場所を決め、コンパクトなものを選ぶ |
初めての節句は、家族みんなの気持ちを尊重しながら、円満に準備を進めましょう!
誰が買うのが正解?話し合いのポイント
『ひな祭り・五月人形』誰が買うのが正解?話し合いのポイント
ひな祭りの雛人形や、端午の節句の五月人形(兜・鎧飾り)は、「誰が買うべきか?」 で悩む家庭が多いです。
伝統的な考え方、現代の傾向、円満に話し合うためのポイントを解説します。
1. 誰が買うのが正解?
実は、「誰が買わなければならない」という明確な決まりはない ため、家庭ごとに相談して決めるのがベストです。
ただし、昔からの風習や地域による違いがあるため、それを踏まえた上で話し合うのが良いでしょう。
① 伝統的な考え方
| 人形の種類 | 誰が買うのが伝統的か? | 理由・背景 |
|---|---|---|
| 雛人形(ひな祭り) | 母方の実家 | 娘が結婚すると実家に戻る機会が減るため、孫や娘に会う口実として贈る習慣があった |
| 五月人形(兜・鎧飾り) | 母方の実家(関西・九州) or 父方の実家(関東・東日本) | 関西・九州では「母方」、関東では「父方」が贈ることが多い |
- 関東・東日本:武家文化の影響で、父方の実家が男児の誕生を祝うために兜を贈ることが多い
- 関西・九州:貴族文化の影響で、母方の実家が用意するのが一般的
☞ ただし、現在はこの風習にこだわらない家庭も増えている!
② 現代の傾向
| 購入パターン | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 母方の実家が購入 | 伝統を重視できる | 父方の実家が何も負担しないと不満を持つ可能性 |
| 父方の実家が購入(関東では一般的) | 武家文化に沿った形 | 地域によっては違和感を持たれることも |
| 両家の祖父母で折半 | 負担が公平でトラブルが少ない | 折半の割合や方法を決める必要がある |
| 両親(パパ・ママ)が購入 | 好みのデザインを自由に選べる | 祖父母が「買いたかった」と思うことも |
| 祖父母からお祝い金をもらい両親が購入 | 祖父母の気持ちも汲みつつ、両親の希望も反映できる | 金額の相談が必要 |
☞ 最近は「両家で折半」や「お祝い金をもらって両親が購入」が増えている!
2. 誰が買うかを決める際の話し合いのポイント
スムーズに決めるために、以下の点を意識して話し合いを進めましょう。
① まずは両親(パパ・ママ)で方向性を決める
✅ 「母方の実家が買うべき」と考えるか?
✅ 「両家で公平に負担する」方法にするか?
✅ 「自分たちで買いたい」と思っているか?
✅ 祖父母に負担をかけず、お祝い金をもらって購入する方法はどうか?
この時点で、ある程度の方針を決めておくと、両家の話し合いがスムーズになる。
✅ 「伝統を重視するのか?」それとも「現代的な方法をとるのか?」を明確にする
✅ 「両家で平等な負担にしたい」という意向があれば伝える
✅ 祖父母がどうしたいか(贈りたい気持ちがあるか)を確認する
✅ 「お祝いの形」として、費用負担だけでなく、プレゼントや食事会での分担も考える
② 両家に相談する際のポイント
☞ 例:こんな伝え方がスムーズ!
👉 「雛人形や五月人形について、伝統的には母方が買うことが多いと聞きましたが、最近は両家で話し合って決める家庭も多いようです。どういう形がいいか相談させてください。」
👉 「おじいちゃん、おばあちゃんにも参加してもらって、お祝いの方法を一緒に考えたいのですが、どう思われますか?」
③ 費用の負担を分ける工夫
両家で負担を公平にするために、以下のような分け方を提案するのも◎
✅ 「雛人形は母方、五月人形は父方」 → 定番の分担方法
✅ 「五月人形は母方、鯉のぼりは父方」 → 端午の節句アイテムを分ける
✅ 「五月人形は父方、名前旗やオプション飾りは母方」 → サイズの大きいものと小物を分担
✅ 「両家で折半し、両親が選ぶ」 → 最近増えている方法
④ どんなものを買うかも相談する
購入者が決まっても、「どんなデザインやサイズのものを買うか」でトラブルになることも。
✅ 大きさや収納スペースを考えて決める
- 祖父母は立派なものを贈りたがるが、実際の住宅事情に合わないこともある
- コンパクトタイプ や 収納飾り を検討する
✅ デザインの好みを共有
- 祖父母が伝統的なものを好む一方、両親はモダンなデザインを好むことがある
- 事前に「どんなものがいいか」をカタログやオンラインショップで確認しておく
✅ 価格の目安を決める
- 雛人形:5万~20万円
- 五月人形:5万~15万円
まとめ:誰が買うのがベスト?
| 選択肢 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 母方の実家が購入(伝統) | 風習を守れる | 父方の実家が不満を持つ場合がある |
| 父方の実家が購入(関東の習慣) | 武家文化に沿っている | 母方が関与できない |
| 両家の祖父母で折半 | 平等でトラブルが少ない | 折半の割合や方法を決める必要あり |
| 両親が自分で購入 | 好みのデザインを自由に選べる | 祖父母が「買いたかった」と思うことも |
| 祖父母からお祝い金をもらい両親が購入 | 祖父母の気持ちを汲みつつ、両親の希望も反映できる | 金額の相談が必要 |
✔️ 正解は「家庭ごとに相談して決める」のがベスト!
✔️ 「誰が買うか」よりも「どう祝うか」を大切に!
初節句は家族みんなでお祝いする大切なイベント。
「誰が買うか」でモメるのではなく、「どうやって楽しく祝うか」を大切に話し合いましょう! 🎎🎏
「誰が買うか」よりも「誰のために買うか」
雛人形や五月人形をめぐって「誰が買うべきか?」で迷う家庭は多いですが、本当に大切なのは「誰が買うか」ではなく、「誰のために買うのか」 という視点です。
節句の人形は、親や祖父母のためのものではなく、子どもの健やかな成長を願うもの です。
この考え方を大切にしながら、円満に準備を進める方法を解説します。
そもそも雛人形・五月人形は何のためにあるのか?
雛人形(ひな祭り) 🎎
- 「子どもの健康と幸せを願う」ためのもの
- 平安時代の流し雛の風習が由来で、「人形が身代わりとなって厄災を引き受ける」 という意味がある
- 親や祖父母の自己満足ではなく、娘の無病息災と幸せな人生を願うために贈るもの
五月人形・兜(端午の節句) 🎏
- 「男の子が健やかに成長し、強くたくましく生きられるように」 との願いが込められている
- 兜や鎧には、「子どもを病気や災厄から守る」 という魔除けの意味がある
- 「誰が買うか」にこだわるのではなく、子どもを守る大切なお守りとして用意することが重要
「誰が買うべきか?」ではなく「どうすれば子どもにとって最善か?」を考える
「誰が買うか」にこだわると、両家の意見がぶつかり、トラブルになりがちです。
✅ 「子どもにとってどんな雛人形・五月人形がベストか?」を考える
✅ 「親や祖父母の見栄のためではなく、子どものためにどうするのが良いか?」を話し合う
これを基準に考えることで、感情的な争いを避け、家族全員が納得できる形になりやすいです。
「誰のために買うのか?」を意識するための話し合いのポイント
① 両親(パパ・ママ)が主体的に考える
- 「私たちの子どものために、どうするのがいいか?」 をまず夫婦で考える
- 親が選ぶことで、子どもにぴったりのものを用意できる
- 祖父母に相談する前に、ある程度の方向性を決めておくとスムーズ
② 両家の祖父母には「孫のためにどうするのがベストか?」という視点で相談
- 「伝統的には母方が買うことが多いですが、最近は家庭ごとに色々な形があるみたいです。
どういう形がいいと思いますか?」 - 「大切なのは孫が健やかに育つことなので、みんなで考えたいです」
✅ こうした伝え方をすることで、「誰が買うか」に固執せず、家族みんなで考える雰囲気になる
③ 「費用負担」ではなく「お祝いの形」を決める
- 「雛人形は母方、五月人形は父方」 という伝統を尊重するのも一案
- 「五月人形は母方、鯉のぼりは父方」 など、別の役割を考えるのもOK
- 「両家で折半し、親が選ぶ」 という方法も公平でトラブルが少ない
- 「祖父母からお祝い金をもらい、親が購入」 する形なら、祖父母の気持ちも反映しつつ、両親が最適なものを選べる
「子どもにとって何が最善か?」を意識して購入するためのポイント
✅ 「飾る場所」や「収納スペース」に合ったものを選ぶ
→ 祖父母は「立派なもの」を選びたがるが、住宅事情を考えてコンパクトなものも検討する
✅ 「子どものための人形」であることを忘れず、親が関与する
→ 祖父母だけで決めるのではなく、両親がしっかり選ぶことで、子どもにぴったりのものを用意できる
✅ 「人形が主役ではなく、子どもが主役」
→ 「高価なものを買うこと」が目的ではなく、「子どもの成長をお祝いすること」が大切
「誰が買うか」よりも「誰のために買うか」を大切に
| 考え方の違い | 問題点 | 解決策 |
|---|---|---|
| 「誰が買うか」にこだわる | 両家の意見がぶつかり、トラブルになりやすい | 「孫のために何がベストか?」を基準に話し合う |
| 「誰のために買うか」を意識する | 家族全員が納得しやすい | 「孫の健やかな成長を願う形を、みんなで考える」 |
✔️ 最適な形を決めるためのポイント
✅ 「誰が買うか」よりも「子どもにとって何が一番良いか」を考える
✅ 「親や祖父母の見栄」ではなく「子どものためのお祝い」であることを意識する
✅ 祖父母とも「孫のためにどうするのがいいか?」の視点で話し合う
✅ 「お祝いの形」として、役割を分担する方法を考える(費用の分担も含めて)
✅ 「子どもが健やかに育つこと」が何よりも大切という共通認識を持つ
結論:大切なのは「誰が買うか」ではなく「誰のために買うか」
雛人形や五月人形は、「両親や祖父母のため」ではなく「子どもの幸せと成長を願うためのもの」 です。
そのため、「どの家が買うか」よりも、「どうすれば子どもにとって最適か?」を話し合うことが最も大切 です。
家族みんなで「子どもの成長を祝う」という共通の気持ちを持ち、お互いの意見を尊重しながら最適な形を決めていきましょう! 🎎🎏✨
まとめ
ひな祭りや端午の節句の飾りを誰が買うかに決まりはなく、地域や家庭の事情によって異なります。
伝統的には母方の実家が用意することが多いですが、最近では両家で費用を折半したり、夫婦で購入するケースも増えています。
また、誰が買うかを決める際には、親族間でトラブルが起きないように事前に話し合うことが大切です。
お祝いの方法は家庭ごとに自由に決められるので、「子供のためにベストな形は何か?」を第一に考えて決めるのが理想的ですね。
「誰が買うか」にとらわれすぎず、大切なのは「子供の健やかな成長を願う気持ち」。
家族みんなで楽しくお祝いできる方法を見つけて、素敵な節句を迎えましょう!





























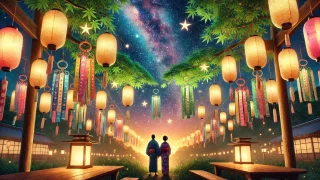







コメント