- 「敬老の日、どう祝えばいいの?」
- 「おじいちゃん、おばあちゃんに喜ばれるプレゼントは?」
- 「何歳から敬老の日を祝うのが正しいの?」
こんな疑問を持ったことはありませんか?
9月の第3月曜日にある「敬老の日」は、大切な家族に感謝を伝える素敵な機会です。
でも、次のように気を遣ったり、迷ったりする人も多いはず。
- 「まだ若いのにお祝いすると失礼かな?」
- 「何を贈れば喜ばれるの?」
この記事では、次のようなことを詳しく解説します。
- 敬老の日の日程
- 敬老の日の由来
- 年代別おすすめのプレゼント
- 年代別のプレゼントの相場
最後まで読めば、敬老の日に何をすれば良いかがわかり、迷うことなく準備できるようになりますよ!
敬老の日とは?基本情報と由来
敬老の日の基本情報
- 敬老の日(けいろうのひ)は、日本の国民の祝日の一つ。
- 毎年9月の第3月曜日に制定されている。
- 高齢者を敬い、その長寿を祝うことが目的。
- 2002年までは9月15日が固定日だったが、2003年からハッピーマンデー制度により現在の日程に変更。
- 老人の日(9月15日)や老人週間(9月15日〜21日)も、関連する記念日として制定されている。
敬老の日の由来
敬老の日の起源にはいくつかの説がある。
- 兵庫県多可町発祥説
- 1947年、兵庫県多可郡野間谷村(現在の多可町)で「としよりの日」が始まる。
- 村長の門脇政夫氏が「高齢者を大切にし、知恵を借りる村作り」を提唱し、9月15日を敬老の日の前身とする敬老会を開催。
- これが全国に広がり、1966年に「敬老の日」として国民の祝日となった。
- 聖徳太子の「悲田院」説
- 593年に聖徳太子が四天王寺に「悲田院」という福祉施設を設立したことが由来とされる説。
- 「悲田院」は孤児や老人の世話をする施設であり、福祉の原点ともいえる。
- 元正天皇の「養老の滝」説
- 717年に元正天皇が「養老の滝」に訪れた日とする説。
- 天皇は湧き水の効能を称え、年号を「養老」と改めた。
- この出来事が「長寿を祝う行事」として影響を与えたといわれる。
敬老の日の変遷
- 1950年(昭和25年):兵庫県が「としよりの日」を制定。
- 1951年(昭和26年):中央社会福祉協議会が「としよりの日」を9月15日とし、全国に普及。
- 1963年(昭和38年):老人福祉法が制定され、9月15日が「老人の日」に。
- 1966年(昭和41年):「敬老の日」として国民の祝日に制定。
- 2003年(平成15年):ハッピーマンデー制度により9月第3月曜日に変更。
敬老の日の祝い方
- 家族が集まり、祖父母や高齢の親を訪問する。
- 食事会やプレゼントを贈る。
- 施設や地域の行事として、高齢者向けのイベントが開催されることも多い。
- 100歳を迎えた方には、内閣総理大臣から「祝状」と「記念品(銀杯)」が贈呈される。
敬老の日の対象年齢
- 何歳から祝うかは明確な決まりがない。
- 60歳(還暦)や65歳(高齢者福祉の基準)を目安とすることが多い。
- ただし「まだ若い」と感じる方も多いため、孫が生まれたタイミングで祝うなど、状況に応じて配慮が必要。
世界の敬老の日
敬老の日に似た記念日は世界各国に存在する。
- アメリカ:9月第1月曜日の次の日曜日が「祖父母の日(National Grandparents Day)」。
- 中国:旧暦9月9日が「重陽節」として高齢者を敬う日。
- 韓国:10月2日が「老人の日」、10月が「敬老の月」。
- イタリア:10月2日が「Festa dei Nonni(祖父母の日)」。
まとめ
敬老の日は、高齢者に感謝を伝え、長寿を祝う日として定められた国民の祝日。兵庫県多可町の「としよりの日」が発祥とされており、その後全国へ広がった。近年では、孫が生まれたタイミングでお祝いを始めることが多く、家族の絆を深める日として大切にされている。H3: 2025年の敬老の日はいつ?
- 2025年の敬老の日は「9月15日(月・祝)」
- 9月の第3月曜日に設定されている
敬老の日の由来と歴史
1. 敬老の日の始まり
- 敬老の日の起源は、兵庫県多可町(旧野間谷村)にある。
- 1947年(昭和22年)、村長の門脇政夫氏が「としよりの日」を提唱。
- 戦後の混乱期に高齢者を敬い、知恵を借りることを目的として始められた。
- 9月15日を「としよりの日」として、55歳以上を対象に敬老会を開催。
- 農閑期で気候の良い時期だったため、この日付が選ばれた。
- 「養老の滝」伝説にちなんだともいわれる。
2. 全国への広がり
- 1950年(昭和25年):兵庫県が「としよりの日」を制定。
- 1951年(昭和26年):中央社会福祉協議会(現在の全国社会福祉協議会)が9月15日を全国統一の「としよりの日」と定める。
- 1963年(昭和38年):老人福祉法が制定され、9月15日を「老人の日」、9月15日〜21日を「老人週間」とする。
- 1966年(昭和41年):
- 「国民の祝日」として「敬老の日」が制定」。
- 「老人の日」という名称が「敬老の日」に変更される。
- 子どもの日や成人の日と並び、高齢者を敬う日として全国的に定着。
3. 9月15日から「9月第3月曜日」へ
- 2001年(平成13年):祝日法改正によりハッピーマンデー制度が導入される。
- 2003年(平成15年):
- 9月15日から「9月の第3月曜日」に移動。
- 初年度の2003年は偶然9月15日だったため、変更後の初適用は2004年の9月20日。
- 当時の敬老の日提唱者・門脇政夫氏や高齢者団体が変更に反対した。
- 同時に9月15日は「老人の日」として復活し、9月15日〜21日は「老人週間」として老人福祉の啓発期間となる。
4. 敬老の日の日付の由来
敬老の日が9月15日だった理由には、以下の説がある。
- 野間谷村で敬老会が9月15日に開催されたため
- 農閑期で天候が良い9月中旬を選んだ。
- 聖徳太子が四天王寺に「悲田院」を建てた日とされる
- 593年9月15日に聖徳太子が大阪の四天王寺に「悲田院」を設立。
- 悲田院は、孤児や老人を保護する日本最古の福祉施設。
- 敬老の日の由来の一つとされるが、日付の確証はない。
- 元正天皇が「養老の滝」に訪れた日
- 717年9月15日、元正天皇が岐阜県の「養老の滝」を訪れる。
- この滝の水を「老を養う若返りの水」として称え、「養老」と改元。
- 長寿を祝う風習が生まれたとも言われる。
5. 敬老の日の現在
- 毎年9月の第3月曜日に定められ、高齢者への感謝や長寿を祝う日として定着。
- 内閣総理大臣から100歳を迎えた人に「祝状」と「記念品(銀杯)」が贈られる。
- 老人福祉法に基づき、9月15日が「老人の日」、9月15日〜21日が「老人週間」として各種イベントが開催。
- 高齢化社会が進む中、敬老の日は単なるお祝いではなく、福祉のあり方を考える機会にもなっている。
まとめ
敬老の日は、1947年に兵庫県多可町で始まり、全国に広まった。
「としよりの日」から「老人の日」へ、そして「敬老の日」として国民の祝日に制定された。
現在は9月の第3月曜日となり、家族が集まり、高齢者を敬う大切な日となっている。
敬老の日は何歳から祝う?
1. 敬老の日の対象年齢に決まりはない
- 敬老の日は「多年にわたり社会に尽くしてきた高齢者を敬い、長寿を祝う日」とされているが、明確に何歳から祝うべきかという決まりはない。
- 国や自治体の基準も統一されておらず、個々の考え方や家庭の事情によって異なる。
2. 一般的な年齢の目安
敬老の日の対象年齢について、一般的な基準として考えられるのは以下の通り。
- 60歳(還暦)
- 日本では昔から還暦(60歳)を長寿の節目として祝う文化がある。
- 還暦を迎えたタイミングで敬老の日のお祝いを始める家庭もある。
- 65歳(高齢者福祉の基準)
- 老人福祉法では65歳以上を「高齢者」と定義。
- 各種シニア割引(公共交通機関や施設)などの対象も65歳以上が多い。
- そのため、敬老の日も65歳からお祝いする家庭が増えている。
- 70歳以上(シニア意識)
- 現在の60代は「まだ若い」と考える人が多い。
- 70歳以上になってから「敬老の日」に祝われることを受け入れる人が多い。
- 実際にアンケートでも「70歳以上が敬老の日の対象」という意見が多い。
- 75歳(後期高齢者の基準)
- 医療制度では75歳以上を「後期高齢者」と定めている。
- 健康寿命も伸びているため、75歳からお祝いを始める家庭もある。
3. 「孫ができたら」という考え方
- 年齢に関係なく、孫が生まれたタイミングで敬老の日を祝うことも多い。
- 「年齢ではなく、おじいちゃん・おばあちゃんになったことを祝う日」と考える人もいる。
- 孫からのプレゼントやメッセージがきっかけで、お祝いを受け入れる人も増えている。
4. 相手の気持ちを考えることが大切
- 「まだ若いのに敬老の日を祝われるのは抵抗がある」という人も多い。
- お祝いをする前に、相手の気持ちを考え、失礼にならないようにするのが大切。
- 敬老の日に限らず、感謝の気持ちを伝えることが重要。
まとめ
敬老の日は何歳から祝うという決まりはなく、一般的には60歳、65歳、70歳、75歳などが目安とされる。
しかし、相手の気持ちを尊重し、孫が生まれたタイミングや本人が納得する年齢でお祝いを始めるのが理想的。
敬老の日に贈るプレゼントの選び方
敬老の日のプレゼントは、相手の年齢や好み、ライフスタイルに合わせたものを選ぶことが大切です。
年齢に決まりがないため、「何を贈るか」に迷うこともありますが、相手の気持ちに寄り添った贈り物を選ぶことで、感謝の気持ちがより伝わります。
プレゼントを選ぶポイント
① 相手のライフスタイルに合ったものを選ぶ
- アクティブな高齢者:健康グッズ、ウォーキングシューズ、スポーツ用品など
- お家で過ごすことが多い方:リラックスグッズ、趣味関連のアイテム、インテリア雑貨など
- 食べることが好きな方:お取り寄せグルメ、スイーツ、果物など
② 体調や好みに配慮する
- 食べ物を贈る場合:柔らかいものや消化の良いもの、好みに合うものを選ぶ
- 香りの強いもの(アロマ、花):香りに敏感な方には控えめなものを
- サイズが必要なもの(衣類・靴):好みやサイズを事前に確認しておく
③ 特別感のあるものを選ぶ
- 名入れギフト:マグカップ、タオル、湯呑みなど
- 記念品や思い出に残るもの:フォトフレーム、アルバム、手作りの品など
④ 実用的なものを選ぶ
- 使いやすい家電:電動歯ブラシ、マッサージ機、電気毛布など
- 日常で役立つもの:湯呑み、スリッパ、エプロンなど
プレゼントの種類別おすすめアイテム
① グルメ・食べ物
- 和菓子・洋菓子(どら焼き、カステラ、プリン、ゼリー)
- お取り寄せグルメ(うなぎ、肉、魚介類)
- 健康志向の食品(低糖質スイーツ、無添加食品)
- 高級フルーツ(シャインマスカット、メロン)
② リラックス&健康グッズ
- マッサージ器(首・肩用、足裏用)
- ストレッチグッズ(ヨガマット、健康器具)
- リラックスアイテム(アロマ、入浴剤)
③ ファッション・雑貨
- パジャマ・ルームウェア
- ストール・カーディガン
- スリッパ・靴下
- 帽子・手袋
④ 趣味に合わせたギフト
- 園芸が好きな方:観葉植物、盆栽、花束
- 読書が好きな方:ブックカバー、電子書籍リーダー
- 手芸が好きな方:刺繍キット、毛糸セット
⑤ 旅行や外出向けのギフト
- 温泉旅行や宿泊ギフト
- 食事券
- ウォーキングシューズ
- 軽量リュックサック
プレゼントの予算
- 3,000円未満:お菓子、花束、雑貨
- 3,000円〜5,000円:スイーツセット、名入れグッズ、ストール
- 5,000円〜10,000円:高級食材、マッサージ機、ファッションアイテム
- 10,000円以上:旅行券、豪華ギフトセット、家電
避けたほうがよいプレゼント
① 縁起が悪いとされるもの
- ハンカチ:「手切れ」を連想させる
- 櫛(くし):「苦」「死」を連想させる
- 靴や靴下:「踏みつける」という意味合いがある
② 使いにくい・負担になるもの
- 重すぎるもの(持ち運びが大変なもの)
- 管理が大変なもの(高級な生花、賞味期限の短い食品)
一緒に過ごす時間が最高のプレゼント
- 食事に招待する
- 手紙やメッセージを贈る
- 孫と一緒に訪問する
- 手作りのプレゼントを用意する(似顔絵、アルバムなど)
まとめ
敬老の日のプレゼント選びで大切なのは、「相手の好みやライフスタイルに合ったものを選ぶこと」。高齢者向けの実用的なものや、リラックスできるアイテム、思い出に残るギフトなど、相手に喜んでもらえるものを贈りましょう。
何よりも、「感謝の気持ちを伝えること」が一番のプレゼントです。
敬老の日の祝い方アイデア
敬老の日は、祖父母や高齢の家族に感謝の気持ちを伝え、長寿をお祝いする大切な日です。
単にプレゼントを贈るだけでなく、一緒に楽しい時間を過ごすことで、より思い出に残る日になります。
ここでは、自宅でのお祝い・外出・オンライン・手作りのプレゼントなど、さまざまな祝い方のアイデアを紹介します。
自宅でのお祝いアイデア
① 家族みんなで食事会を開く
- おじいちゃん・おばあちゃんの好きな料理を用意する。
- おせち料理のように「長寿」を願う縁起の良い料理を取り入れるのもおすすめ。
- 赤飯(お祝いの定番)
- うなぎ(滋養強壮)
- そば(長寿の象徴)
- 茶碗蒸し(柔らかく食べやすい)
② 一緒に料理をする
- 孫と一緒にクッキーやおにぎりを作ってプレゼントする。
- おばあちゃん・おじいちゃんに昔の家庭料理を教えてもらうのもよい。
③ 家でゆったりと過ごす
- 映画や昔の思い出の写真を見ながら会話を楽しむ。
- 好きな音楽を流してリラックスする。
- 孫が手作りのプレゼントを渡す。
外出して楽しむ祝い方
① 温泉や日帰り旅行
- 近場の温泉旅館やホテルでのんびり過ごす。
- 敬老の日向けの温泉プランを利用する。
② 一緒にお出かけ
- 庭園や公園で散歩
- 美術館や博物館巡り
- 動物園や水族館で孫と一緒に楽しむ
③ 特別なランチやディナー
- 和食・寿司・フレンチなど、好きな料理を一緒に食べに行く。
- 個室付きのレストランやホテルのビュッフェもおすすめ。
オンラインでのお祝い(遠方の方へ)
① ビデオ通話でお祝い
- ZoomやLINEビデオ通話で顔を見ながら「おめでとう!」を伝える。
- 孫がメッセージや歌を披露すると特別感が増す。
② オンラインギフトを活用
- 食事券や旅行券をオンラインでプレゼント。
- デジタルフォトフレームに写真を送る。
③ サプライズ動画を作成
- 家族みんなで感謝のメッセージ動画を撮影。
- 昔の写真や動画をまとめたスライドショーを作る。
手作りのプレゼントアイデア
① 孫からの手作りプレゼント
- 似顔絵や手紙を書く。
- 折り紙や手作りカードを贈る。
- フォトアルバムを作る。
② 名前入りのギフトを贈る
- 湯呑み、マグカップ、エプロンなどに名前やメッセージを入れる。
- 孫の手形・足形アートも記念に残る。
③ 手作りのお菓子や料理
- クッキーやケーキを焼いてラッピングする。
- ジャムやドレッシングなどの手作り食品を贈る。
敬老の日ならではの特別な過ごし方
① 昔話を聞く時間を作る
- おじいちゃん・おばあちゃんの若い頃の話を聞く。
- 写真やアルバムを見ながら昔話に花を咲かせる。
② 一緒に趣味を楽しむ
- 家庭菜園や盆栽を一緒に手入れする。
- 将棋や囲碁を一緒に楽しむ。
- 手芸や編み物を教えてもらう。
③ 健康を意識したイベントをする
- 一緒にストレッチや軽い運動をする。
- ウォーキングやハイキングを楽しむ。
施設にいる祖父母へのお祝い方法
介護施設や老人ホームで過ごしている祖父母へ敬老の日のお祝いをする場合は、施設のルールを尊重しつつ、祖父母が喜ぶ方法を選ぶことが大切です。
直接訪問できる場合と、できない場合のそれぞれの方法を紹介します。
施設に訪問して直接お祝いする
① 施設のルールを確認する
- 面会可能かどうかを事前に施設に確認する(コロナ対策やインフルエンザ流行期などで制限がある場合も)。
- 面会時間や持ち込み可能なものを確認する。
② 一緒に食事を楽しむ
- 施設内の食堂で一緒に食事をする(可能な場合)。
- 外出許可があれば、近くのレストランやカフェで食事をする。
- お寿司や和菓子など、祖父母の好きな食べ物を差し入れする(施設の許可が必要)。
③ 思い出に残る時間を作る
- 孫と一緒に訪問し、手作りのプレゼントを渡す。
- 昔の写真を見ながら、思い出話をする。
- 施設の庭や周辺を散歩して気分転換。
直接訪問できない場合のお祝い方法
① 手紙やメッセージカードを送る
- 直筆の手紙や孫が書いたメッセージカードを送ると、特別感が増す。
- 絵や折り紙を添えると、より温かみのある贈り物になる。
② ビデオ通話や電話でお祝いする
- LINEやZoomなどを使ってビデオ通話をする(施設のWi-Fi環境を事前に確認)。
- 電話で祖父母の体調を気遣いながらお祝いの言葉を伝える。
③ サプライズ動画を作って送る
- 家族全員のメッセージ動画を撮影し、DVDやUSBで送る。
- 孫が歌を歌ったり、似顔絵を描いた様子を記録して贈る。
施設でも受け取れるプレゼントを贈る
① 食べ物(施設の許可を確認)
- 個包装された和菓子・洋菓子(どら焼き、ゼリー、羊羹など)。
- 健康に配慮した食品(低糖質のお菓子、お茶、フルーツ)。
- 消化が良く、噛みやすいもの(柔らかい煮物、スープなど)。
② お花や観葉植物
- 花束ではなく、管理が楽な鉢植えやプリザーブドフラワーを選ぶ。
- 施設での管理が難しい場合は、小さめのアレンジメントフラワーがおすすめ。
③ 使いやすい実用品
- 名前入りのマグカップ(割れにくい素材のもの)。
- ひざ掛けやブランケット(冷え対策)。
- スリッパやクッション(快適な時間を過ごせるアイテム)。
④ 施設での生活を楽しくするもの
- 塗り絵やパズル(頭の体操になる)。
- 好きな音楽を入れたCDやラジオ。
- デジタルフォトフレーム(家族の写真をたくさん入れて贈る)。
施設でのイベントに参加する
施設での敬老の日イベントに参加する方法と楽しみ方
敬老の日には、多くの介護施設や老人ホームで特別なイベントが開催されます。
家族が参加できるイベントも多いため、祖父母と一緒に楽しい時間を過ごす良い機会です。
施設でのイベントに参加する際のポイントや、楽しみ方を紹介します。
施設の敬老の日イベントの種類
施設によって内容は異なりますが、一般的に以下のようなイベントが開催されます。
① 記念式典・お祝い会
- 敬老の日の表彰式(長寿のお祝い、100歳の方への表彰など)。
- 施設長やスタッフからの感謝の言葉。
- 入居者同士や家族との交流の場として設けられることも。
② 家族参加型のレクリエーション
- ビンゴ大会、クイズ大会、福引きなど、家族と一緒に楽しめるイベント。
- カラオケ大会(祖父母が好きな曲を歌う)。
- 手作りの作品展示会(入居者が作った絵や手芸作品を披露)。
③ 伝統文化体験
- 書道や折り紙など、日本の伝統文化を体験するワークショップ。
- 和菓子作りやお茶会を開催する施設も。
④ 孫世代との交流イベント
- 幼稚園・小学生の子どもたちによる歌やダンスの発表。
- 孫と一緒に折り紙や塗り絵を楽しむ。
⑤ ゲームや運動レクリエーション
- 玉入れ、輪投げ、ボウリングなどの軽い運動。
- 簡単なストレッチや健康体操。
⑥ 敬老の日スペシャル食事会
- お祝い膳や特別メニューが用意されることも。
- 家族が一緒に参加できる場合もあるので、施設に確認。
施設のイベントに参加するための準備
① 事前に施設のイベント内容を確認
- 家族の参加が可能かどうかを確認。
- 持ち物や服装の指定があるかチェック。
② 祖父母が楽しめるようにサポート
- 体調に配慮し、無理のない範囲で参加できるようにする。
- 必要なら、車椅子のサポートや座りやすい席を確保する。
③ 手土産やプレゼントを準備
- 施設のルールに従ったギフトを用意する(食べ物や花など)。
- 孫からの手作りプレゼント(似顔絵、手紙など)を持参すると喜ばれる。
施設イベントをもっと楽しむ方法
① 一緒に写真や動画を撮る
- イベントの思い出を写真に残す。
- 祖父母と一緒に撮影し、後でアルバムやフォトフレームにしてプレゼントする。
② 他の入居者とも交流する
- 祖父母の友人や同じ施設の方々とも会話を楽しむ。
- 交流することで、施設内での生活がより充実することにつながる。
③ 孫と一緒に参加する
- 孫が来ると祖父母は特に喜ぶので、できるだけ家族全員で参加。
- 子どもと一緒に折り紙や塗り絵などのアクティビティに参加。
施設での敬老の日イベントに参加できない場合
① ビデオメッセージを送る
- 家族全員で「おめでとう」のメッセージを録画し、施設に送る。
- 孫の歌やダンスなどを撮影して送るのもおすすめ。
② 施設のスタッフにメッセージを託す
- 祖父母への手紙やプレゼントを施設のスタッフに預けて渡してもらう。
敬老の日における施設スタッフへの配慮が大切な理由
敬老の日は、施設で暮らす祖父母にとって特別な日ですが、日々お世話をしてくれているスタッフへの配慮も重要です。
介護スタッフは、入居者のケアやイベントの準備で忙しくなるため、家族が協力し、負担を増やさないことが大切です。
敬老の日イベントの進行を妨げない
① イベントのスケジュールを把握
- 敬老の日には施設独自のイベント(式典、レクリエーション、食事会など)があるため、事前に確認する。
- イベント中の面会が制限される場合もあるので、スケジュールを調整。
② 面会時のマナーを守る
- 面会時間を長く取りすぎないようにする(他の入居者もいるため)。
- 施設内で大きな声を出したり、騒ぎすぎたりしない。
- スタッフの業務の邪魔にならないよう、適切な距離感を保つ。
施設と良好な関係を築く
① 施設の運営方針を尊重する
- 施設ごとに、食事の提供方法や介護サービスの方針が異なるため、過度な要望をしない。
- 特別なリクエストをする場合は、スタッフと相談しながら進める。
② 普段から良好な関係を築く
- 敬老の日だけでなく、普段から感謝を伝えることが大切。
- 「先日、祖母が施設で楽しく過ごしている様子を見て安心しました」と、何気ない一言を伝えるだけでも良い関係につながる。
施設のルールやスケジュールを尊重する
① 事前に施設のルールを確認
- 施設ごとに訪問やプレゼントの持ち込みに関する規則が異なるため、事前に問い合わせる。
- 面会時間や人数制限、飲食物の持ち込み可否などを確認する。
② スタッフの負担を増やさない
- 訪問時間を守る(忙しい時間帯を避ける)。
- プレゼントが管理しやすいものか考える(大きすぎるもの、手入れが必要なものは控える)。
- 施設側が提供する食事がある場合は、持ち込む食べ物の内容に注意。
③ 敬老の日イベントのスケジュールを確認
- 当日、施設で行われるイベントがあれば、その流れを確認してから訪問する。
- イベントの進行を妨げないよう、適切なタイミングでお祝いをする。
施設スタッフへの感謝の伝え方
① 直接「ありがとう」の言葉を伝える
- スタッフに日頃の感謝を伝えることで、より良い関係が築ける。
- 「いつも祖父母がお世話になっています。ありがとうございます。」と、シンプルな言葉でも気持ちは伝わる。
② メッセージカードや手紙を渡す
- 祖父母と一緒にスタッフへお礼のメッセージを書くと、より気持ちが伝わる。
- 孫からのイラストや手書きのメッセージを添えると喜ばれる。
スタッフへの差し入れやプレゼントについて
① 差し入れをする場合は事前確認
- 食べ物の差し入れは施設のルールに従う(手作りのものはNGの場合も)。
- 個包装のお菓子やドリンクが無難(人数が多い場合でも分けやすい)。
② ちょっとしたギフトを贈る
- 感謝の気持ちを伝えるため、控えめなギフトを選ぶ。
- ボールペンやメモ帳、ハンドクリームなどの日常で使えるアイテムが喜ばれる。
- スタッフの負担にならないよう、高価なものは避ける。
施設との良好な関係を築く
① スタッフの意見を尊重する
- 施設のルールや方針に従い、スタッフの負担にならないよう配慮する。
- 「祖父母が施設でどのように過ごしているか」など、日々のケアについて話を聞くと、よりよい関係が築ける。
② 無理なお願いをしない
- 敬老の日に「特別に○○をしてほしい」とお願いするのではなく、できる範囲でお祝いができる方法を相談する。
施設の敬老の日イベントの種類
施設によって内容は異なりますが、一般的に以下のようなイベントが開催されます。
① 記念式典・お祝い会
- 敬老の日の表彰式(長寿のお祝い、100歳の方への表彰など)。
- 施設長やスタッフからの感謝の言葉。
- 入居者同士や家族との交流の場として設けられることも。
② 家族参加型のレクリエーション
- ビンゴ大会、クイズ大会、福引きなど、家族と一緒に楽しめるイベント。
- カラオケ大会(祖父母が好きな曲を歌う)。
- 手作りの作品展示会(入居者が作った絵や手芸作品を披露)。
③ 伝統文化体験
- 書道や折り紙など、日本の伝統文化を体験するワークショップ。
- 和菓子作りやお茶会を開催する施設も。
④ 孫世代との交流イベント
- 幼稚園・小学生の子どもたちによる歌やダンスの発表。
- 孫と一緒に折り紙や塗り絵を楽しむ。
⑤ ゲームや運動レクリエーション
- 玉入れ、輪投げ、ボウリングなどの軽い運動。
- 簡単なストレッチや健康体操。
⑥ 敬老の日スペシャル食事会
- お祝い膳や特別メニューが用意されることも。
- 家族が一緒に参加できる場合もあるので、施設に確認。
施設のイベントに参加するための準備
① 事前に施設のイベント内容を確認
- 家族の参加が可能かどうかを確認。
- 持ち物や服装の指定があるかチェック。
② 祖父母が楽しめるようにサポート
- 体調に配慮し、無理のない範囲で参加できるようにする。
- 必要なら、車椅子のサポートや座りやすい席を確保する。
③ 手土産やプレゼントを準備
- 施設のルールに従ったギフトを用意する(食べ物や花など)。
- 孫からの手作りプレゼント(似顔絵、手紙など)を持参すると喜ばれる。
施設イベントをもっと楽しむ方法
① 一緒に写真や動画を撮る
- イベントの思い出を写真に残す。
- 祖父母と一緒に撮影し、後でアルバムやフォトフレームにしてプレゼントする。
② 他の入居者とも交流する
- 祖父母の友人や同じ施設の方々とも会話を楽しむ。
- 交流することで、施設内での生活がより充実することにつながる。
③ 孫と一緒に参加する
- 孫が来ると祖父母は特に喜ぶので、できるだけ家族全員で参加。
- 子どもと一緒に折り紙や塗り絵などのアクティビティに参加。
施設での敬老の日イベントに参加できない場合
① ビデオメッセージを送る
- 家族全員で「おめでとう」のメッセージを録画し、施設に送る。
- 孫の歌やダンスなどを撮影して送るのもおすすめ。
② 施設のスタッフにメッセージを託す
- 祖父母への手紙やプレゼントを施設のスタッフに預けて渡してもらう。
施設のスタッフへの配慮も大切
- イベント運営の負担を考え、スタッフの方への感謝の気持ちを忘れずに。
- 当日のルールやスケジュールを守る。
- 施設によっては家族の参加に人数制限がある場合もあるので、事前に確認する。
まとめ
施設での敬老の日イベントは、祖父母にとって特別な思い出になる機会です。
家族が参加できる場合は積極的に関わり、一緒に過ごす時間を大切にしましょう。
参加できない場合でも、ビデオメッセージや手紙を通じて気持ちを伝えることができます。
施設のルールを尊重しながら、祖父母が楽しめるよう工夫することが大切です。
- 祖父母がお世話になっている施設のスタッフにお礼のメッセージを伝える。
- 差し入れや小さなギフトを贈るのもよいが、施設の規則に従うことが大切。
敬老の日と老人の日の違い
「敬老の日」と「老人の日」はどちらも高齢者を敬う日ですが、それぞれの目的や制定の背景、日付が異なります。
この2つの違いをわかりやすく解説します。
敬老の日とは?
① 敬老の日の概要
- 高齢者を敬い、長寿を祝うための国民の祝日。
- 日付:毎年9月の第3月曜日(2003年から)。
- 制定年:1966年(昭和41年)。
- 法律上の分類:国民の祝日。
② 敬老の日の目的
- 長年社会に貢献してきた高齢者への感謝と敬意を表す日。
- 家族が集まり、おじいちゃん・おばあちゃんをお祝いする日として定着。
③ 敬老の日の由来
- 1947年(昭和22年)、兵庫県多可町(旧野間谷村)で「としよりの日」が始まる。
- 1966年(昭和41年)、国が9月15日を「敬老の日」として国民の祝日に制定。
- 2003年(平成15年)からハッピーマンデー制度により、9月の第3月曜日に変更。
老人の日とは?
① 老人の日の概要
- 高齢者の福祉について理解を深め、社会全体で高齢者を支えることを目的とした日。
- 日付:毎年9月15日。
- 制定年:1963年(昭和38年)。
- 法律上の分類:老人福祉法に基づく記念日。
② 老人の日の目的
- 高齢者の生活の向上や福祉について考える機会をつくる。
- 単なるお祝いの日ではなく、高齢者がより良い社会生活を送るための啓発活動を行う。
- 9月15日から21日までを「老人週間」とし、全国で福祉イベントや啓発活動を実施。
③ 老人の日の由来
- 1963年(昭和38年)、老人福祉法が制定され、「老人の日」が正式に定められる。
- 1966年(昭和41年)に9月15日が「敬老の日」として国民の祝日になる。
- 2003年(平成15年)に敬老の日が9月第3月曜日に変更されたため、元々の9月15日を「老人の日」として復活。
敬老の日と老人の日の違い(比較表)
| 項目 | 敬老の日 | 老人の日 |
|---|---|---|
| 目的 | 高齢者の長寿を祝い、敬意を表す | 高齢者福祉について考え、社会全体で支える意識を持つ |
| 日付 | 9月の第3月曜日 | 9月15日 |
| 制定年 | 1966年(昭和41年) | 1963年(昭和38年) |
| 法律上の分類 | 国民の祝日 | 老人福祉法による記念日 |
| 関連期間 | なし | 9月15日〜21日を「老人週間」とする |
| 主な活動 | 家族のお祝い、敬老会、贈り物など | 高齢者福祉の啓発イベント、ボランティア活動 |
敬老の日と老人の日、どちらを優先する?
- 一般的に、家族や企業のイベントは「敬老の日」に行われることが多い。
- 福祉施設や自治体では「老人の日」や「老人週間」に関連イベントを開催。
- 敬老の日は「家族でお祝いする日」、老人の日は「社会全体で高齢者福祉について考える日」と理解するとわかりやすい。
まとめ
「敬老の日」は高齢者を祝う日であり、家族や社会が長寿を喜び、感謝を伝える日。
一方、「老人の日」は高齢者の福祉や社会の支援について考える日であり、国が高齢者の生活向上を促すために設けた日です。
それぞれの意味を理解し、適切な形でお祝いし、高齢者への敬意を示すことが大切です。
まとめ
敬老の日は、大切な家族に感謝の気持ちを伝える特別な日です。
何歳から祝うべきかに明確な決まりはなく、相手の気持ちを尊重しながら祝うことが大切。
プレゼントを選ぶ際は年齢や好みに合ったものを贈り、メッセージカードを添えるとより心がこもります。
また、食事会や旅行、ビデオ通話など相手に合わせたお祝い方法を考えるのもポイントです。
2025年の敬老の日は9月15日(月・祝)。
この記事を参考に、素敵な敬老の日を過ごしてくださいね!


























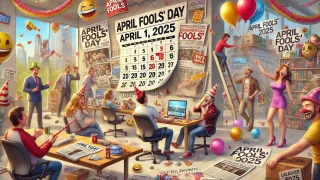




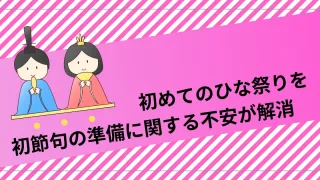




コメント