「お中元って、何を贈ればいいの?」
「贈る時期を間違えたら失礼になる?」
「そもそも、お中元とお歳暮って何が違うの?」
このような悩みを抱えている方は、実はとても多いんです。
特に、初めてお中元を贈ろうと思っている方にとっては、わからないことだらけで不安になりますよね。
この記事では、そんなあなたのために「お中元って何?」という基本から「いつ・誰に・何を贈るのが正解なのか」までやさしく、そして丁寧に解説していきます。
私自身も、最初は“のしの書き方”ひとつでつまずいた経験があります。
でも、正しい知識を知ることで自信を持って贈れるようになりました。
この記事を読めば、
✔ お中元の意味や由来
✔ 贈る相手・時期・マナー
✔ 失敗しないギフト選びのコツ
✔ 贈った後のお礼やお返しのマナー
こういったポイントがしっかり理解でき、相手に喜んでもらえるお中元を選ぶことができるようになります。
大切なのは、高いものを贈ることではなく、心を込めること。
この夏、お世話になったあの人に、感謝の気持ちを届けませんか?
お中元とは?意味と由来をやさしく解説
お中元の起源は中国と仏教の文化
「中元」は中国の古い行事が始まり
- 中国では、旧暦7月15日を「中元」と呼び、三人の神さまのひとり「地官大帝」の誕生日とされていました。
- 地官大帝は“人の罪をゆるす神さま”として知られており、この日に罪をゆるしてもらう行事が行われていました。
贈り物を配る風習が生まれた
- 中元の日には、近所の人や親しい人に贈り物を配るという習慣が生まれます。
- この「人と人とのつながりを大切にする文化」が、お中元のルーツといわれています。
日本の「お盆」と結びついた
- 日本には、同じ時期に「お盆(盂蘭盆)」というご先祖さまを供養する行事がありました。
- 中元とお盆は意味が似ていたため、2つの行事が混ざり合っていきました。
お供え物から贈り物へ変化
- 初めは、ご先祖さまへのお供え物を親族や近所と分け合う「共食(ともじき)」という文化でした。
- これが時代とともに、“お世話になった人へ贈り物をする”今のお中元スタイルへと変わっていきました。
「お中元」という言葉に込められた意味
「お中元」は時期の名前でもある
- 「お中元」はもともと、旧暦の7月15日を表す言葉です。
- 現在では、7月初旬~8月中旬ごろを指す「夏の季節の区切り」として使われます。
「贈り物そのもの」もお中元
- 同時に、「夏に贈る感謝の品物そのもの」のことも「お中元」と呼ばれます。
- たとえば「お中元を贈る」と言えば、贈り物を届ける行為全体を指します。
感謝と気づかいの気持ちがこめられている
- お中元には、「上半期お世話になりました」という感謝の気持ちと、
- 「これからもよろしくお願いします」「暑さに気をつけてくださいね」といった気づかいが込められています。
日本らしい思いやりの文化
- 大切なのは値段ではなく、気持ちをこめて贈ることなのです。
- 「お中元」は、相手の健康や暮らしを気にかける日本独自の“やさしさの表現”です。
お中元とお歳暮の違いとは?
贈る時期の違い
お中元は「夏」に贈る
- お中元は主に7月初旬〜8月中旬に贈ります。
- 関東では7月初旬〜7月15日、関西では7月中旬〜8月15日までが一般的。
- 地域によって違うので、贈る相手の住んでいる場所に合わせましょう。
お歳暮は「年末」に贈る
- お歳暮は12月初旬〜12月25日ごろが目安。
- 年末のあいさつとして、「1年お世話になりました」の気持ちをこめて贈ります。
時期の違いが意味の違いに
- お中元は上半期の感謝、お歳暮は1年間の感謝を表す贈り物です。
- この違いを知っておくと、気持ちがより丁寧に伝わります。
込められた想いと意味の違い
お中元は「今まで+これから」の感謝
- 夏に贈るお中元は、「上半期ありがとう」と「暑い中お体に気をつけてね」の2つの想いが込められています。
お歳暮は「1年の締めくくり」
- お歳暮は年末のごあいさつ。
- 「今年1年、本当にありがとうございました」という気持ちを表す習慣です。
お歳暮のほうがフォーマル
- 一般的には、お歳暮の方が重要度が高いとされています。
- 予算もお中元よりやや高めになる傾向があります。
相場やマナーの違い
お中元は3,000〜5,000円が基本
- 相手との関係にもよりますが、お中元は3,000円〜5,000円の品物が多いです。
- 特別にお世話になった人には、5,000〜10,000円のギフトも。
お歳暮は少し高めに
- お歳暮は「1年の感謝」なので、お中元より2〜3割高い金額のギフトが選ばれることもあります。
- とはいえ、高すぎると相手に気を使わせるので注意が必要です。
両方贈るなら“お歳暮重視”が基本
- 毎年続けることがマナーなので、無理のない範囲で贈ることが大切です。
- もしどちらかだけ贈る場合は、お歳暮の方を優先しましょう。
お中元を贈る時期はいつ?地域別の違いも解説
関東と関西で異なる贈るタイミング
お中元の基本の時期
お中元は、夏のごあいさつとして、7月〜8月に贈るのが一般的です。
ただし、地域によって贈る時期が少し違うので注意が必要です。
関東地方は7月初旬〜7月15日
関東では、7月1日〜7月15日が「お中元」として贈るベストな時期です。
東京・千葉・神奈川・埼玉など、関東圏に住んでいる方には、
なるべく7月中旬までに届くように贈りましょう。
関西地方は7月中旬〜8月15日
関西では、7月15日〜8月15日までが「お中元」の期間とされています。
大阪・京都・兵庫・奈良などでは、
関東よりも少し遅めの時期がマナーとなっています。
地域差に合わせるのがマナー
贈る自分の地域ではなく、相手が住んでいる地域の風習に合わせることが大切です。
たとえば、あなたが関東に住んでいて、相手が大阪にいるなら、
関西のマナーに合わせて7月下旬〜8月中旬に贈るのが正解です。
時期を逃したら?暑中見舞いや残暑見舞いで対応
お中元の時期を過ぎてしまったら
「忙しくて、お中元のタイミングを逃してしまった…」
そんなときでも大丈夫です。
贈る時期を過ぎてしまった場合は、
“暑中見舞い”や“残暑見舞い”として贈るのが一般的な対応です。
暑中見舞いは梅雨明け〜立秋まで
お中元の時期を過ぎた 8月初旬~立秋(例年8月7日ごろ)まで に贈る場合は、
「暑中見舞い」として贈ります。
この時期はまだ暑さが本格的な頃なので、
冷たいスイーツや飲み物など、夏らしい品がぴったりです。
残暑見舞いは立秋以降に
立秋を過ぎた 8月8日以降〜8月下旬ごろ に贈る場合は、
「残暑見舞い」として贈りましょう。
秋の気配が少しずつ感じられる時期なので、
季節感のある落ち着いた品もおすすめです。
表書き(のし)の書き方にも注意
- お中元の場合:「御中元」
- 暑中見舞い:「暑中御見舞」
- 残暑見舞い:「残暑御見舞」
それぞれの時期に合った表書きで贈ることが、相手に対する心づかいになります。
お中元は誰に贈る?関係別おすすめリスト
親・親族へのお中元
感謝の気持ちを伝えるよい機会
両親や親戚にお中元を贈るのは、とても自然で温かい習慣です。
ふだん面と向かって言えない「ありがとう」を、贈り物にのせて伝えましょう。
離れて暮らす家族にもぴったり
とくに離れて暮らす家族や祖父母には、季節の変わり目に体調を気づかう意味もこめて贈ると喜ばれます。
気をつけるポイントは「気軽さ」
家族へのお中元は、かしこまる必要はありません。
高すぎず、実用的で「食べてうれしい」「使って助かる」ものが喜ばれます。
上司・取引先への注意点
社会人のマナーとして重視される場面
会社の上司や取引先にお中元を贈る場合、ビジネスマナーとしての配慮がとても大切です。
会社のルールを必ず確認
最近では、「会社としてお中元やお歳暮のやりとりを禁止している」ケースも増えています。
まずは自分の会社のルールを確認しましょう。
相手の立場を考えた選び方を
贈る相手が上司や目上の人である場合、高価すぎない・かしこまりすぎないバランスが重要です。
ビール、ジュース、高級お茶、カタログギフトなどが人気です。
困ったときは「部署宛て」もアリ
個人宛てが難しい場合は、「○○部のみなさまへ」といった形で部署宛てにすることで、失礼にならずスマートです。
先生・習い事の相手には?
習い事の先生へのお礼として
ピアノ、茶道、習字などの先生に対して、日頃の感謝をこめてお中元を贈る方も多いです。
適度な距離感が大切
先生に対しては、あまりに高価なものや個人的すぎる贈り物は控え、
季節のごあいさつとして受け入れられるものを選びましょう。
形式や礼儀を重んじる先生も多い
のしの書き方や包装、渡し方など、丁寧さを意識することで、相手の心に響くお中元になります。
贈ってはいけない人(公務員など)
公務員や政治家は原則NG
国家公務員・地方公務員・学校の先生(公立)・政治家などは、
職務の性質から贈り物の受け取りが禁止されている場合があります。
これは、贈り物が「見返りを期待するもの」とみなされるおそれがあるからです。
贈る前に確認を
迷ったら、相手の立場を考えたり、さりげなく確認するのが安全です。
無理に贈ってしまうと、かえって相手に迷惑がかかることもあります。
代わりに手紙や暑中見舞いもおすすめ
気持ちを伝えたい場合は、手紙やハガキで感謝を伝えるのも素敵な方法です。
贈り物にこだわらず、想いを伝えることが大切です。
お中元の相場とマナーを確認しよう
相場は3,000〜5,000円が基本
一般的なお中元の予算
お中元の平均的な相場は、3,000円〜5,000円程度が主流です。
この価格帯であれば、気をつかわせずに感謝の気持ちを届けることができます。
相手との関係で変わる金額
相手との関係性によって、予算に少し差が出るのは自然なことです。
- 親族や近しい人:3,000円前後
- 上司・恩師など目上の人:5,000円前後
- 特別にお世話になった方:5,000〜10,000円程度
※ただし、高すぎる贈り物は相手に気をつかわせる場合があるので、ほどよい金額が大切です。
毎年続けられるかを考えて選ぶ
お中元は一度贈ったら、翌年以降も継続することが基本です。
無理のない範囲で、継続できる金額を選ぶようにしましょう。
「のし」や「水引」の正しい書き方・選び方
のしとは?
「のし」とは、贈り物に付ける飾り紙のことです。
「これは心を込めた正式な贈り物です」という印になります。
水引は「紅白の蝶結び」を選ぶ
お中元には、紅白で結び直せる「蝶結び」の水引を使います。
これは「何度あっても良いご縁」という意味があるからです。
※「結び切り」は慶弔や一度きりの場面で使うものなので注意!
表書きの書き方
のし紙の中央上部には、時期に合わせた表書きを記入します。
- 7月初旬〜15日(関東):「御中元」
- 7月15日以降〜立秋まで:「暑中御見舞」
- 立秋以降:「残暑御見舞」
下段には、贈る人の名前をフルネームで記入します。
宅配と手渡しで異なるのしの種類
「外のし」と「内のし」の違い
- 外のし:包装紙の外側にのしをつける
- 内のし:包装紙の内側にのしをつける
それぞれには、目的に応じた使い分けがあります。
手渡しするなら「外のし」
相手に直接手渡しする場合は、外のしが基本です。
贈り物の目的が一目でわかるため、丁寧な印象を与えます。
宅配で送るなら「内のし」
宅配や郵送で贈る場合は、内のしがおすすめです。
配送中にのしが傷つかないよう、包装紙の内側にのしを入れます。
相手がのしに詳しい場合は、より丁寧に
相手が目上の方や、礼儀に敏感な方であれば、
のしや水引の細かな部分までしっかり整えておくと、信頼感もアップします。
贈って喜ばれる!お中元人気ギフト5選
アイス・ゼリーなど涼しげなスイーツ
夏らしい「冷たい贈り物」は定番
暑い夏にぴったりなのが、ひんやり系のスイーツ。
食べて涼しくなれる贈り物は、子どもから大人まで喜ばれます。
人気のスイーツ例
- フルーツゼリーセット
- 高級アイスクリーム
- 水ようかんや和菓子の詰め合わせ
見た目も涼しげで、冷蔵庫で保管できる点も好評です。
小分けになっていると分けやすい
職場や大家族など、複数人で食べる場面を想定して、小分けタイプのギフトがおすすめです。
高級フルーツ・うなぎなどのグルメ
「特別感」のある食材はやっぱり人気
普段はなかなか自分で買わないような、ちょっと高級な食材は贈り物として特別感があります。
人気のグルメ例
- 季節の高級フルーツ(桃・メロン・ぶどう など)
- 国産うなぎ・牛肉の詰め合わせ
- 高級ハムや海鮮セット
特にお中元の時期は「土用の丑の日」とも重なるので、うなぎギフトは非常に人気です。
賞味期限や保存方法にも配慮を
冷蔵・冷凍が必要なグルメは、事前に相手の受け取りやすいタイミングを確認してから送ると安心です。
家族で使えるカタログギフト・日用品
相手に選んでもらえる「カタログギフト」
最近では、お中元でもカタログギフトがとても人気です。
相手が好きなものを選べるので、好みがわからないときにも便利です。
実用的な日用品も喜ばれる
- 洗剤セット
- タオル・バスグッズ
- コーヒーやお茶の詰め合わせ
家族みんなで使える実用的なものは、気をつかわせず自然に受け取ってもらいやすいです。
「もらって困らない」を意識
「高級すぎるより、生活に役立つもの」の方が、結果的に喜ばれることも多いです。
相手に応じた選び方のポイント
相手の「家族構成」や「生活スタイル」を意識
- 小さなお子さんがいる家庭 → スイーツやジュースセット
- 一人暮らしの相手 → 日持ちするグルメや少量タイプ
- 高齢の方 → 消化にやさしい食品や飲み物
贈る相手に合わせて選ぶことで、“思いやり”が伝わる贈り物になります。
好みがわからない場合は「万人受け」狙いで
どうしても好みがわからないときは、カタログギフトやコーヒー・お茶などの定番品を選ぶと安心です。
予算とマナーのバランスも忘れずに
見栄えがしても、高すぎるギフトはNG。
相手との関係性・年齢・立場をふまえて、ちょうどよい価格帯に収めましょう。
お中元を受け取ったら?お礼のマナーも大切に
すぐに連絡!電話・メール・お礼状のマナー
お礼は「すぐに」が基本マナー
お中元を受け取ったら、できるだけ早くお礼を伝えるのがマナーです。
感謝の気持ちは、スピードが命。できれば当日中、遅くても翌日までには連絡しましょう。
電話やメールでもOK
昔は手紙が主流でしたが、今は電話やメールでも問題ありません。
相手との関係や年齢層に合わせて、丁寧な言葉で感謝を伝えましょう。
- 電話の場合:「○○をいただき、ありがとうございます。家族みんなで喜んでいます。」
- メールの場合:「素敵なお中元をありがとうございました。暑い日が続きますので、お体に気をつけてお過ごしください。」
フォーマルな場面では「お礼状」がおすすめ
取引先や目上の人からのお中元には、手書きのお礼状がより丁寧な印象を与えます。
形式にとらわれすぎず、自分の言葉で気持ちを綴ることが大切です。
お返しは基本不要だが、ケースによっては対応も
お中元は「お返しを前提としない贈り物」
本来、お中元は「見返りを求めない感謝の贈り物」です。
そのため、基本的にはお返しは不要とされています。
どうしても気になる場合は「お礼の品」を
とはいえ、「何か返した方がよいのでは…?」と感じる場合もありますよね。
そんなときは、軽めのギフトや手土産を別の機会に渡すのも良い方法です。
例:
- お盆帰省時にお土産を持っていく
- 残暑見舞いとして冷たい飲み物を送る
「対等なおつき合いにしたい」という気持ちが伝われば十分です。
連絡や感謝の気持ちが何より大切
お返し以上に大切なのは、相手への感謝の気持ちをしっかり伝えることです。
丁寧な言葉で「うれしかった」という気持ちを伝えることで、相手も安心し、今後も良い関係を築けます。
よくあるQ&A|お中元のギモンを一発解決!
喪中・忌中に贈っても大丈夫?
喪中と忌中の違いを理解しよう
- 喪中:親族が亡くなってから1年間、故人を偲ぶ期間
- 忌中:亡くなってから四十九日までの特に慎む時期
この2つでは対応が少し異なります。
喪中の相手には贈ってOK
お中元は「お祝い」ではなく「感謝の気持ち」なので、
喪中の相手に贈っても失礼にはなりません。
ただし、気を使わせたくない場合は、暑中見舞いや時期をずらす方法もあります。
忌中はタイミングを見て配慮を
四十九日を過ぎていない場合(忌中)は、相手が精神的に落ち着いていない可能性があります。
この時期は、贈るのを控えたり、時期をずらして「残暑見舞い」として贈るのが無難です。
表書きに「御中元」は避けることも
どうしても贈りたいときは、のし紙の「御中元」ではなく、
「暑中御見舞」「残暑御見舞」と書くことで、やわらかい印象になります。
突然やめたいときはどうする?
毎年贈るのがマナー。でも事情は人それぞれ
お中元は「毎年続けるのが基本的なマナー」とされていますが、
生活の変化や関係性の変化でやめたいと感じることもありますよね。
やめるなら「感謝の気持ちを伝えてから」
いきなりやめてしまうと、相手に不安や誤解を与えることがあります。
やめるときは、手紙やメッセージで「これまでのお礼」を伝えると丁寧です。
例:
「これまで心のこもったお付き合いをいただき、ありがとうございました。事情により今年からお中元を控えさせていただきますが、変わらぬ感謝の気持ちは変わりません。」
一度やめると、再開しにくいことも
関係が復活しても、お中元の再開は少し気まずくなることがあります。
できれば、無理のない範囲で続けるか、形を変えて感謝を伝える方法も検討してみましょう。
お中元とお歳暮、どちらかだけ贈ってもいい?
実は「どちらか一方」だけでもOK
お中元とお歳暮はセットで考えられがちですが、どちらか一方だけでも問題ありません。
無理に両方続ける必要はないのです。
優先するなら「お歳暮」がベター
どちらか一つにする場合は、お歳暮を優先するのが一般的です。
年末のあいさつとして、「1年の感謝」を込めたお歳暮の方がフォーマルな印象になります。
お中元だけの場合は「継続性」に配慮
お中元のみを贈る場合も、数年続ける意識を持っておくと好印象です。
途中でやめる場合は、お礼や事情を伝える心づかいを忘れずに。
まとめ
お中元は、ただの贈り物ではありません。
日ごろお世話になっている人に「ありがとう」の気持ちを形にして伝える、大切な日本の習慣です。
「いつ贈ればいいの?」「何を選べばいいの?」と、最初は不安になることもあります。
でも、基本のマナーさえ知っていれば大丈夫。
贈る相手のことを思って、丁寧に選んだギフトには、ちゃんと気持ちが伝わります。
今回の記事でご紹介したように、贈る時期には地域差があり、相手との関係によって予算も変わります。
のしや水引の選び方なども少し注意が必要ですが、ひとつひとつ知っておくだけで、失礼のないお中元を贈ることができます。
そして何より大事なのは、感謝の気持ちです。
値段の高いギフトでなくても、「あなたに感謝しています」という心がこもっていれば、それだけで十分なんです。
今年のお中元は、そんな気持ちを大切にして、相手の笑顔を思い浮かべながら選んでみてくださいね。
読んでいただき、ありがとうございました。






























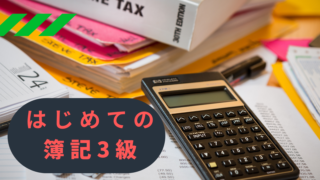






コメント