選挙のたびに耳にする「1票の格差」。
その是正を目的として導入されたのが「アダムズ方式」です。
2024年の衆院選から本格適用されたこの制度は、衆議院の小選挙区の定数を都道府県別に配分する際に使われています。
しかし、
「アダムズ方式って具体的にどう計算されるの?」
「ドント方式と何が違うの?」
「本当に平等なの?」
といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
本記事では、「アダムズ方式とは何か」から、その仕組み、導入の背景、計算例、メリット・デメリット、そして他方式との違いまでをわかりやすく解説。
選挙制度を理解するうえで知っておくべき重要なトピックを丁寧にお届けします。
読者のあなたが、「なんとなく分かる」から「しっかり説明できる」にステップアップできるようサポートいたします。
アダムズ方式とは?簡単な定義と背景
アダムズ方式は、人口に比例した議席配分を目指す方法で、日本では衆議院の小選挙区における都道府県別の議席数を決定するために採用されています。特に「1票の格差」を是正する目的で導入されました。
アダムズ方式の定義
人口に応じた議席数の配分を行う方式で、基準人口(X)を用いて各都道府県に議席を割り当てます。
基本の考え方
- 各都道府県の人口 ÷ 基準値X で得られた値を 切り上げ。
- 得られた数値が、その都道府県に割り当てられる議席数になります。
アメリカが起源
- アメリカ第6代大統領 ジョン・クインシー・アダムズ によって提唱。
- 合理的で公平な議席配分方式として知られています。
アダムズ方式はなぜ導入されたのか?
選挙の「1票の格差」是正が最大の目的
日本においてアダムズ方式が導入された背景には、「人口による議席配分の不平等」という長年の課題がありました。
制度変更の理由と流れを段階的に解説します。
背景にある「1票の格差」問題
人口が少ない県と多い県で、1票の価値に差があることが指摘されてきました。
格差の実例
- 都市部:100万人に1議席 → 1票の価値が軽い
- 過疎地:30万人に1議席 → 1票の価値が重い
このような不均衡が「違憲状態」と判断されたこともあります。
最高裁の違憲判決が導入の引き金に
最高裁大法廷は2011年3月、2009年総選挙の1票の格差(最大2.304倍)について違憲状態と判断した
また、2025年、最高裁第二小法廷は2024年選挙の最大格差2.06倍を『合憲』と判断」などを具体的に引用する。
- 2011年最高裁判決:「1票の格差」が2倍を超える状態を違憲状態と判断(※「違憲状態」とは、直ちに無効とはされないが憲法違反の可能性がある状態とされる判決の用語)
- 2025年:報道によれば、最高裁第二小法廷は2024年衆院選の最大格差(2.06倍)について合憲と判断
(出典:朝日新聞 2025年9月25日)
判決の要点
- 「投票価値の平等」が憲法違反に近い状態
- 抜本的な制度改革の必要性を明言
改革に向けた政治的な合意形成
国会では「1票の格差」是正に向け、複数の方式が議論されました。
有力候補だった3つの方式
| 方式名 | 特徴 | 採用の有無 |
|---|---|---|
| ドント方式 | 切り捨て処理 | 不採用 |
| サンラグ方式 | 四捨五入 | 不採用 |
| アダムズ方式 | 小数点切り上げ | 採用(2016年法改正) ✅ |
アダムズ方式が選ばれたのは、「地方に一定の配慮ができる」「客観的でわかりやすい計算方式」であることが評価されたためです。
2024年からの本格適用
2020年の国勢調査をもとに、2024年衆院選で初めて適用されました。
適用後の影響
「10増10減」による大規模区割り再編が実現
東京都:議席+5
地方:10県で議席-1
背景となる判決と制度見直し
アダムズ方式導入の根幹には「違憲状態」とされた選挙制度の問題があります。
ここでは、最高裁判決とそれに続く制度改正の流れを時系列で分かりやすく説明します。
2011年:最高裁「違憲状態」判決
長年使用されていた「1人別枠方式」が、憲法の「法の下の平等」に反するとされました。
「2011年3月23日、最高裁大法廷は2009年衆院選の選挙区間格差が最大2.304倍だった点について『違憲状態』と判断」と正確に記述する。
判決の概要と影響
- 対象選挙:2009年の衆院選
- 最大格差:2.30倍
- 最高裁の判断:「投票価値の著しい不平等は違憲状態」
この判決が、選挙制度全体の見直しを迫る強いメッセージとなりました。
2013年:一票の格差是正への第一次対応
政府と国会は、応急的な格差是正として「0増5減」(定数0増・5県で定数減)を実施しました。
問題の根本解決には至らず
- 仮対応であり、制度の根本は変わらない
- 再び「違憲状態」判決が出る可能性を懸念
2015年:有識者による検討会設置
「衆議院選挙制度に関する調査会」が設けられ、配分方式の検討が本格化します。
検討された主な方式
- ドント方式:切り捨て → 都市部に有利
- サンラグ方式:四捨五入 → 中立的
- アダムズ方式:切り上げ → 地方に配慮 ✅
アダムズ方式は、小数点以下を切り上げることで最小1議席の保障が可能であり、地方とのバランスに優れていると評価されました。
2016年:公職選挙法の改正で正式決定
政府はアダムズ方式の採用を正式に決定し、関連法案を成立させました。
法改正のポイント
- 定数配分の基準方式を「アダムズ方式」に明記
- 初適用は「次回の国勢調査(2020年)に基づく選挙」から
この決定により、将来的な制度の透明性と公平性が確保される方向へと進みました。
従来方式との違い
アダムズ方式は、従来の議席配分方法とは「小数点以下の扱い」と「格差是正の姿勢」に明確な違いがあります。
従来の「1人別枠方式」とは?
かつて使われていた「1人別枠方式」は、地方に有利な配分方法でした。
特徴と課題:
- 各都道府県にまず1議席を自動的に割り当て
- 残りの議席を人口に応じて配分
- → 人口の少ない県でも必ず1議席確保できるが、都市部との格差が拡大
結果:
- 最大で2倍以上の一票の格差
- 最高裁からも「違憲状態」と判断された
アダムズ方式との比較
| 比較項目 | 1人別枠方式 | アダムズ方式 |
|---|---|---|
| 小数処理 | 特になし(枠で固定) | 小数点以下をすべて切り上げ |
| 地方配慮 | 非常に強い(1議席保障) | 配慮しつつも人口比に忠実 |
| 格差是正効果 | 弱い | 高い(1票の重みを均等化) |
| 最高裁評価 | 違憲状態とされた | 制度そのものは合理的と評価(2025年) |
公平性重視へのシフト
アダムズ方式は、「1票の価値は平等であるべき」という理念に沿った制度です。
選挙制度の「民主的正当性」を高めるための重要な一歩といえます
都市部と地方のバランスを取りつつ、数値的に公平な配分を実現
※補足:ドント方式はスペインやポーランドなどで採用されており、都市部に有利な傾向があります。サンラグ方式はドイツ・ノルウェーなどで使われ、中立的な配分が特徴です。
背景と目的
アダムズ方式の導入は、「1票の格差是正」を目的とした選挙制度改革の一環です。最高裁の判断や国民の公平意識の高まりが背景にあります。
1票の格差とは何か?
「同じ1票でも、選挙区によって“重み”が異なる」状態を指します。
例:
- 東京都の有権者数:100万人に1議席
- 過疎県の有権者数:30万人に1議席
→ 東京都民の1票は「1/3の価値」
このような差が「1票の格差」です。
最高裁が示した違憲状態(2011年)
2011年、最高裁は当時の選挙制度について「違憲状態」とする判断を下しました。
指摘のポイント:
- 最大格差が「2倍以上」
- 現行制度では国民の平等な選挙権が損なわれている
- 国に早急な是正を求める判決
この判断が制度見直しの起点となりました。
導入の目的は「選挙の公平化」
アダムズ方式は、次のような目的のもと導入されました。
- 人口に比例した配分で公平性を確保
- 都市部と地方のバランスを見直す
- 国際的な民主主義基準にも近づける
政治への信頼回復を図る
公正な制度を導入することは、政治への信頼向上にもつながる重要な施策です。
- 「納得できる制度」は投票率にも影響
- 政治不信を軽減し、民主主義を健全化
※2025年時点でも「1票の格差」に関する訴訟は続いており、今後の制度見直しや新たな訴訟動向にも注目が集まっています。最高裁判所の判断は、選挙制度改革の方向性に大きな影響を与え続けています。
(参考:毎日新聞)
従来方式との違い
アダムズ方式は、「小数点以下の切り上げ」を特徴とする配分方法です。
他の方式と比べて、どのような違いがあるのでしょうか?
3つの主な方式の違いとは?
日本の議席配分で用いられてきた、または検討されてきた方式を比較します。
| 方式名 | 主な使用例 | 小数処理 | 特徴・傾向 |
|---|---|---|---|
| アダムズ方式 | 小選挙区の都道府県配分 | 切り上げ | 地方にやや有利、公平性を重視 |
| ドント方式 | 比例代表の政党配分 | 切り捨て | 都市部や大政党に有利 |
| サンラグ方式 | 一部欧州で使用 | 四捨五入 | 中立的だが採用実績は少なめ |
アダムズ方式のポイント
- 小数点を切り上げるため、人口の少ない県でも1議席が確保される
- 地方の「声」を確保する意味合いが強い
- 配分結果に政治的恣意性が入りにくく、計算根拠が明確
ドント方式との大きな違い
ドント方式(比例代表に使用)は、得票数を割っていく方式で、小数点以下は切り捨てられます。
- 都市部や支持者の多い政党が有利になりやすい
- 地方の意見が反映されにくくなる懸念も
なぜアダムズ方式を選んだのか?
- ドント方式では「1票の格差」が是正されにくい
- サンラグ方式は中立的だが、導入事例が少ない
- アダムズ方式は格差是正に最も効果的と判断された
なぜ導入されたのか?背景と課題
- 1人別枠方式の格差問題
- 1票の格差是正が最高裁からも求められた【2011年違憲状態判決】
アダムズ方式の計算方法とは?
アダムズ方式は、「人口÷基準値X」で議席を配分し、小数点以下を切り上げることで、各都道府県に公平な議席数を割り当てる方法です。
計算の基本ルール
まずは、アダムズ方式の計算方法の全体像をつかみましょう。
基本の計算式
- 議席配分 = 都道府県人口 ÷ 基準値X
- 結果の小数点以下は切り上げ
- 議席数の合計が国会の総議席数(例:289)と一致するよう、Xを調整
ステップごとの流れ
- 各都道府県の人口を準備
- 仮の基準値X(例:18万人)を設定
- 人口÷Xの計算 → 小数点以下はすべて切り上げ
- すべての都道府県の議席を合計し、総定数(例:289)と一致するようXを微調整
なぜ切り上げなのか?
- 人口の少ない県でも最低1議席が保証される
- 地方に配慮された設計で、地域代表の確保にもつながる
実際の計算例
具体的な数字で理解を深めましょう。
仮定条件
- 総人口:900万人
- 総議席数:50議席
- A県:500万人、B県:300万人、C県:100万人
基準値X=18.6万で計算した結果
| 県名 | 人口 | 人口÷18.6万 | 切り上げ後 | 議席数 |
|---|---|---|---|---|
| A県 | 500万 | 26.88 | 27 | 27議席 |
| B県 | 300万 | 16.13 | 17 | 17議席 |
| C県 | 100万 | 5.38 | 6 | 6議席 |
✅ 合計:27 + 17 + 6 = 50議席(ピッタリ)
なぜXを調整する必要があるのか?
Xは単なる定数ではなく、議席数との整合性を取るための調整値です。
Xの調整パターン
| 基準値X | 合計議席数 | 備考 |
|---|---|---|
| 18.0万 | 51 | 多すぎ |
| 19.0万 | 49 | 少ない |
| 18.6万 | 50 | ✅ピッタリ |
- 小さいX:切り上げ回数が多くなり、議席が過剰
- 大きいX:割り算の結果が小さくなり、議席が不足
他方式との違い(小数点処理)
アダムズ方式の大きな特徴は「小数点以下を切り上げ」にする点です。
簡易比較表
| 方式名 | 小数処理 | 地域への配慮 |
|---|---|---|
| アダムズ方式 | 切り上げ | 地方に配慮あり |
| ドント方式 | 切り捨て | 都市部にやや有利 |
| サンラグ方式 | 四捨五入 | 中立的な議席配分 |
サンラグ方式:バランス型
アダムズ方式:地方を守る設計
ドント方式:都市部で有利になりがち
アダムズ方式のメリットとは?
アダムズ方式の最大の魅力は、「選挙の公平性」を高める点にあります。
人口に応じて議席を分配することで、1票の格差を是正する効果が期待されています。
1票の格差の是正につながる
アダムズ方式は、人口に応じた配分を基本としているため、選挙区ごとの「1票の重み」を可能な限り均等化できます。
格差是正ができる仕組み
- 人口に比例して議席を配分
- 都市部と地方の不均衡を調整
- 割り算によって客観的な数値で決定
結果として得られる効果
- 投票の価値に公平感が生まれる
- 選挙制度への信頼性が向上する
- 憲法が求める「法の下の平等」に近づく
すべての都道府県に議席が確保される
切り上げ処理によって、人口が少ない地域でも最低1議席を持つことができます。
地方への配慮がある仕組み
- 小数点以下を切り上げることで、人口の少ない県でも議席が付与される
- 「0議席」という極端なケースが起こらない
政治参加の機会を保証
- 地方住民の政治的孤立を防ぐ
- 全地域に国政への代表者を配置できる
- 「地域切り捨て感」の解消にもつながる
数値に基づく客観性と透明性
アダムズ方式は「計算」に基づいた配分方法のため、恣意性の排除にもつながります。
公平な根拠を提供
- 感覚や政治判断ではなく、人口と数値が根拠
- 誰でも計算すれば同じ結果になる
結果の納得感を高める
- 政治的な対立を回避しやすい
- 有権者も議席数の妥当性を理解しやすい
アダムズ方式のデメリットとは?
公平性を追求するアダムズ方式ですが、制度上の弱点や懸念も存在します。
ここではその代表的なデメリットを整理して解説します。
都市部への議席集中と地方の議席減
人口比に基づく配分ゆえに、都市部の議席が増える一方で、地方の議席は減少する傾向があります。
地方の声が届きにくくなる可能性
- 人口が少ない地域は、議席が減少する傾向にある
- 地方選出の議員が減ると、地方の課題が国会で扱われにくくなる懸念
- 「政治の都市集中化」が進む恐れ
例:2024年衆院選での再編影響
- 東京都 → 5議席増
- 広島県や愛媛県など → 1議席減
- 結果として「都市優遇・地方不利」の構図が拡大
格差の“完全な”是正には限界がある
アダムズ方式でも、導入タイミングや人口変動の影響で格差は再発する可能性があります。
制度のラグ(遅れ)が生むズレ
- 国勢調査(10年に1回) → 区割り → 実選挙まで数年のタイムラグ
- その間に都市部人口が増えれば、再び格差が広がる
最高裁の見解(2025年 高裁判決)
- 最大格差2.06倍でも「アダムズ方式自体が原因とは言えない」
- とはいえ、「制度の合理性を失わせるほどではない」と慎重な評価
制度としての複雑さと理解の難しさ
数式やXの調整など、専門的な計算が必要なため、有権者の理解が難しいという課題もあります。
国民にとっての分かりづらさ
- 「なぜ自分の県の議席が減ったのか?」が理解しにくい
- 配分の根拠が数式ベースのため、直感的に納得しにくい
政治不信につながる可能性も
- 配分結果が「地方切り捨て」と受け取られると、不満や不信感を招く恐れ
- 説明責任や広報の重要性が増す
アダムズ方式はいつから?導入時期と選挙の変化
アダムズ方式の導入は「1票の格差」是正のための大きな一歩でした。
導入決定から実際の選挙適用までの流れと、その影響について解説します。
制度としての導入決定は2016年
実際に法律でアダムズ方式が明記されたのは、2016年の選挙制度改革においてです。
公職選挙法の改正内容
- 2016年:衆院選挙制度改革関連法が成立
- これにより、次回以降の国勢調査に基づいてアダムズ方式を適用することが決定
- 導入対象は、小選挙区の都道府県への定数配分
実際に適用されたのは2024年衆院選から
制度は2020年の国勢調査結果を基に準備され、2024年に初めて選挙へ反映されました。
導入までのスケジュール
- 2020年10月:国勢調査実施
- 2021年11月:国勢調査の確定値が公表
- 2022年:区割り改定法案が成立(10増10減)
- 2024年10月27日:アダムズ方式が適用された初の衆院選実施
選挙区数の大きな再編「10増10減」
アダムズ方式の導入により、全国の選挙区数が再編されました。
議席増加の都道府県(都市部中心)
- 東京都:+5議席
- 神奈川県:+2議席
- 埼玉県・千葉県・愛知県:各+1議席
議席減少の都道府県(地方中心)
- 宮城県、福島県、新潟県、滋賀県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、長崎県 → 各-1議席
比例代表の見直しも同時に実施
アダムズ方式は小選挙区だけでなく、比例ブロックにも影響を与えています。
比例代表の「3増3減」
- 増加:東京ブロック +2、南関東ブロック +1
- 減少:東北・北陸信越・中国 各-1
全体としての議席配分の見直し
- 地域ごとの人口比に応じて、比例区でも調整が進んだ
- より公平な議席配分を意識した結果
アダムズ方式はいつから?導入時期と選挙の変化
アダムズ方式の導入は「1票の格差」是正のための大きな一歩でした。
導入決定から実際の選挙適用までの流れと、その影響について解説します。
制度としての導入決定は2016年
実際に法律でアダムズ方式が明記されたのは、2016年の選挙制度改革においてです。
公職選挙法の改正内容
- 2016年:衆院選挙制度改革関連法が成立
- これにより、次回以降の国勢調査に基づいてアダムズ方式を適用することが決定
- 導入対象は、小選挙区の都道府県への定数配分
実際に適用されたのは2024年衆院選から
制度は2020年の国勢調査結果を基に準備され、2024年に初めて選挙へ反映されました。
導入までのスケジュール
- 2020年10月:国勢調査実施
- 2021年11月:国勢調査の確定値が公表
- 2022年:区割り改定法案が成立(10増10減)
- 2024年10月27日:アダムズ方式が適用された初の衆院選実施
選挙区数の大きな再編「10増10減」
アダムズ方式の導入により、全国の選挙区数が再編されました。
議席増加の都道府県(都市部中心)
- 東京都:+5議席
- 神奈川県:+2議席
- 埼玉県・千葉県・愛知県:各+1議席
議席減少の都道府県(地方中心)
- 宮城県、福島県、新潟県、滋賀県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、長崎県 → 各-1議席
比例代表の見直しも同時に実施
アダムズ方式は小選挙区だけでなく、比例ブロックにも影響を与えています。
比例代表の「3増3減」
- 増加:東京ブロック +2、南関東ブロック +1
- 減少:東北・北陸信越・中国 各-1
全体としての議席配分の見直し
より公平な議席配分を意識した結果
地域ごとの人口比に応じて、比例区でも調整が進んだ
| 比較項目 | アダムズ方式 | ドント方式 |
|---|---|---|
| 用途 | 小選挙区の都道府県割当 | 比例代表での政党への議席配分 |
| 計算方法 | 人口 ÷ 定数X(小数点切り上げ) | 得票 ÷ (1, 2, 3,…)で多い順に配分 |
| 導入時期 | 2016年決定 → 2024年適用 | 1996年の比例代表から適用 |
2016年:選挙制度改革関連法が成立し、アダムズ方式の導入が制度として決定。
2024年:この方式が初めて実際に適用された衆議院選挙が実施された。
よくある質問(FAQ)
Q1. アダムズ方式とドント方式の違いは?
アダムズ方式は「小選挙区の都道府県定数配分」、ドント方式は「比例代表の政党配分」に用いられます。
計算方法も異なり、アダムズ方式は人口を定数Xで割り小数点切り上げ、ドント方式は得票を割って順に割り振る方法です。
Q2. なぜ2024年から適用されたの?
制度は2016年に導入決定されましたが、最新の国勢調査(2020年)結果に基づいて実施する必要があったため、2024年の衆議院選挙からの適用となりました。
Q3. 地方の議席が減るのはなぜ?
アダムズ方式は人口に比例して議席を配分するため、人口の少ない地方では議席が減る傾向にあります。
逆に、人口の多い都市部は議席が増えるため、結果として「都市優遇」になるケースもあります。
まとめ
アダムズ方式は、議席配分の公平性を確保するために導入された新しい制度です。
特定の定数Xで人口を割り、小数点以下を切り上げることで、人口の多い都市部と少ない地方での投票価値の格差を是正しようという目的があります。
2024年の衆議院選挙ではじめて適用され、「10増10減」という大きな区割り変更が実施されました。
東京都では5議席増加し、逆に地方では議席が減少するなど、まさに人口比に基づいた再編が行われたのです。
ただし、人口の少ない地方が政治的に不利になる可能性や、導入のタイムラグによる一時的な格差再発など、課題も残っています。
アダムズ方式は、「投票価値の平等」を追求する上で画期的な制度でありながらも、地域間の公平性や政治的影響力のバランスという新たな議論を呼び起こしています。
これからの選挙制度を考える上で、知っておきたい重要な制度。
それが「アダムズ方式」なのです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
衆議院小選挙区の区割りの改定等について
参考出典:
- 総務省|衆議院小選挙区の区割りの改定等について(公式リンク)
- 読売新聞(2024年10月28日):「アダムズ方式適用、都市部で議席増」
- 最高裁判所判例データベース(2025年):選挙無効訴訟に関する最新判決






























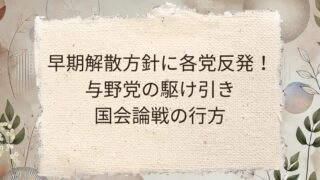




コメント