車を持っていると、税金のことがいつも気になりますよね。
「2025年に自動車税が変わるって聞いたけど、何がどう変わるの?」
「今乗っている車の税金は高くなるの?」
「買い替えたほうがいいのか悩んでいる…」
そんな不安を感じている方は少なくありません。
税金のことって、文字を見るだけで難しく感じてしまいますよね。
でも安心してください。この記事では、これからどう変わるのか?
今、何に気をつければいいのか?
わかりやすく、かんたんに説明していきます。
私は自動車税の改正に関する情報をいち早くキャッチし、実際の政策文書や専門家の意見を元に、情報を整理してきました。
この記事を読むことで、2025年の税制改正の内容やスケジュール、そして車ユーザーとしてどんな行動を取れば良いかが、しっかりわかります。
「損したくない」
「今のうちにできることが知りたい」
そんな方にこそ読んでほしい内容です。
そもそも自動車税とは?
自動車税とはどんな税金?
- 自動車税は、車を所有している人に毎年かかる税金です。
- 税金の種類としては、地方税(都道府県税)に分類されます。
- 車を使っていなくても、持っているだけで課税されます。
自動車税の使い道
- 主に道路整備や維持管理の財源として使われます。
- 最近では環境対策や脱炭素政策の一環としても注目されています。
- 税金によって、環境にやさしい車への買い替えを促す目的もあります。
課税の基準は?
- 普通車の場合、排気量の大きさに応じて税額が決まります。
例:1000cc以下 → 25,000円、2000cc超 → 45,000円(※旧基準の場合) - 軽自動車は一律で、年間10,800円程度(地域によって多少異なる)
- 課税対象は、毎年4月1日時点で車を所有している人です。
支払いのタイミングと方法
- 通常は毎年5月頃に納付書が届きます。
- 支払い方法は以下の通りです:
- コンビニ払い
- 銀行・郵便局
- クレジットカード払い
- スマホ決済アプリ(PayPay・LINE Payなど)
なぜ知っておくべき?
2025年の税制改正により、今後この仕組み自体が大きく変わる可能性があるため、今の制度を知っておくことが重要です。
自動車税は車を持つ限り、毎年かかる固定費です。
だからこそ、車の維持費を考える上でとても大切な要素になります。
なぜ税制改正されるの?
カーボンニュートラルの実現が急務
- 日本は2050年までにカーボンニュートラル(脱炭素)を目指すと宣言しています。
- そのため、ガソリン車の使用を減らし、EVやハイブリッド車の普及を進める必要があります。
- 今の税制は、環境にやさしい車に十分なメリットを与えていないという課題があります。
現行制度が古くなってきた
- 現在の自動車税制度は、1990年代から大きくは変わっていません。
- 排気量による課税は、ガソリン車が主流だった時代の考え方です。
- 今のように、EVやPHEV(プラグインハイブリッド車)が登場している現代では、制度が合わなくなってきています。
EVやハイブリッド車に課税の不公平感
- EVやハイブリッド車は燃費が良く、環境性能も高いですが、一部では「重さ(車両重量)」があるため、重量税が高くなることがあります。
- それに対して、古いガソリン車でも排気量が小さいと税金が安いというケースもあり、環境に配慮している人ほど負担が大きいという矛盾が生じています。
若者や地方の負担感が大きい
- 若い世代や地方の人にとっては、車は生活必需品。
- ですが、税金の負担が大きいため、車を持つこと自体が「贅沢」と見られることもあります。
- 生活を支える移動手段としての車に対する課税は、もう少し見直す必要があるという声が増えています。
国の収入構造の見直しも背景に
- 自動車関係の税金は、取得時・保有時・燃料購入時など、複数のタイミングで課税されています。
- 「わかりづらい」「多すぎる」「二重課税では?」といった批判も多く、よりシンプルでわかりやすい制度が求められているのです。
2025年以降の改正ポイント
取得時の税金が変わる
- 車を購入するときにかかる「環境性能割」という税金が廃止される方向で検討されています。
- これは、従来の「自動車取得税」の代わりとして導入された制度ですが、制度が複雑で分かりづらい、時代に合っていないという指摘が多くあります。
- 廃止されることで、購入時の税負担がシンプルになる可能性があります。
保有時の課税が見直される
- 現在、自動車税は「排気量」に応じて決まっていますが、今後は車の重さ=重量に応じた課税方法が検討されています。
- EV(電気自動車)は排気量がゼロでも車重は重いため、税金ゼロという不公平を是正する狙いがあります。
- これにより、より公平な課税が実現される可能性があります。
環境性能による差別化が強化される
- 今後は環境に優しい車に対する優遇措置がさらに強化される予定です。
- 例えば、EV・ハイブリッド・PHEVなどの車は、一定の条件を満たせば税額が軽減される方向です。
- 一方で、古いガソリン車や排ガス性能の低い車には増税(重課)の可能性もあります。
長期的には「走行距離課税」も検討?
- 将来的には、「どれだけ走ったか」に応じて課税する方法も検討されています。
- 燃費の良いEVはガソリン税を払わないため、国の税収が減る問題が出てきており、走行距離に応じて公平に税金を集める仕組みの必要性が議論されています。
- ただし、この制度は技術的・法的な課題が多く、すぐには導入されない見込みです。
軽自動車の扱いも再検討の可能性
- 現在は軽自動車が税制面で大きな優遇を受けていますが、今後の見直しで、普通車との税額差が縮まる可能性も出てきています。
- これは、税の公平性の観点や、軽自動車の使用環境が都市部でも増えていることなどが背景にあります。
今乗ってる車は影響を受ける?
13年超の車は「重課」が継続、または強化される可能性
- 現在、車を13年以上乗り続けると、自動車税が高くなる「重課制度」があります。
- これは「環境性能が古い車に対しては多めに課税する」という仕組みです。
- 改正後も、この重課制度は継続、またはさらに厳しくなる可能性があります。
- 特に、ガソリン車やディーゼル車で環境性能が低い車は要注意です。
ハイブリッド車・EVは税負担が軽くなる方向
- 環境にやさしい車に乗っている方は、今後の制度で優遇される可能性が高いです。
- 特に、EVやハイブリッド車、PHEV(プラグインハイブリッド)は、保有税・取得税の面で減税が強化される方向です。
- ただし、EVは重くなる傾向があるため、重量ベースの課税制度になると一部負担が出る可能性もあります。
軽自動車にも変化の兆しあり
- 現在は軽自動車の自動車税は一律で安く、普通車よりも優遇されています。
- しかし、「公平性の観点」から見直しの声もあり、軽自動車の税金が今後少しずつ上がっていく可能性もあります。
- 現時点では大きな改正はありませんが、将来的な影響は視野に入れておきましょう。
車種・年式によって影響の大きさが変わる
- 自動車税の影響は、乗っている車の種類・年式・燃費・排出ガス性能などで変わります。
- 同じ車でも、新車登録から何年経っているかによって課税額が違ってきます。
- つまり、「今の車が古いかどうか」や「環境にやさしいかどうか」で、今後の負担が大きく変わるということです。
実際の税額はどうなる?簡単シミュレーションのすすめ
- 国や自治体のサイトでは、新制度を想定した試算ツールなどが今後公開される可能性があります。
- また、ディーラーやメーカーでも、新制度に合わせたアドバイスをしてくれるケースが出てきます。
- 「あと数年はこの車に乗るつもり」という人は、制度がどう変わるかを早めにチェックして、損をしない選択をするのがおすすめです。
今後のスケジュールと注目点
2024年:制度の方向性が明らかに
- 2024年には、政府・与党の「税制改正大綱」で自動車税の見直し案が明示されました。
- これにより、「環境性能割の廃止」や「重量課税の導入」などの基本方針が固まりつつあります。
- 自治体や業界団体からも意見が出ており、今は制度設計の最終調整段階です。
2025年:税制改正のスタート年
- 2025年度からは、新しい税制度が段階的にスタートする可能性が高いです。
- 特に、環境性能割の廃止が注目されており、取得時の税負担が変わる初年度になると見られています。
- 他にも、自動車保有税(毎年の税金)への変更・統一の動きが本格化する可能性も。
2026年以降:新制度が本格適用?
- 重量ベースの課税や、環境性能に応じた細かな税額調整などは、段階的な導入になると予想されます。
- 一気にすべてが変わるわけではなく、経過措置や既存車への影響を最小限にする対応がとられるでしょう。
- そのため、2025年から数年かけて、制度が完全に切り替わる流れになると見込まれています。
注目すべき動き①:政府の発表と法改正
- 今後のカギを握るのは、政府の最終決定と法改正の内容です。
- 国会での審議を経て正式に法律として決まるため、最新のニュースや官報情報をチェックすることが大切です。
注目すべき動き②:自動車メーカーやディーラーの対応
- 各メーカーや販売店では、新制度を見越したプロモーションや値引きキャンペーンが出てくる可能性があります。
- 特にEVやハイブリッド車の購入を考えている方は、減税対象になるかどうかをよく確認することが大事です。
注目すべき動き③:自治体の動きと補助制度
- 一部の自治体では、EV購入に対する補助金や、独自の税軽減措置が実施されることがあります。
- 地域によって内容が異なるため、お住まいの自治体のホームページや広報誌もチェックしておくと安心です。
ユーザーにできる対策
車の買い替えタイミングを見極めよう
- 2025年から税制が大きく変わるため、「いつ買い替えるか」が節税のポイントになります。
- 特に、13年以上経過している車をお持ちの方は、早めの買い替えで重課を避けられる可能性があります。
- 一方で、2025年度以降に買う方が、取得税が軽くなる(環境性能割の廃止)というメリットもあるため、
「今すぐ買う」「2025年を待つ」どちらが得かを比較して判断することが重要です。
エコカーやEVへの買い替えを検討する
- 改正後は、環境性能の高い車への優遇措置がさらに強化される見込みです。
- EV(電気自動車)やハイブリッド車、PHEV(プラグインハイブリッド車)などは、自動車税・重量税の軽減、補助金の対象になる可能性が高くなっています。
- 長期的に見ても維持費が安くなる傾向にあるため、買い替えを考えているなら選択肢に入れておきましょう。
地方自治体の補助金や減免制度を活用しよう
- 自治体によっては、EV購入への補助金や独自の税負担軽減制度を設けているところもあります。
- 特に地方では、カーシェア補助・軽自動車減税・住宅用充電設備補助なども併せて利用可能な場合があります。
- お住まいの市区町村のホームページや広報誌で、使える制度があるか確認しておきましょう。
税額シミュレーションをしてみる
- メーカーサイトや一部自治体では、「新制度に基づく自動車税の見込み額」を算出できるツールが登場しています。
- 今乗っている車と、乗り換え候補の車でどれくらいの税額差があるかを具体的に比較してみましょう。
- 数字で見ると、「いま動くべきかどうか」がハッキリわかります。
定期的に最新情報をチェックしよう
- 政府の方針や法改正の内容は、年度ごとの税制改正大綱や国会審議でアップデートされていきます。
- 古い情報のまま判断すると、損をしてしまう可能性もあるため、
国土交通省や総務省、新聞社など信頼できる情報源から最新情報を確認する習慣をつけましょう。
車を持たない選択肢も一つの方法
- 税金や維持費の負担が大きいと感じるなら、カーシェアやレンタカーの活用も選択肢の一つです。
- 特に都市部に住んでいる方は、必要なときだけ使う方がトータルで安くなるケースも増えています。
- 「持つから使う」時代から「必要なときだけ借りる」時代への移行も、今後ますます進んでいきそうです。
まとめ
ここまでお読みいただきありがとうございます。
2025年の自動車税改正は、まだ最終決定には至っていませんが、大まかな方向性は明確になってきました。
「取得時の税負担を軽くする」
「保有時の税金を公平にする」
この2つが大きな柱です。
もし今お乗りの車が13年を超えていたり、これから買い替えを考えていたりする場合は、今回の改正が大きく関係してくる可能性があります。
だからこそ、今のうちに情報を知っておくことがとても大切です。
車は生活の一部。だからこそ、税金のことも避けては通れません。
この記事が、あなたの行動を後押しするきっかけになれば嬉しいです。
今後も税制の議論は続きます。最新情報をキャッチして、あなたにとっていちばん得する選択をしていきましょう。
「知らなかった」ではすまされない時代です。
知っている人だけが、正しく動けます。
その第一歩を、今日この瞬間から踏み出しましょう。




































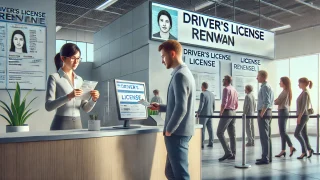



コメント