長時間労働の是正を目的に始まった「働き方改革」。
その象徴とも言えるのが、月45時間・年360時間の残業上限規制です。
しかし今、こうした労働時間の制限に見直しの動きが報じられています。
2025年10月、高市早苗首相が厚生労働省に対して「労働時間の規制緩和を検討するよう指示した」とする報道があり、社会全体に注目が集まっています。
「また過労死が増えるのではないか」と不安視する声がある一方で、「もっと働きたい」「収入を増やしたい」という労働者の希望を後押しする動きとして歓迎する声もあります。
さらに企業側からは、人手不足や生産性向上を目的に、柔軟な制度整備を望む声も出ています。
では実際に、首相が検討を指示したと報じられている規制緩和とはどのような内容なのでしょうか?
なぜこのタイミングなのでしょうか?
そして、私たちの働き方や暮らしにはどんな影響があるのでしょう?
本記事では、政府の動きの背景や意図、賛否それぞれの主張、そして今後の働き方改革の方向性について、「報道・検討段階」の情報をもとにわかりやすく解説します。変化の可能性がある労働環境の中で、自分らしく働くヒントを一緒に探していきましょう。
高市首相が労働時間の規制緩和を“検討”指示
首相が検討すべきとした規制緩和の方向性と、その背景を段階的に整理し、論点を明確にします。
労働時間規制緩和の“報道”とは
首相が厚労省に出したと報じられている指示の概要を把握しましょう。
- 報道によれば、高市首相が全閣僚に対して指示書を配布したとされていますが、**ページ数など詳細な公式資料の確認は現時点で取れていません。
- 指示先として厚労省へ「労働時間規制の見直しを検討するよう指示した」と報じられています(出典:TBS NEWS DIG 2025年10月22日)。
- キーワードとして「心身の健康維持」「従業者の選択」が取り上げられているという報道があります。
なぜ今“緩和検討”なのか
報じられている背景には、経済再生と人手不足という課題があります。
- 介護・建設・IT分野などで人手不足が深刻化しており、柔軟な働き方のニーズが高まっています。
- 高市政権は「働きたい人が働ける社会」を掲げ、経済重視の姿勢を示しています。
- 成長分野では、現行の残業上限規制が“柔軟な働き方”の導入を妨げているとの指摘があります。
検討されている具体策
規制緩和といっても無制限ではなく、慎重な設計が前提です。
高プロ制度の要件緩和
「年収1,075万円以上」という条件がネックに。
- 対象業務の拡大(例:営業・企画職など)
- 年収要件の引き下げ(→より多くの職種が対象に)
- 選択制を前提に「自由な働き方」を確保
オプトアウト制度の導入
「残業時間の上限撤廃」も個人の選択に委ねる案。
- 労働者の自己選択で、月45時間などの上限を外すことが可能に
- 代わりに企業は「健康管理義務の強化」が必須
- 勤務間インターバル11時間
- 産業医との定期面談
- 長時間労働者への特別措置
導入時の注意点と課題
制度の悪用を防ぎ、自由な選択が本当に守られるかが焦点。
選択の自由=建前にならない工夫
「会社に逆らえない空気」の中での「選択」の意味とは?
- 圧力に対抗するための仕組みづくりが重要
- 労働組合の関与
- 労働者保護機関による監視
- ハラスメント対策の徹底
現場の混乱を防ぐための段階導入
いきなりの全面施行はリスクが大きい。
- 「特区」に限定した試験導入の案も浮上
- 産業・職種別の段階的適用で影響を見極める
- 政府の説明不足が不信感を生む恐れあり
社会的リアクション
賛否が大きく分かれており、国民的議論の必要性が浮き彫りに。
賛成意見の例
「もっと働きたい人」にとっては朗報。
- 60代会社員:「老後資金のためにもっと稼ぎたい」
- パート・非正規労働者:「年収の壁」さえなければもっと働ける
反対意見の例
「過労死」や「精神疾患」への懸念が拭えない。
- 過労死遺族:「働いて、働いて、亡くなった娘のような悲劇は繰り返さないで」
- 労組や連合:「働き方改革への逆行であり看過できない」
高市首相と賛成派の意見とその理由
「働きたい人がもっと働ける社会」への期待感が広がる一方で、規制緩和を支持する声には明確な根拠があります。
「働きたいのに働けない」人々の現状
一部の人にとって、現行の労働時間規制は「機会の損失」になっているという声が上がっています。
収入増を求める労働者層
- パートや非正規雇用の多くは「年収の壁(103万円・130万円)」で勤務時間に制限
- 60代・定年後の労働者は「老後資金のためにもっと働きたい」
- 副業やフリーランスにも柔軟な働き方を望む声が多い
例:「今の制度では、収入を増やしたくても労働時間でブレーキがかかる」(50代・副業ワーカー)
企業側の視点:人手不足対策と生産性向上
企業経営者にとっても、規制緩和は“人材活用の幅”を広げる施策となります。
スタートアップ・成長分野での要望
- スピード重視の開発現場では、労働時間に縛られると成果が出しにくい
- 柔軟な働き方を導入することで、より多様な人材の採用が可能に
成果主義やジョブ型雇用との相性
- 時間ではなく「成果」で評価される働き方を導入しやすくなる
- ジョブ型雇用にシフトする企業が増える中、制度の柔軟性が必須に
規制緩和で生まれるメリット
働き方の選択肢が広がることで、社会全体にも好影響が期待されます。
ワークスタイルの多様化が可能に
- 週4日勤務で1日10時間など、個人のライフスタイルに合わせた勤務設計が可能
- 1時間単位での有給取得、短時間集中勤務などの制度も進展しやすい
高スキル人材の流動性向上
- 専門性の高い人材が「稼げる時間」を最大限活かす環境へ
- リモート・副業・プロジェクト単位での複数就労にも適応可能
制度的安全網とセットなら安心
規制緩和は、適切なルールと監視があってこそ機能します。
健康確保策の義務化
- インターバル制度(勤務間11時間以上)
- 産業医との定期面談
- ストレスチェックや過重労働面談の強化
労働者の自由意思を守る制度設計
- 選択は「本人の意思」であることの明文化
- 第三者機関による監視と相談窓口の整備
- 強制されない「自由な選択」であることが前提
高市首相への反対派の懸念と過去の教訓
「規制緩和」という言葉に潜むリスクへの警鐘。
過去の痛ましい出来事を踏まえた慎重論が根強く存在します。
過労死を招いた長時間労働の歴史
日本ではすでに「働きすぎ」が命を奪う深刻な問題となった過去があります。
髙橋まつりさんの悲劇と社会の覚醒
- 電通での長時間労働により、2015年に自死した高橋まつりさん(当時24歳)
- 遺族や社会の声を受けて2019年に「働き方改革関連法」が施行
- 「月45時間・年360時間」という上限設定は、まさに“過労死防止”が原点
髙橋さんの母:「あの子は『働いて、働いて』亡くなった。規制緩和だけはやめてほしい」
「自由な選択」が現場で通用しない現実
形式上の「同意」でも、実際には断れない空気があることが問題です。
同調圧力と上司の圧力
- 「残業したくない」と言える雰囲気がない職場が多い
- 上司の「期待」や「空気」を読み過ぎて無理をしてしまう
- 自由な選択とは程遠い実態
形だけの制度になる懸念
- 形式的に「本人が選んだ」ことにされてしまう
- 不利益扱いや評価への影響を恐れて拒否できない構造
緩和が悪用されるリスク
一部の企業が制度を“労働力の搾取”に使う可能性を危惧する声も強いです。
ブラック企業化の懸念
- 「残業代なしで働かせる仕組み」として悪用されるリスク
- 健康管理義務が名ばかりになる可能性
副業・兼業推進との矛盾
- 本業で残業時間が増えたら副業できる余地は消える
- 柔軟性の名の下に実質的な拘束が増す危険
規制強化こそ必要とする声
働く人の健康を守るには、むしろ「強化」が必要という立場もあります。
連合・芳野会長の発言
- 「緩和は長時間労働是正の取り組みに逆行する」
- 「過労死ラインぎりぎりの現状でも不十分」
社説や専門家の論調
- 「規制を緩める前に、生産性向上や業務効率化を優先すべき」
- 「『働きたい改革』は名ばかり。実態は“働かされる改革”では?」
制度設計に求められる要件とは?
労働時間規制の緩和が“真に自由な選択”となるためには、制度そのものに慎重かつ丁寧な設計が求められます。
自由な選択を守る制度的仕組み
選択の自由を保証するには、「会社と個人の交渉力の非対称性」を直視する必要があります。
労働者保護のためのルール整備
- 労働組合の関与を義務付ける
- 第三者チェック機関による「適正運用」の確認
- 意思確認書類に本人の明確な署名+撤回権の保証
ハラスメント・報復への防止策
- 「NO」と言っても不利益にならないことの明文化
- 上司・管理職に対するガイドラインの強化
- 労働局や監査機関への匿名通報制度の充実
健康と安全を担保する措置
緩和する代わりに「健康確保」の水準を引き上げることが最低条件です。
勤務間インターバルの厳格化
- 毎日の労働終了から次の勤務開始まで最低11時間空けるルール
- 実施状況を勤怠システムで自動記録・監査
産業医との定期面談義務化
- 長時間労働者には月1回以上の健康チェック
- メンタルヘルス対策も含む
残業時間の“緩和上限”を明確に
- 完全な無制限化ではなく、「本人の選択で月80時間まで」など段階設定
- 年間上限(例:720時間)維持や総合的負荷の管理を組み込む
リスキリング支援と公正な評価制度
「働けない人」と「働ける人」の格差を防ぐためには教育と制度が鍵になります。
スキル習得支援の強化
- 時間に制約のある層(育児・介護中など)への学習機会提供
- 短時間でも成果を出せるような能力開発支援(オンライン講座、助成金など)
評価制度のアップデート
- 時間ではなく「成果」で評価するジョブ型雇用への移行支援
- 評価軸の透明化と、公平性の担保
段階導入と検証プロセスの設計
一斉導入ではなく「試行と評価」を繰り返す慎重な運用が求められます。
特区でのパイロット導入
- まずは一部業界・地域・職種で限定実施
- 効果や課題を可視化し全国展開の是非を判断
第三者評価と定期見直しの制度化
- 制度導入後は年次レビュー必須
- 改善すべき点は柔軟に修正・撤廃を可能にする条項設計
これからの「働き方改革」の方向性
「労働時間を減らす」だけでなく、「自律的な働き方」へ。
次のステージの働き方改革には、視点の転換が求められています。
時間管理から“成果管理”へ
単に労働時間を制限するのではなく、「成果」に基づいた働き方が重要視されつつあります。
ジョブ型雇用の導入促進
- 成果で評価される雇用形態
- 労働者が業務時間・場所を自律的に選択しやすくなる
- 管理職層や専門職を中心に導入拡大中
時間に縛られない柔軟な評価制度
- 「在席時間」ではなく「アウトプット」で評価
- 業務ごとにKPI(成果指標)を設定
- 時短勤務者やフリーランスも公正に評価可能に
健康管理との両立がカギ
「働きすぎず、成果も出す」ためには、健康の維持が土台になります。
勤務インターバル制度の拡充
- 1日11時間以上の休息確保
- 勤怠記録と連動した強制管理が鍵
メンタルヘルス対策の標準化
- 長時間労働によるうつやバーンアウトの防止
- ストレスチェックの活用、産業医との連携強化
デジタル活用による効率化
「働きすぎ」は非効率の象ばんめのきじのしゅうせいかしょとしゅうせいをおねがいします徴。テクノロジーで時間当たりの生産性を高める発想へ。
DX(デジタル・トランスフォーメーション)の推進
- 定型業務の自動化(RPA、AI)
- 業務フローの可視化と最適化
- チームごとの労働時間データの活用でムリ・ムダの削減
リモートワーク・ハイブリッド勤務の拡大
- 通勤時間の削減=総労働時間の短縮
- 地方在住人材の活用など多様な働き方に対応可能
「働くこと」そのものの再定義
今後の働き方改革は、制度ではなく“価値観の変化”が中核になります。
ワーク・ライフ・バランスから「ライフ・デザイン」へ
- 自分の人生設計に基づいて働き方を選ぶ
- 「週4勤務+副業」や「短期集中+長期休暇」など多様な働き方が選べる社会へ
企業も「健康経営」へ転換を
- 働く人の健康が、企業成長の前提条件
- 「生産性=労働時間の長さ」という価値観の転換が不可欠
【まとめ】規制緩和の本質は「自由」か「強制」か
高市首相が示した「労働時間規制の緩和」方針は、表面的には「働きたい人が働ける社会」を目指す前向きな改革に見えるかもしれません。
しかし、その裏には日本社会の深層にある問題──同調圧力、労使間の交渉力の格差、過労死の歴史──といった課題が未解決のまま横たわっています。
制度上は「本人の選択」とされていますが、実際には上司や会社の意向に逆らいにくい現場も多く、「選択の自由」が形骸化する懸念も否定できません。
こうした中で規制を緩めれば、本来守るべき健康や命が犠牲になる危険性があります。
一方で、働く意欲を持ち、経済的理由や自己実現のために「もっと働きたい」と願う人々にとっては、柔軟な労働時間制度こそが可能性を広げる鍵になります。
大切なのは、「すべての人が自分らしく働ける仕組み」をいかにして設計できるかという点です。
働き方改革の本質は「誰もが安心して、納得して、自分の働き方を選べる社会」を実現することにあります。
規制強化か、緩和かという二元論ではなく、働く人一人ひとりの多様なニーズに寄り添った制度設計と運用が、今後ますます求められるでしょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
この記事が、あなたの働き方や生き方を考えるきっかけになれば幸いです。
これからも、わかりやすく丁寧に、社会を見つめる情報をお届けしてまいります。
📚 参考文献・出典一覧
- 厚生労働省「働き方改革実行計画」
- 朝日新聞「高橋まつりさんの過労死問題娘が亡くなって5年…電通過労自殺」(2016年12月)
- yahooニュース「【高プロ】弁護士らが街宣、過労死NHK記者の母親も涙の訴え」(2018年3月)
- 日本経済新聞「高市首相、労働時間規制緩和の検討を指示」(2025年10月報道)
- 日本経済新聞「高市早苗首相の18閣僚への指示書、全文明らかに」(2025年10月報道)
- 厚労省「過労死等防止対策白書」
※本記事の内容は2025年10月時点の情報に基づいて執筆されています。制度内容は今後の国会審議・政策動向によって変更される可能性があります。


























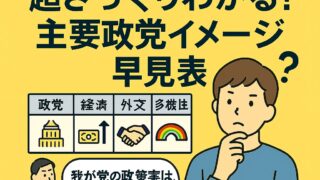








コメント