ETC2.0とは?基本をやさしく解説
ETC2.0は、従来のETC(Electronic Toll Collection)を進化させた次世代のシステムです。
料金の自動支払いに加え、道路と車両の双方向通信を活用して、より安全で快適なドライブをサポートします。
ETC2.0の基本機能
- 通行料金の自動支払い:従来のETCと同様に、料金所での停止なしに自動で料金を支払えます。
- 広範囲な交通情報の提供:全国の高速道路に設置されたITSスポットと連携し、渋滞や事故、災害情報などをリアルタイムで取得できます。
- 安全運転支援:急カーブや合流地点、事故多発エリアなどの注意情報を音声や画像で提供し、ドライバーの安全をサポートします。
- 一時退出と再進入の柔軟性:特定の道の駅などでの休憩後、一定時間内に再進入すれば、追加料金なしで利用できます。
ETC2.0と従来ETCの違い
| 機能 | 従来ETC | ETC2.0 |
|---|---|---|
| 通行料金の自動支払い | ✅ | ✅ |
| 交通情報の提供 | ❌ | ✅ |
| 安全運転支援 | ❌ | ✅ |
| 一時退出と再進入の柔軟性 | ❌ | ✅ |
| 渋滞回避ルートの提案 | ❌ | ✅ |
ETC2.0のメリット
- 快適なドライブ:リアルタイムの情報提供により、渋滞や事故を回避しやすくなります。
- 安全性の向上:危険箇所の事前通知で、事故リスクを軽減します。
- 経済的な利点:特定の区間では、ETC2.0利用者限定の割引が適用されます。
- 災害時の対応力:災害発生時には、通行可能なルートや避難情報を提供します。
導入時の注意点
- 専用車載器の必要性:ETC2.0を利用するには、対応する車載器の設置が必要です。
- 対応機器の確認:カーナビやスマートフォンとの連携が必要な場合があります。
- コスト:車載器の価格や取り付け費用が発生します。
ETC2.0は、より安全で快適なドライブを実現するための進化したシステムです。
導入を検討する際は、自身の利用スタイルや必要性を考慮し、メリットとデメリットを比較して判断しましょう。
ETC2.0のメリット|導入すると何が良くなる?
ETC2.0は、料金の割引だけでなく、安全運転支援や災害時の情報提供など、多岐にわたるサービスを提供しています。
導入を検討されている方は、これらのメリットを踏まえて判断されると良いでしょう。
通行料金の割引が受けられる
ETC2.0割引の対象区間と内容
1. 圏央道・新湘南バイパス(関東エリア)
- 対象区間:
- 圏央道:茅ヶ崎JCT~海老名JCT、海老名JCT~木更津JCT
- 新湘南バイパス:藤沢~茅ヶ崎JCT
- 割引内容:
- 高速自動車国道の普通区間の料金水準(普通車の場合、1kmあたり24.6円)に割引されます。
- 例えば、大井松田~相模原間(44.9km)では、普通車の料金が1,500円から1,390円に割引されます。
2. 東海環状自動車道(中部エリア)
- 対象区間:
- 東海環状自動車道全線
- 割引内容:
- 高速自動車国道の普通区間の料金水準に割引されます。
- 具体的な料金は、NEXCO中日本の公式サイトで確認できます。 Drive Plaza+2Sompo Direct+2GO!ETC ETC総合情報ポータルサイト+2
割引適用の条件と注意点
- ETC2.0車載器の搭載:
- ETC2.0に対応した車載器を搭載し、セットアップが完了している必要があります。
- ETC無線通信の利用:
- ETCが整備されている入口・出口インターチェンジを、ETC無線通信で通過する必要があります。
- 料金表示について:
- 料金所の表示やETC車載器の画面には、割引前の通常料金が表示されます。
- 割引後の料金は、後日、カード会社からの請求時に適用されます。
- 他の割引との併用:
- ETC2.0割引は、他のETC割引(例:平日朝夕割引、障がい者割引)と重複して適用されません。
- 複数の割引が適用される場合、最も割引額が大きいものが適用されます。
ETC2.0を導入することで、特定の区間での通行料金が割引され、経済的なメリットがあります。
ご自身の利用頻度や走行ルートに合わせて、導入を検討されてみてはいかがでしょうか。
渋滞情報をもとに迂回ルートを提案してくれる
ETC2.0は、高速道路に設置された「ITSスポット」という設備から、広範囲の道路情報をリアルタイムで受信します。
この情報には、前方の渋滞や事故、規制の情報などが含まれています。
たとえば、 「この先で事故が起きているよ」
「渋滞が発生しているよ」
といった情報を、ETC2.0対応のカーナビやスマホに送ってくれます。
すると、その情報をもとに、ナビが「こっちの道から行くと早いですよ」と、
別のスムーズなルートを教えてくれるんです。
特に長距離ドライブや、お盆・年末年始など混雑が予想される時期に重宝します。
最大で1,000km先の広域情報まで受け取れるのも、ETC2.0の魅力です。
ポイントまとめ
- 渋滞を事前に察知できる
- ルート変更の提案で時間短縮に
- ナビとの連携でドライブがより快適に
このように、ETC2.0があると“走りながら渋滞を避ける”ということができるようになります。
運転のストレスも減って、安全面にもつながるうれしい機能ですね
合流・急カーブなど危険箇所の通知で安全性がアップ.
高速道路には、思わぬ危険が潜んでいます。
たとえば「合流地点」や「急カーブ」、あるいは「事故が多い場所」などです。
ETC2.0を搭載した車では、こうした場所に近づくと、
ITSスポット(道路に設置された通信ポイント)から情報が送られます。
そして、対応したカーナビや車載器が、
「この先、合流があります」
「この先、急カーブです」
「事故多発地点です。ご注意ください」
といったメッセージを音声や画面で教えてくれるのです。
これにより、あらかじめ注意して運転することができ、
事故のリスクをぐっと下げることができます。
ポイントまとめ
- 合流・急カーブ・事故多発地点を事前にお知らせ
- 音声や画面で「危ないよ」と注意してくれる
- ドライバーの安全意識が自然と高まる
安全運転は何よりも大切です。
ETC2.0は、こうした危険箇所の情報をリアルタイムで教えてくれる頼もしい味方です。
ドライブ中の「うっかり」や「見落とし」を防ぐ、大事な機能なんですよ。
災害時の通行情報が得られる
地震や大雨、台風などの災害が起きたとき、「どこが通れるのか」「どのルートが安全なのか」って、とても気になりますよね。
ETC2.0が搭載されていると、ITSスポットという通信装置から、災害に関する情報をリアルタイムで受け取ることができます。
たとえば、
- 通行止めの区間
- 土砂崩れが発生した場所
- 代わりに通れる道路
- 被災地周辺の支援ルートや避難場所 など
こうした情報が、ETC2.0対応のカーナビや画面に表示され、ドライバーはそれを見ながら、安全なルートを選ぶことができるんです。
ポイントまとめ
- 災害発生時もリアルタイムで通行情報を入手
- 通れるルートや避難所の情報がわかる
- 道に迷わず、安全な行動がとりやすくなる
もしもの時に、自分や家族を守るためにも、ETC2.0のこうした防災サポート機能はとても心強い存在です。
「備えあれば憂いなし」ですね。
物流・運送業にも強い味方
運送業では、「時間どおりに荷物を届ける」ことがとても大事です。
でも、渋滞や通行止め、災害などで予定が狂ってしまうこともありますよね。
そんなときに役立つのがETC2.0です。
主なサポート内容
- 走行経路の管理ができる
どこをどう走ってきたのかという情報が記録されるので、
運行管理がしやすくなります。 - 到着予定時刻が読みやすくなる
リアルタイムの交通情報から、所要時間が予測できるため、
到着時刻を正確に見積もることができます。 - 渋滞回避で効率アップ
渋滞情報をもとにルート変更ができるので、
無駄な待機時間が減り、配送効率がアップします。 - 災害時のルート確保
被災地へ物資を届ける際にも、通行可能なルートがすぐにわかります。
企業にとってのメリット
- 配送の「見える化」が進む
- ドライバーの安全確保にも役立つ
- 燃料や時間のムダを減らせる
- 顧客への信頼にもつながる
ETC2.0は、単なる「高速料金の支払いシステム」ではありません。
運送業界にとっては、コスト削減・効率化・安全確保の三拍子そろった、頼れる相棒なんです。
特に車両台数の多い企業ほど、そのメリットは大きくなりますよ。
ETC2.0のデメリット|購入前に知っておこう
対応機器の価格が高い(2〜5万円+取付工賃)
ETC2.0を使うには、専用の車載器が必要です。
でもこの機器、じつはけっこうお高めなんです。
一般的な価格帯
- ■ 本体価格:2万円〜5万円
※メーカーや機能によって幅があります。 - ■ 取付工賃・セットアップ費用:5,000円〜1万円前後
※販売店や整備工場によって異なります。
たとえば、
パナソニックやパイオニアなどの人気モデル → 2.5万円前後
高性能なナビ連動型や音声案内つき → 3〜4万円以上
さらに、車への取り付け費用や、ETC2.0として登録(セットアップ)する費用も別途かかるため、
合計で3万円〜6万円程度が目安になるケースが多いです。
ETC1.0と比べると…
従来のETC(1.0)機器は1万円台が主流なので、ETC2.0の価格は約2〜3倍になることもあります。
どうして高いの?
ETC2.0には、次のような高度な機能が搭載されているからです。
- ITSスポットとの双方向通信機能
- 安全運転支援や災害情報取得
- 広域な渋滞情報やルート案内
- ナビやスマホとの連動 など
こういった便利機能のために、機器が高性能になっている=価格が高めになるということなんですね。
買う前にチェックしたいこと
| チェック項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 車載器のタイプ | ナビ連動型/発話型/スマホ連動型 |
| ナビやスマホとの相性 | 機種によって非対応の場合もあり |
| セットアップ店舗 | ディーラー or カー用品店など |
| 割引対象エリアの有無 | 自分のよく走る道が対象かどうか |
対応機器は決して安くありませんが、走行距離が多い方や、安全運転支援を重視する方にとっては投資の価値ありです。
でも、「ちょっと使ってみたい」くらいの方にはハードルが高く感じられるかもしれません。
導入前に、自分の使い方と価格のバランスをしっかり見て決めましょう。
割引が受けられる区間が限られている
ETC2.0を使えば通行料金が安くなる──そう思われがちですが、割引が受けられるのはごく一部の区間だけというのが現実です。
現在、主に割引対象となっているのはこのエリア
圏央道(関東)
- 茅ヶ崎JCT〜海老名JCT〜木更津JCTなど
- 割引内容:通常の高速料金より約2割引
新湘南バイパス(神奈川)
- 藤沢〜茅ヶ崎JCT
- 圏央道と同じく料金割引あり
東海環状自動車道(中部)
- 全線が対象で、通常の高速区間と同等の料金水準に割引されます
その他、社会実験・一部優遇施策もあり
- 「道の駅」一時退出→2時間以内に再進入すれば通し料金(例:三芳PA、道の駅もっくる新城など)
- 都市高速や一部放射高速でもルート条件による割引(大阪・名古屋圏など)
※ただしこれらはエリアや条件が限定され、知らないと使いこなせません。
なぜ“全国一律”ではないの?
- 割引は国土交通省やNEXCO各社の施策次第
- 「利用促進エリア」「交通分散」が目的のため、全国展開はされていません
- 今後の拡大は検討中だが、具体的な計画は未定
導入前にここをチェック!
| チェックポイント | 内容 |
|---|---|
| よく走る道は対象か | 圏央道・新湘南BP・東海環状などならお得 |
| 出張や遠距離が多いか | 長距離運転なら恩恵あり |
| 割引対象外でも便利? | 渋滞回避・安全運転支援が必要かどうか |
まとめ
ETC2.0の料金割引はとても魅力的ですが、すべての高速道路で適用されるわけではありません。
「自分の使う道が対象なのか?」をきちんと確認した上で、導入のメリットを判断するのが大切ですね。
スマホで代替できる情報も多い
ETC2.0は、渋滞情報や災害情報、安全運転支援など、多彩なサービスを提供してくれます。
ですが、その中にはスマートフォンのアプリでも得られる情報がたくさん含まれています。
たとえばこんな情報はスマホでもOK
| 情報の種類 | スマホアプリでできること |
|---|---|
| 渋滞情報 | GoogleマップやYahoo!カーナビでリアルタイム確認可 |
| 交通規制 | ナビタイムやVICSアプリなどで最新情報を取得可 |
| 道路状況・事故情報 | 各地の交通ライブカメラやニュースアプリで確認可 |
| 災害による通行止め | 防災アプリやTwitterなどでも情報共有あり |
つまりどういうこと?
ETC2.0が提供している一部の機能は、スマホアプリでも「無料」で手軽に確認できるんです。
そのため、「わざわざ高価な機器をつけなくても…」と思う人も少なくありません。
それでもETC2.0にしかできないこともある
ただし、以下のような点ではETC2.0に優位性があります。
- スマホを操作せずに自動で情報提供してくれる
- 「道の駅一時退出」などの専用割引制度が使える
- ITSスポットとの双方向通信により、詳細な位置情報と連動
- スマホの通信圏外でも機能する(※ITSスポットと連携)
まとめ
| 視点 | スマホでもOK | ETC2.0が有利 |
|---|---|---|
| 渋滞・道路情報 | ✅ Googleマップなど | ✅ 自動通知・正確な区間情報連動あり |
| 災害・規制情報 | ✅ ニュース・アプリでOK | ✅ 車内で自動表示され安全性が高い |
| 料金割引・制度対応 | ❌ 対応不可 | ✅ 一時退出割引など専用サービス対応 |
| 走行中の操作性 | ❌ 手動操作が必要 | ✅ 自動で音声案内や表示 |
スマホはとっても便利ですが、「手動で確認する」手間や「運転中の操作ができない」ことを考えると、
ETC2.0の“運転に集中できる安心感”は大きな魅力です。
どちらが自分の使い方に合っているか、ライフスタイルに合わせて選ぶのが一番ですね。
対応カーナビやスマホとの接続が必要
その点はETC2.0をより便利に使ううえでとても大切です。
ETC2.0の機能をフル活用するには、カーナビやスマホとの接続が必要なケースがあります。やさしく説明しますね。
対応カーナビやスマホとの接続が必要な理由
ETC2.0は、「ただ料金を支払うだけの機械」ではありません。
交通情報・渋滞情報・危険箇所の通知などを画面で見たり、音声で聞いたりするためには、
その情報を表示・出力する「パートナー」が必要なんです。
カーナビと連動するタイプ(ナビ連動型)
- カーナビに渋滞・事故・災害などの情報を表示できる
- カーナビのルート案内と連携して、渋滞回避ルートの提案もできる
- 視覚的にもわかりやすく、長距離運転には最適
ただし…
➡ ナビがETC2.0対応かどうか事前に要確認!
➡ 古いナビや一部メーカー製品では非対応のことも
スマホと接続するタイプ(スマホ連動型)
- Bluetoothでスマホと連携し、専用アプリで情報を確認できる
- カーナビがなくても、スマホ画面で渋滞・危険箇所情報などがチェックできる
- 情報の受信や確認がアプリ経由になるためスマホ操作に慣れている人向け
注意点: ➡ 車載器と対応しているスマホの機種やOSに制限あり
➡ 一部機種ではアプリの動作が不安定な場合も
機器選びで迷ったら…
| 利用スタイル | おすすめの接続先 |
|---|---|
| ナビをよく使う | カーナビ連動型がおすすめ |
| スマホを使い慣れている | スマホ連動型が手軽で便利 |
| シンプルでいい | 音声案内のみの発話型もアリ |
まとめ
- ETC2.0を最大限活かすには、対応ナビやスマホとの接続が重要です
- 接続しないと「情報は受信してるのに、表示されない」ということも
- 購入前に、機器の対応状況を必ずチェックしましょう!
ちょっとした確認不足で「せっかく買ったのに機能が使えなかった…」なんてこともあります。
不安なときは、お店のスタッフやメーカーの公式サイトで機種対応表を確認してから購入するのがおすすめです。
導入方法とおすすめの選び方
はい、これはETC2.0を導入するかどうか迷っている方にとって、とても気になるポイントですよね。
実際に「スマホで十分じゃない?」という声もよく聞きます。
スマホで代替できる情報も多い
ETC2.0は、渋滞情報や災害情報、安全運転支援など、多彩なサービスを提供してくれます。
ですが、その中にはスマートフォンのアプリでも得られる情報がたくさん含まれています。
たとえばこんな情報はスマホでもOK
| 情報の種類 | スマホアプリでできること |
|---|---|
| 渋滞情報 | GoogleマップやYahoo!カーナビでリアルタイム確認可 |
| 交通規制 | ナビタイムやVICSアプリなどで最新情報を取得可 |
| 道路状況・事故情報 | 各地の交通ライブカメラやニュースアプリで確認可 |
| 災害による通行止め | 防災アプリやTwitterなどでも情報共有あり |
つまりどういうこと?
ETC2.0が提供している一部の機能は、
スマホアプリでも「無料」で手軽に確認できるんです。
そのため、「わざわざ高価な機器をつけなくても…」と思う人も少なくありません。
それでもETC2.0にしかできないこともある
ただし、以下のような点ではETC2.0に優位性があります。
- スマホを操作せずに自動で情報提供してくれる
- 「道の駅一時退出」などの専用割引制度が使える
- ITSスポットとの双方向通信により、詳細な位置情報と連動
- スマホの通信圏外でも機能する(※ITSスポットと連携)
まとめ
| 視点 | スマホでもOK | ETC2.0が有利 |
|---|---|---|
| 渋滞・道路情報 | ✅ Googleマップなど | ✅ 自動通知・正確な区間情報連動あり |
| 災害・規制情報 | ✅ ニュース・アプリでOK | ✅ 車内で自動表示され安全性が高い |
| 料金割引・制度対応 | ❌ 対応不可 | ✅ 一時退出割引など専用サービス対応 |
| 走行中の操作性 | ❌ 手動操作が必要 | ✅ 自動で音声案内や表示 |
スマホはとっても便利ですが、「手動で確認する」手間や「運転中の操作ができない」ことを考えると、ETC2.0の“運転に集中できる安心感”は大きな魅力です。
どちらが自分の使い方に合っているか、ライフスタイルに合わせて選ぶのが一番ですね。
セットアップと取付場所(ディーラー・カー用品店など)
基本的にはこの3か所で対応できます
| 設置場所 | 特徴・メリット |
|---|---|
| カーディーラー | ✔ 新車購入時に一緒に依頼できる ✔ 保証や書類対応も安心 |
| カー用品店 | ✔ オートバックス・イエローハットなど ✔ 即日対応が多い |
| 整備工場・整備士 | ✔ 車検や点検時に依頼できる ✔ 地元のお店でも対応可能 |
セットアップってなに?
セットアップとは、車両情報(ナンバー・車種など)をETC2.0車載器に登録する作業のことです。
これは法律で義務づけられているため、自分ではできません。
登録には下記のような書類が必要になります。
- 車検証(原本)
- ETCカード(所有していれば)
- 身分証明書(店舗によって異なる)
セットアップ&取付の費用目安
| 内容 | 料金の目安 |
|---|---|
| セットアップ料 | 約2,500〜3,000円 |
| 取付工賃 | 約3,000〜8,000円前後 |
| 合計(参考) | 約5,000〜1万1,000円ほど |
※車種や配線の難易度によって変わることがあります
こんなときは事前に確認を!
- ネットで車載器を買った → 「持ち込み対応OKか」確認しましょう
- 古いDSRC機器を使っている → 再セットアップが必要な場合あり
- 土日や繁忙期 → 予約しておくとスムーズです
まとめ
ETC2.0を導入するには、
🔹 専用の車載器の「取り付け」
🔹 車両情報を登録する「セットアップ」
この2つがセットで必要です。
お近くのディーラーやカー用品店で気軽に相談できますので、まずは「どの機種を選ぶか」「費用はいくらぐらいか」聞いてみると安心ですよ。
古いDSRC車載器は再セットアップが必要な場合も
ETC2.0は、もともと「ITSスポットサービス」としてスタートしました。
当時使用されていたのがDSRC車載器(デジタル通信対応のETC機器)です。
その後、2014年に正式に「ETC2.0」という名称に統一されたことで、
それまでのDSRC車載器を使い続けるには、再セットアップが必要になったのです。
再セットアップが必要な人の条件
- 2015年6月30日以前にDSRC車載器をセットアップしている方
- → この場合、ETC2.0の新しいサービスは使えません
- → 機器は対応していても、情報提供機能などが動かない可能性があります
再セットアップとは?
車載器の内部にある「登録データ(車両情報など)」を、ETC2.0用の登録データに更新しなおす作業のことです。
必要なもの
- 車検証(原本)
- ETCカード(所有していれば)
- 本体(車載器)そのもの
再セットアップは、ディーラーやカー用品店、整備工場で対応してもらえます(費用目安:2,500〜3,000円ほど)。
確認方法
「自分の車載器が再セットアップ必要か分からない…」
そんなときは:
- 車載器の型番と製造年月をチェック
- セットアップ証明書(控え)を確認
- 購入店またはメーカーサイトで調べる
まとめ
| 状況 | 必要な対応 |
|---|---|
| 2015年6月30日以前にセットアップ | 再セットアップが必要 |
| 2015年7月1日以降にセットアップ | ETC2.0として使用可能 |
| 型番が古いけど未確認 | 購入店・メーカーに問い合わせ |
車載器そのものはETC2.0対応でも、再セットアップをしないと機能が使えないということがあるので、
「昔つけたETC2.0らしき機器」がある方は、ぜひ一度確認してみてくださいね。
再セットアップでまた便利に使えるようになるかもしれません。
人気のETC2.0車載器モデルと特徴
1. パナソニック CY-ET2620GD
- 価格帯:約15,200円~
- 特徴:音声案内機能付きのアンテナ分離型。カーナビとの連携が不要で、シンプルな操作性が魅力です。
2. パナソニック CY-ET2010D
- 価格帯:約13,350円~
- 特徴:コンパクトなデザインで、取り付け場所を選ばない設計。基本的なETC2.0機能を備えています。
3. パイオニア ND-ETCS10
- 価格帯:約16,000円~
- 特徴:GPS付きで、広範囲の道路情報を取得可能。カーナビとの連携で、より詳細な情報提供が可能です。
4. アルパイン HCE-B120
- 価格帯:約31,000円~
- 特徴:高音質な音声案内と高い互換性を持ち、アルパイン製カーナビとの連携でさらに便利に。
購入時のポイント
- 対応機種の確認:お使いのカーナビや車両との互換性を確認しましょう。
- 取り付け費用:商品価格に加えて、取り付け工賃やセットアップ費用が必要な場合があります。
- 保証とアフターサービス:信頼できるメーカーや販売店からの購入をおすすめします。
まとめ|ETC2.0を導入する前に知っておきたいこと
ETC2.0は、従来のETCに比べて進化したシステムです。
料金の自動支払いだけでなく、渋滞や事故の情報、安全運転支援、災害時の通行情報までカバーします。
特定区間で割引が受けられるなどの経済的なメリットもあり、
物流業界をはじめ、頻繁に高速道路を利用する方にとっては頼れる存在です。
ただし、導入には専用の車載器が必要で価格も高め。
さらに、割引の対象区間が限られていたり、スマホで代替できる情報も多いため、
すべての人にとって「必須」というわけではありません。
ナビやスマホとの接続設定、古いDSRC機器の再セットアップなど、
注意点もあるので、自分の使い方や走行エリアに合っているかをよく見極めることが大切です。
✅ 最後にひとこと
- よく高速を使う人 → 費用対効果あり!
- 安全や災害対応も重視したい人 → 大きな安心感
- ときどき使う人 → 導入の必要性をじっくり検討して◎

































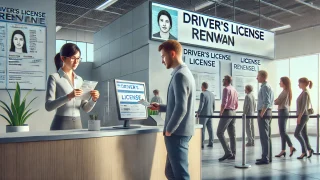


コメント