新年度のスタートとともに、新入社員を迎えたばかりの企業にとって、頭を悩ませる事態が起きています。
それは「入社後すぐの早期退職」。
入社式からわずか数日、あるいは1週間以内に辞表が提出されるケースも珍しくなくなってきました。
「これから一緒に成長していく」と期待をかけていた人材が、なぜこんなにも早く離れてしまうのでしょうか。
実はそこには、企業側の“伝え方”や“受け入れ体制”に見落としがあるかもしれません。
採用にかかるコスト、育成の手間、既存社員への影響……。
早期退職は単なる「個人の問題」ではなく、企業全体の経営課題とも言えるのです。
本記事では、早期退職が起こる背景を整理し、企業ができる具体的な対策についてやさしく解説していきます。
採用活動を「つなぐ力」へと変えていくために、今こそ見直すべきポイントとは?
入社後すぐ退職する社員が増えている理由
新年度を迎え、新入社員を受け入れたばかりの企業も多いかと思います。
そんな中、入社直後に退職してしまう若手社員が増えているという声をよく耳にします。
この記事では、入社後すぐに辞める人が増えている背景を、企業側の視点で整理し、
今後の採用活動や定着率アップに活かせるヒントをお届けします。
入社前と入社後のギャップが大きい
入社前に期待していた仕事内容や環境と、実際の業務内容に差があると、
新入社員は「思っていたのと違う」と感じてしまいます。
企業説明会や面接で「良い面」ばかり伝えていると、入社後に落差が大きくなりがちです。
特に若い世代は“ギャップ”に敏感で、その違和感が早期退職につながります。
教育・サポート体制が整っていない
入社後のフォロー体制が不十分だと、不安や戸惑いが募りやすくなります。
「何をすればいいかわからない」「質問しづらい」状態が続くと、
自信を失ってしまい、「自分には向いていない」と辞める原因に。
新入社員には、安心して相談できる環境が必要です。
職場の雰囲気・人間関係に馴染めない
「人間関係が合わない」「空気が重い」など、
職場の雰囲気に違和感を持つと、居心地が悪くなりやすいです。
とくに20代は、職場の雰囲気を重視する傾向が強く、
歓迎ムードがなかったり、冷たい対応をされると「ここは自分の居場所じゃない」と感じやすくなります。
理不尽な指導や過度な期待
「なんでそんなこともできないの?」という言葉や、
上司の感情的な指導が、新人にとっては大きなストレスになります。
最近は、昭和・平成の「背中を見て覚えろ」的な教育では通用しなくなっています。
個々の特性を見て、丁寧に関わる姿勢が求められています。
世代の価値観の変化と“見切りの早さ”
Z世代やミレニアル世代は、「違う」と感じたらすぐに行動を起こす傾向があります。
長く我慢するよりも、「無理をせず早く次に進む」考え方が一般的です。
これは決して“根性がない”のではなく、時代の変化とも言えます。
企業側も、柔軟な理解と対応が求められています。
まとめ
早期退職の背景には、さまざまな理由がありますが、
その多くは「会社と社員のすれ違い」によって生まれています。
だからこそ、採用段階からリアルな情報を伝えること、
そして、入社後の“安心できる環境”を整えることが、今まで以上に大切になってきます。
「辞められた理由」ではなく、「続けてもらえる工夫」を考えることが、
これからの採用と定着のカギになりそうです。
企業が被る“早期退職”による損失とは
新入社員や中途社員が入社後すぐに退職してしまうと、企業にはさまざまな「目に見えにくい損失」が発生します。
ここでは、主な4つの損失を紹介します。
採用コスト・教育コストの無駄
人材をひとり採用するには、求人広告費や面接の人件費など、多くのコストがかかっています。
さらに入社後は、OJTや研修などに人や時間が必要になります。
せっかくかけた時間とお金が、短期間で“ゼロ”になるのは大きな痛手です。
現場社員への負担が増える
新入社員が抜けた穴を埋めるために、現場の社員がその分の仕事をカバーしなければならなくなります。
これにより、残業が増えたり、ストレスが溜まったりして、最悪の場合、既存社員のモチベーションや離職にもつながりかねません。
組織全体の士気が下がる
「せっかく育てようと思ったのに辞められた…」
「何かウチの会社に問題があるのでは?」
こんな気持ちが広がると、組織の雰囲気が暗くなります。
とくに新人の定着が続かないと、会社の信頼感そのものが揺らいでしまうことも。
「すぐ辞める会社」という評判につながる
採用サイトやSNSで「入社してすぐ辞めた」という情報が出回ると、企業のイメージダウンにもつながります。
応募者の数が減るだけでなく、良い人材が集まりにくくなるという悪循環に。
中小企業ほどこの影響は大きく、注意が必要です。
まとめ
早期退職は「ひとり辞めただけ」と軽く見てしまいがちですが、実際には、会社の成長を止める大きなリスクをはらんでいます。
採用・育成・職場環境を見直すことは、企業の未来を守る第一歩です。
「辞めさせない工夫」が、企業の強さをつくる時代になっています。
会社ができる早期退職の防止策【入社前編】
早期退職を防ぐためには、入社してからではなく「入社前」からの工夫が大切です。
ここでは、採用活動や内定者フォローの段階で、企業ができる主な対策を4つ紹介します。
リアルな情報を伝える「RJP」の実施
RJP(リアリスティック・ジョブ・プレビュー)とは、会社の「良いところ」だけでなく「大変なところ」もあえて伝える手法です。
たとえば、
「繁忙期は残業が多くなります」
「部署によっては電話対応がメインです」など、
実際の働き方を事前に伝えることで、入社後のギャップを減らすことができます。
見せ方を工夫すれば、ネガティブにはならず、「誠実な会社だ」と感じてもらえることもあります。
社風や職場の雰囲気が伝わる“接点”を増やす
面接や説明会だけでは、職場のリアルな雰囲気は伝わりづらいものです。
可能であれば、
・先輩社員との座談会
・オフィス見学や社内イベントへの招待
・SNSや社内ブログでの情報発信
などの方法で、内定者との接点をつくりましょう。
「どんな人と働くのか」が事前にわかることで、安心感が生まれます。
内定後のフォローを“手厚く・こまめに”
内定を出したあと、入社までの期間が長いと、不安や迷いが生まれやすくなります。
そこで、以下のようなフォローを意識すると効果的です:
- 定期的な連絡(LINEやメール)
- 簡単な学習コンテンツの提供
- 配属予定の上司からの一言メッセージ
企業からの関心や期待が伝わることで、入社のモチベーションを維持できます。
ミスマッチを防ぐ「選考の精度」を見直す
「誰でもウェルカム」な採用では、入社後のミスマッチが起こりやすくなります。
だからこそ、選考では“スキル”だけでなく、“価値観の相性”も大切にしましょう。
たとえば:
- 性格診断を活用する
- 「うちに合う人・合わない人」を社内で共有する
- 面接には現場の社員も同席する
こうした取り組みで、入社後の違和感を減らすことができます。
まとめ
早期退職は「入社してからの問題」と思われがちですが、
実は、入社前のすり合わせやコミュニケーションが大きなカギを握っています。
“採用”は「選ぶ」だけでなく「つながる」こと。
企業と求職者の双方が納得して前に進めるような、丁寧な準備を心がけていきたいですね。
会社ができる早期退職の防止策【入社後編】
新入社員が「入社してよかった」と思えるかどうかは、
入社後のサポート体制と職場の雰囲気にかかっています。
ここでは、入社後に企業ができる4つの防止策を紹介します。
オンボーディングを丁寧に行う
「オンボーディング」とは、新入社員がスムーズに職場に慣れ、活躍できるようにサポートする一連の取り組みです。
・社内ルールや業務の流れを丁寧に教える
・定期的な面談を行い、悩みや不安を聞く
・配属先のメンバーと一緒に働く機会を増やす
入社して間もない時期は、ちょっとした戸惑いが「辞めたい」に変わることも。
だからこそ、最初の3ヶ月がとても大事なのです。
メンター制度の導入で「相談できる人」をつける
直属の上司には言いにくい悩みも、年齢の近い先輩なら話しやすいもの。
そこで効果的なのが「メンター制度」です。
新入社員に専属の相談役となる先輩社員をつけることで、職場への不安や孤独感をやわらげることができます。
「ちゃんと見てもらえている」という安心感が、定着につながります。
定期的なフォローアップ面談を実施する
月1回など、定期的な1on1面談を行うことで、小さな不安やモヤモヤに早めに気づくことができます。
「困っていることはない?」と尋ねるだけでなく、
・職場に馴染めているか
・仕事内容にギャップはないか
・体調やメンタル面は大丈夫か
などを、やさしく掘り下げていくのがポイントです。
チーム全体で“新人を支える空気”をつくる
新人をサポートするのは、上司だけではありません。
現場の雰囲気そのものが、新入社員の安心感に直結します。
たとえば、
・「わからないことあったら何でも聞いてね」と声をかける
・歓迎会やランチ会などで打ち解ける機会をつくる
・小さな成功もチームで一緒に喜ぶ
こうした日常の積み重ねが、「ここでがんばりたい」という気持ちを育てます。
まとめ
入社後の早期退職を防ぐためには、業務の説明だけでなく、「人とのつながり」や「安心できる環境」が何より大切です。
新入社員は、何気ない表情や言葉から職場の空気を感じ取っています。
だからこそ、企業側からの“寄り添い”が必要なのです。
「この会社で続けたい」と思ってもらえるように、入社後こそ、ていねいなサポートを心がけていきましょう。
こんな企業が危ない!早期退職を招く企業の共通点
早期退職は「たまたま人材に恵まれなかった」ではなく、企業の側に共通する“落とし穴”があることも少なくありません。
ここでは、早期離職が起こりやすい企業に共通する特徴を紹介します。
思い当たる点があれば、今からでも改善のチャンスです。
求人情報が“いいこと”だけで埋め尽くされている
「アットホームな職場」「残業ほぼなし」「未経験でも安心」など、魅力的な言葉ばかり並べた求人には注意が必要です。
入社後に現実とのギャップを感じた社員は、すぐに不信感を持ちます。
「聞いていた話と違う」と思われると、信頼の糸が切れてしまうのです。
リアルな情報を誠実に伝える姿勢が求められます。
現場任せで育成やフォロー体制が不十分
新入社員の育成が「現場にお任せ」になっていませんか?
明確なマニュアルやサポート制度がないままだと、教える側も戸惑い、受け入れられる側も不安になります。
「とりあえずやってみて」では、離職のリスクが高まります。
育成も業務と同じように“仕組み化”することが大切です。
社風や価値観の共有ができていない
会社として大事にしている想いや文化が、社員一人ひとりにまで伝わっていない企業では、「自分がこの組織に合っているのかわからない」という不安が広がります。
採用時や入社時に、「自社の価値観」「仕事のやり方」を伝え、納得感を持って働ける状態をつくることが必要です。
忙しすぎて“新人への気配り”が足りていない
現場が慢性的に人手不足だったり、常に忙しい状態だと、どうしても新人への声かけやフォローが後回しになります。
「歓迎されていない」「誰にも頼れない」と感じた新人は、たった数日でも心が折れてしまうことがあります。
忙しい中でも、“小さな気配り”が大きな差を生みます。
新人が「意見を言える空気」がない
「何かあっても言えない」「質問したら怒られそう」
そんな空気があると、悩みを抱えたまま辞めてしまう人が出てきます。
風通しの良さは、早期退職を防ぐ最大の防波堤です。
「どんなことでも話していいよ」と伝える文化づくりが必要です。
まとめ
早期退職を招く企業には、いくつかの共通した特徴があります。
しかし、それは“努力次第で変えられる”ものばかりです。
今いる社員を大切にし、これから入る人が安心して働けるように、一つずつ見直していくことが、会社の未来を守ることにつながります。
まずは「自社は大丈夫か?」を見つめ直すことから始めてみませんか。
まとめ
いま、多くの企業が直面している「入社後すぐの早期退職」。
新入社員の一言や行動に戸惑い、悩む人事担当の方も少なくありません。
でもその背景には、入社前後のすれ違いや、企業と本人のギャップが潜んでいることが多いのです。
だからこそ、採用の段階から「リアル」を伝え、受け入れた後も丁寧なフォローが大切になります。
会社にとっても、新しく入ってきた人にとっても、スタートはとても大事な時間です。
その時間を、安心と信頼で満たせるように。
「育てる力」も「伝える力」も、これからの企業には欠かせない大切な資産です。
一人ひとりが長く活躍できる職場づくりを、一緒に目指していきましょう。

























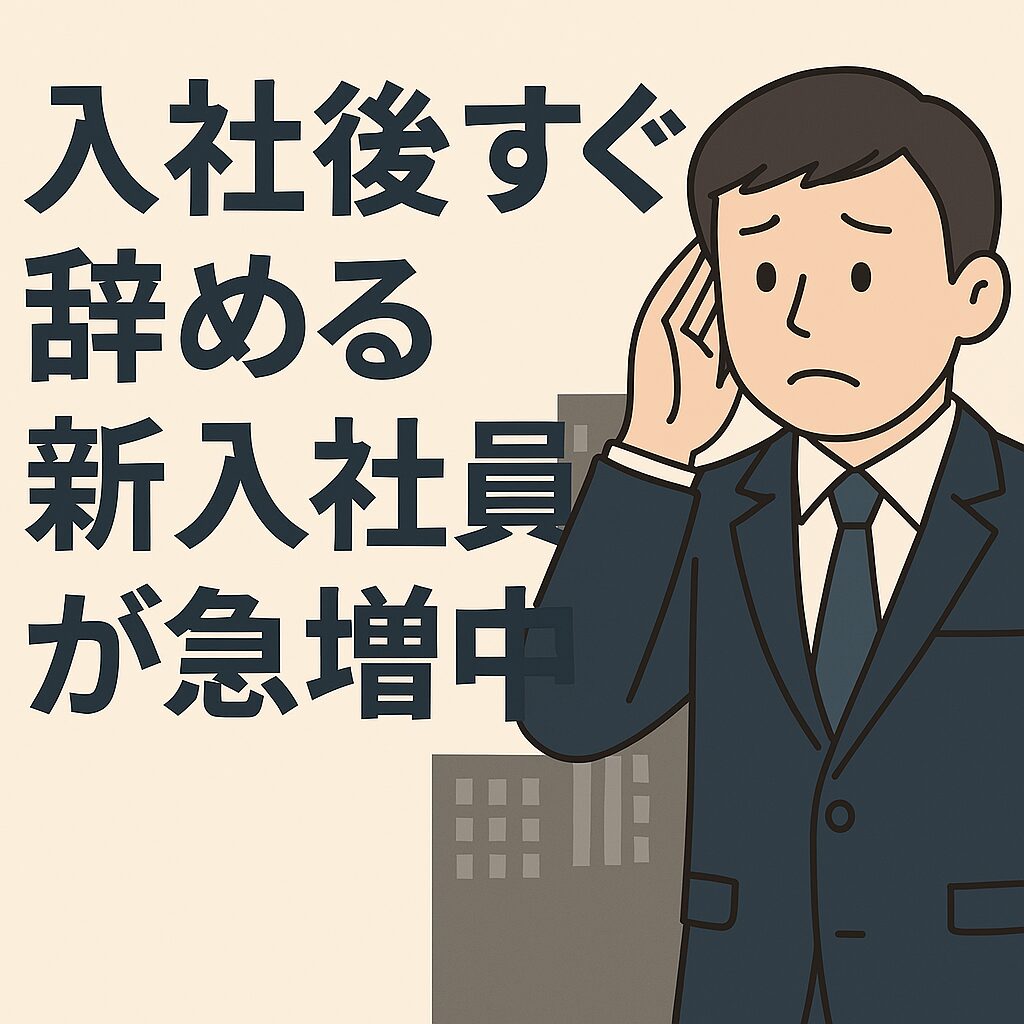







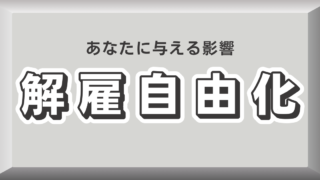
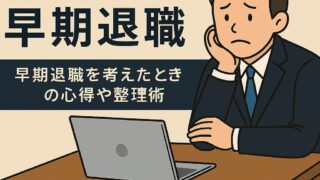

コメント