「退職したいけど、直接会社に言えない…」そんな不安を抱えたとき、手軽に利用できる退職代行サービスは心強い存在です。
その中でも話題を集めたのが「モームリ」。
20代を中心に人気を集め、4万人以上が利用したという実績がある一方で、2025年に「弁護士法違反の疑い」で警視庁の家宅捜索を受けたことが報じられました。
本記事では、「モームリ」の違法性や構造的な問題点、安全な退職代行サービスの選び方を解説します。
この記事を読むことで、トラブルを避けながら、自分に合った退職方法を見つけるヒントが得られるはずです。
モームリとは?退職代行サービスの概要
退職代行サービス「モームリ」は、20代の若者を中心に人気を集めたが、後に法的トラブルも抱えたことで注目を浴びた。
まずはその基本概要を押さえておこう。
モームリのサービス内容とは?
モームリは「退職の意思表示」を代行してくれるサービス。
どんなサービスだったのか?
- 本人に代わって会社に退職意思を伝える
- 会社とのやり取りはすべてモームリが担当
- LINEや電話を使って簡単に依頼できる仕組み
利用の流れ(シンプルなステップ)
- LINEやWebフォームから相談
- 支払いと本人確認
- モームリが勤務先に連絡
- ユニフォームや備品の返却方法も代行連絡
この手軽さが、特に人間関係に悩む若者たちに支持されました。
誰が利用していたのか?
利用者の特徴を知ることで、モームリの社会的なニーズが見えてくる。
主なユーザー層
- 利用者の6割以上が20代
- 正社員からアルバイトまで幅広く対応
- 勤続1年未満の人が多い傾向
利用動機の例
- 「上司に辞めると言えない」
- 「辞めさせてくれない」
- 「パワハラが怖い」
- 「感情的な引き止めが嫌」
こうした理由から、自分で退職を言い出すのが難しい人々がモームリを選んでいました。
運営会社の背景と成長スピード
運営元の急成長ぶりも注目されましたが、そこにはリスクも伴っていました。
運営会社について
- 株式会社アルバトロス(東京都品川区)
- 2022年に設立
- 創業からわずか3年で従業員数70名以上に成長
成長要因
- 「即日退職OK」「会社と話さなくていい」などのキャッチコピー
- SNSや動画メディアを活用したマーケティング
- 利用者レビューや「口コミ文化」を巧みに利用
モームリが注目された理由
退職のハードルを下げた存在として評価されつつも、法的リスクが潜在していた。
人気の理由
- 簡単に申し込めてストレスがない
- 弁護士よりも費用が安い
- 誰にも会わずに辞められる
問題視された点
- 弁護士法違反(非弁行為)の疑い
- 「交渉はしない」としていたが、一部で弁護士とのやりとりを“あっせん”していた可能性
モームリに起きた問題とは?
人気を集めたモームリですが、2025年には大きな法的トラブルに発展しました。
表面上は「合法」とされていたサービスに、なぜ違法性が疑われたのでしょうか?
家宅捜索の衝撃|弁護士法違反の疑い
2025年10月、警視庁は100人体制でモームリ本社と複数の法律事務所に家宅捜索を実施しました。
捜索の理由
- 弁護士法72条違反(いわゆる「非弁行為」)の疑い
- 弁護士資格のない者が「退職交渉」をしていた可能性
- 有償で弁護士を“あっせん”していたとの見方
弁護士法72条とは?
- 弁護士以外の者が報酬目的で法律業務を行うのは禁止
- 特に「交渉」や「あっせん」は違法とされる
- 通知のみなら合法、だが境界線が非常にあいまい
モームリの主張と実態のギャップ
公式サイトでは「通知業務に徹している」としていましたが…。
モームリ側の説明
- 「交渉はしない」「通知のみなので違法ではない」と主張
- サービス紹介でも「安心・合法」とアピール
現場の実態(疑われた内容)
- 退職に関するやり取りの中で、会社との交渉が発生
- 弁護士の紹介や仲介が「有償」で行われていた可能性
- LINEやQ&A形式では“曖昧な説明”も見受けられた
構造的な問題|退職代行市場の限界
法的制限と収益構造の狭間で、サービスそのものが限界に達していたとも言えます。
「伝言役」だけでは差別化が難しい
- 法律上、許されるのは単なる伝言・通知業務
- 他社との差別化が困難 → 結果として価格競争が激化
- 安価な料金で人件費・広告費をまかなうのが困難に
交渉ニーズとのジレンマ
- 実際の現場では「退職させてくれない」「引き止められる」など交渉が不可避なケースが多発
- 顧客ニーズに応えようとするほど、違法リスクが高まるという構造的矛盾が生じた
退職代行サービスに必要な法的認識
利用者・運営者ともに法律の基礎理解が欠かせない時代です。
違法性が問われやすい行為
- 有償での弁護士あっせん・仲介
- 会社と条件交渉(例:退職日、有休取得、給与未払い)
- 「代わりに話し合っておきます」は完全アウト
合法的に運営するためには?
- 弁護士法人が運営 or 弁護士監修があることが最低条件
- 完全に通知業務のみに特化すること
モームリの一件は、退職代行業界における“グレーゾーン”のリスクを改めて浮き彫りにしました。
次章では、これを踏まえて「安全な退職代行サービスの選び方」を紹介します。
なぜモームリが問題に発展したのか?構造的問題を解説
モームリの問題は、単なる「違法性の疑い」ではなく、退職代行ビジネス自体が抱える構造的な課題に起因していました。
この章では、業界の“限界構造”に焦点を当てて解説します。
退職代行のビジネスモデルに潜むジレンマ
退職代行は「シンプルな通知」だけを扱う業種ですが、それでは差別化が難しくなります。
法的制限の壁
- 弁護士でないと「交渉」ができない → 非弁行為のリスク
- 通知に徹すれば合法だが、業務内容が極めて限定的
サービス向上との矛盾
- 顧客が求める「会社との交渉」に応えると違法になる
- サービス品質を上げたくても法律がブレーキになる
✅「親切に対応したい」という姿勢が、違法行為に繋がる危険性が常に付きまとう業界です。
参入障壁の低さと価格競争
誰でも参入しやすいがゆえに、競争過多と利益圧迫が起きているのが現状です。
参入が簡単すぎる
- 法的知識や資格が不要(通知業務だけなら)
- 小規模資本でもスタート可能 → 新規業者が続々登場
競争が加速 → 単価が下がる
- 「料金最安値」「即日対応」などで消耗戦に
- 利益確保のために“グレーゾーン”に踏み込むケースも
| 問題 | 内容 |
|---|---|
| 利益率の低下 | 法的制限により提供できるサービスが少ない |
| 差別化困難 | サービスの質で勝負できず価格勝負に偏る |
| 法律違反リスク | 顧客ニーズに応えると非弁行為の可能性 |
利用者のニーズと現実の乖離
モームリが問題化した背景には、顧客の期待とのズレもありました。
顧客が本当に求めていること
- 「退職を拒否されたときの対応」
- 「有休の買取・退職金などの条件交渉」
- 「パワハラの相談・証拠提出の助言」
通知業務ではカバーできない現実
- 上記のようなニーズはすべて「法律業務」に該当
- 通知代行だけでは顧客の不満が解消されない
- クレームを避けるために、違法リスクのある“親切対応”に流れがち
モームリが限界を迎えた理由とは?
退職代行ビジネスの構造上の限界が、モームリの違法疑惑につながったと考えられます。
善意が仇になった構造的背景
- 法的グレーゾーンで運営するビジネスモデル
- 利益を得ながら違法リスクを避けるのは至難
- 成長と共に避けられない“交渉”の場面が増加
今後、同様のサービスにも影響が?
- 法整備や取り締まりが強化される可能性
- 業界全体で「弁護士連携」または「縮小運営」が求められる流れに
モームリの問題は、同業他社やこれから退職代行の利用を考える人々にとっても無視できない教訓となりました。
次の章では「安全な退職代行の選び方」を具体的に紹介します。
安全に退職するには?代行サービスの正しい選び方
退職代行を利用すること自体は合法ですが、選び方を誤るとトラブルに巻き込まれるリスクも。
ここでは、安全なサービスを見極めるためのチェックポイントを解説します。
まず理解しておきたい「合法」と「違法」の違い
退職代行には、法律上許される範囲と超えてはいけないラインが明確に存在します。
合法な退職代行の特徴
- 本人の退職意思を「通知」するだけ
- 引き継ぎや条件交渉には一切関与しない
- 弁護士または弁護士監修のもと運営されている
違法となる可能性がある行為
- 退職条件や未払い給与などの「交渉」を行う
- 弁護士資格がないのに「代理人」を名乗る
- 弁護士に有償で依頼者を“あっせん”する
✅ 通知=OK/交渉=NG が鉄則。
違法業者のリスクを避けるため、仕組みを知っておくことが大切です。
信頼できる退職代行サービスを見極めるポイント
価格や対応だけでなく「法的な安全性」が最優先です。
チェックリスト(選ぶ際に確認したい6つの項目)
- ✅ 運営主体が「弁護士」「労働組合」「一般企業」のどれか
- ✅ 弁護士監修・所属の有無
- ✅ 料金体系が明瞭(追加料金なし)
- ✅ 交渉・あっせんをしないと明言している
- ✅ 実績・口コミ・メディア掲載などの信頼性
- ✅ LINEなどでの迅速な相談対応が可能
比較表:運営形態ごとの特徴
| 運営主体 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 弁護士・弁護士法人 | 法的交渉も対応可能/安心 | 費用がやや高い(3〜5万円) |
| 労働組合 | 有休取得なども交渉可能/コスパ◎ | 非弁リスクが完全にゼロではない |
| 一般企業(民間) | 安価・スピード対応 | 交渉できず限界がある/違法リスクあり |
おすすめの退職代行サービス3選(2025年最新版)
信頼性・コスパ・対応力を兼ね備えた人気サービスを紹介。
弁護士監修で安心|退職代行Jobs
- 弁護士監修・法的トラブルも対応
- 24,800円〜とコスパも◎
- スピーディーな返信で不安を軽減
即日対応が魅力|退職代行ガーディアン
- 労働組合が運営
- 有休取得など交渉も可能
- LINE対応で即日退職OK
最安級のコスパ|退職代行オイトマ
- 24,000円と業界最安レベル
- 弁護士提携あり
- 即日退職・有休取得もサポート可
トラブルを避けるためにできること
代行サービスに頼る前に、最低限の準備や知識を持つことも大切です。
準備しておくべきこと
- 社員証・制服・会社の備品を揃えておく
- 引き継ぎ資料を簡潔にまとめておく(自衛のため)
- 退職の意思表示を証拠として記録(メール or LINE)
利用前に相談しておきたい相手
- 労働基準監督署(無料相談)
- 地方弁護士会の法律相談(初回無料のことも多い)
- 家族や信頼できる知人への事前相談
退職は人生の大きな転機。安心して次のステップへ進むためにも、信頼できる代行サービス選びが重要です。
次の章では、退職代行のメリット・デメリットを冷静に整理していきます。
退職代行のメリット・デメリットを整理
退職代行サービスは「退職できない…」という悩みを解消する強力な手段ですが、万能ではありません。
利用前に、メリットとデメリットをしっかり理解することが重要です。
退職代行を使うメリット
退職代行には精神的・実務的な負担を減らせるメリットがあります。
心理的ハードルを下げられる
- 上司や同僚に直接言う必要がない
- 職場と一切関わらずに辞められる
- 言い出せずにいた人でもスムーズに行動できる
✅「辞めたいのに言えない」という精神的な負担が軽減され、ストレスから解放される点は大きな利点です。
即日退職も可能
- 連絡をしたその日から出社不要に
- 「もう行きたくない…」と感じた日でも対応可能
- 有給消化の交渉も代行可能(労働組合・弁護士の場合)
手続きがすべて代行される
- 書類のやりとりも郵送で完結
- 面倒なやりとりなしで退職できる
- 24時間対応のサービスも多く、急な相談にも強い
退職代行を使うデメリット
一方で、退職代行には法的・実務的な注意点も存在します。
費用がかかる
- 相場:民間企業2〜3万円、弁護士4〜5万円
- 自分で辞める場合は無料
- 費用対効果の見極めが必要
会社との関係が悪化する可能性
- 一方的な通告になるため、感情的な摩擦が残ることも
- 今後その業界で転職を考えている人は慎重に
⚠️特に業界内でのつながりが強い職場(例:医療・教育・士業)では影響を考慮すべきです。
トラブル対応には限界がある
- 非弁業者の場合、未払い賃金や有休取得の交渉ができない
- 会社から損害賠償請求されるリスク(まれに)
- 弁護士監修のない業者は法的に不安
退職代行が向いている人・向いていない人
退職代行が向いているケース
- 上司がパワハラ・高圧的で話すのが困難
- 精神的に限界で会話すら難しい
- 退職を申し出ても拒否されている
- 出社せずに辞めたい
向いていない・慎重になるべきケース
- 業界内での評判が重要視される職種
- 円満退職を目指したい人
- 長期的に信頼関係を維持したい人
まとめ表|退職代行のメリット・デメリット一覧
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 精神的負担 | 上司と話さず辞められる | 感情的な摩擦が残る可能性 |
| 手続き面 | 書類・連絡すべて代行可 | 法的交渉には限界がある |
| スピード | 即日退職も可能 | 費用がかかる(2〜5万円) |
| 信頼関係 | 人間関係を断ち切れる | 会社との関係悪化の恐れ |
退職代行には確かに大きなメリットがありますが、サービスの選び方と状況判断を誤ると逆効果になることもあります。
次章では、こうした情報を踏まえた上で、退職代行を検討している方に向けた「まとめとアドバイス」をお届けします。
まとめ
退職代行サービス「モームリ」は、若者を中心に支持される一方で、法律上のリスクと業界の構造的な問題に直面し、弁護士法違反の疑いで警察の捜査を受ける事態に至りました。
今回の件から学べることは、「退職代行」は万能ではないということです。
利用者としても、どのサービスが合法なのか、どんなリスクがあるのかを正しく理解し、自身を守る判断力が求められます。
安全に退職するためには、信頼できる弁護士法人が運営するサービスを選ぶことが大切です。
また、会社に退職を言い出せない自分を責める必要はありません。
大切なのは、自分らしい働き方を見つけ、健やかな生活を送ることです。
あなたの選択が、より良い未来につながることを心から願っています。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
🔖 注釈・補足事項(記事末または対象セクション末に挿入)
🔸 注釈一覧
- 本記事は2025年10月時点の情報をもとに作成されています。今後、法的判断や業界動向の変化により内容が変わる可能性があります。
- 退職代行サービスの合法・違法の判断は、具体的なサービス内容や状況により異なります。詳細については、必ず弁護士など専門家にご相談ください。
- 本記事内の「モームリ」に関する記載は、報道および公式発表に基づくものであり、運営元への断定的な非難や中傷を目的としたものではありません。
📚 出典・参考リンク(出典セクションまたは脚注形式)
- 【1】弁護士ドットコムニュース「退職代行モームリに家宅捜索、弁護士法違反の疑い」
- 【2】ABEMA TIMES「退職代行『モームリ』に警視庁が家宅捜索」
- 【3】退職代行サービス比較ナビ「2025年最新|退職代行会社おすすめ比較20選」
- 【4】日本弁護士連合会「隣接士業・非弁活動・非弁提携対策」
🔄 更新方針の案内(記事末に添えると好印象)
🔁 本記事は、退職代行業界および「モームリ」に関する最新の法的動向や報道に応じて、内容を随時見直し・更新いたします。新たな情報が確認された場合は速やかに反映いたします。




























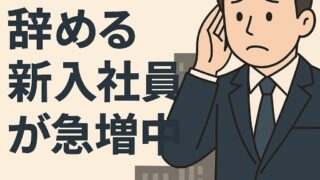

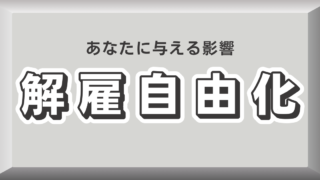

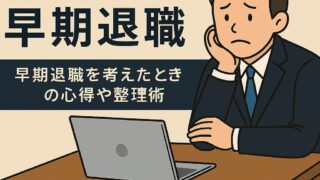
コメント